会社で最も重要な決定権である「代表権」を持つ「代表取締役」は一般的に1名のみが選定されている例が多いです。
しかし、共同経営者がいる場合など、会社の経営形態によっては、代表取締役を2名以上、複数名選定して共同代表で経営を行いたいと考える経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では代表取締役を2名〜複数人選定する場合の手続きや注意点について解説します。

会社で最も重要な決定権である「代表権」を持つ「代表取締役」は一般的に1名のみが選定されている例が多いです。
しかし、共同経営者がいる場合など、会社の経営形態によっては、代表取締役を2名以上、複数名選定して共同代表で経営を行いたいと考える経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では代表取締役を2名〜複数人選定する場合の手続きや注意点について解説します。
専門家に依頼せずともやろうとすれば自分で手続きできてしまう代表取締役の変更登記ですが、いざ始めたものの
・自分で作成した書類はこれで合っているのか?
・不足している手続きがあるのではないか?
など、自分のやり方が正しいのか不安になってしまうものです。
GVA 法人登記を利用すれば、必要情報を入力するだけで代表取締役の変更登記に必要な登記申請書や株主総会議事録などの必要書類を最短7分で自動作成、専門家に依頼せず自分で申請できます。郵送申請サポートもついていますので、法務局に行かずに申請でき手続き時間を大幅に短縮できます。
「会社の代表取締役は何人までいていいのですか?」と聞かれることがありますが、会社法上、代表取締役の人数制限はなく、1つの会社に複数人いても問題はありません。
しかし、代表取締役は会社法上、会社の業務執行機関として強い権限(代表権)を有しており、複数人選定するべきかを検討するにあたっては、まずは代表取締役とは会社法上どのような権限を有するのかについて検討を行う必要があります。
代表取締役とは取締役の中で代表権と呼ばれる会社を代表する権限を付された取締役のことをいい、会社法第349条第4項において、代表取締役は以下のような権限を有することが定められています。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
つまり、代表取締役とは会社の業務にかかわる行為の全てをすることができると定められているのです。
また、仮に会社が代表取締役単独では一定の行為については有効にできない旨の制限を行っていても、それを知らない第三者に対しては制限が効力を生じないことになっています(会社法第349条第5項)。
以上のようなことから会社法上も代表取締役は会社の業務執行機関として最も強い権限を有するものとされていることがわかります。
そんな会社で最も強力な権限を有する代表取締役ですが、冒頭でも解説したとおり、会社法上は人数に制限はありません。
正確には取締役でなければ代表取締役にはなれないので、取締役の人数がその会社の代表取締役の人数の上限となりますが、その範囲内であれば、会社法上は代表取締役を何人選任しても会社の自由であるといえます。
では、代表取締役を複数選定することにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。共同代表制を検討している方はよく理解しておきましょう。
代表取締役を複数選定するメリットとしては次のようなものが挙げられます。
・機動的な会社経営が可能になる
代表取締役が複数いる場合、当然に会社の業務執行をできる人が複数になるため、意思決定から行動までのプロセスが非常にスピードの速いものとなります。
そのため、機動的な会社経営が可能となるでしょう。これは支店や営業活動を行う拠点が離れている会社の場合にも有効な方法といえます。
・代表取締役の業務負荷を軽減できる
小規模な会社の場合であっても、代表取締役の職務範囲は非常に広く、業務負荷が高い会社も少なくありません。
そうした会社の場合で代表取締役を複数選定した場合には、職務を複数でこなすことができるため、代表取締役一人当たりにかかる業務負荷を軽減することができます。
これは、経営者が、代表取締役として職務だけでなく、営業や開発などの多種にわたる業務を行っている場合にも有効な方法といえるでしょう。
他方で、代表取締役を複数選定する場合には次のようなデメリットがあります。
・意見の対立が生じた場合の調整が困難
共同経営者全員が代表取締役となったようなケースでよく見られる例ですが、業務執行の決定や職務執行は、各代表取締役として単独で行えるものもあり、意見に対立が生じた場合にその調整が困難となります。
特に取引先など会社の外との関係では、それぞれの代表取締役は有効に契約を結べるため、社内での意見がまとまっていないのに一人の経営者が単独で契約をしてしまったというケースでは、事後的に会社が効力を否定することは非常に困難となります。
・対外的な窓口が不明確になる
会社の外から見た場合、複数の代表取締役がいる場合、どの方に交渉や話を通せばよいのか不明確となります。
あらかじめ会社の外へ各代表取締役が何を担当しているのかという点を示しておくことである程度こうした問題を回避することができるでしょう。
代表取締役を複数とした場合の法的なリスクとしては先ほど少し触れた通り、各代表取締役が代表権を有しており、会社内部でこうした権限に制限を課しても、こうした制限を知らない会社の外の人(善意の第三者)との関係では、その制限が効力を生じない点です(会社法第349条第5項)。
そのため、その他の代表取締役に無断で銀行などから借り入れを行う、商品の売買を行う、広告を出す等の契約締結をしても、その代表取締役の職務権限の範囲外であることを理由に会社にその契約の効力が及ばないと主張することは非常に難しくなります。
このように、単独で会社内の意思に反して契約締結など様々な行為をされてしまうリスクが代表取締役を複数置く場合には生じます。
代表取締役を複数にする場合には以下のような手続きが必要となります。なお、代表取締役は取締役の中から選ばなければいけません。
そのため、取締役でない人を代表取締役に選定するためにはまず、取締役として選任する必要があり、この場合には株主総会の決議が必要となる点に注意しましょう。
取締役会設置会社における代表取締役の選定方法は、取締役会の決議(会社法第362条第2項第3号)または定款で定めがある場合には株主総会決議によって選定することも可能です(会社法第295条第2項)。
取締役会を設置していない会社の場合は、定款による選定、株主総会決議、定款の定めによる取締役の互選による方法の3つの手続きがあります。
取締役の互選により選定する場合には、各取締役が誰を代表取締役とするかについて、選びその結果過半数または全員の一致があった候補者を代表取締役とすることになります。
なお、取締役の互選についてはこちらの記事もご参考ください。
代表取締役の氏名及び住所は登記事項となっています(会社法第911条第3項第14号)。そのため、新たに代表取締役に就任した場合には、代表取締役就任の登記が必要となります。
代表取締役就任の登記は変更が生じた日から2週間以内に行う必要があります。前述の選定手続きを経たら直ちに登記手続きが行えるよう、選定手続きに応じて適切な添付書類を準備しておきましょう。
代表取締役の就任登記における添付書類や手続き内容の詳細はこちらの記事もご参考ください。
代表取締役を新たに選定するだけであれば原則として定款変更は必要ありません。ただし、以下のようなケースでは定款変更のために株主総会を開催する必要があります。
・定款で代表取締役の人数を決めており、その人数を超える場合
・定款で取締役の互選により決定される旨の定めがなく、互選により決定する場合
・取締役会設置会社が株主総会決議によって代表取締役を選任できることとする場合
以上のような場合には代表取締役の選定を行う前に定款変更のための株主総会を行う必要があります。
代表取締役選任の株主総会議事録テンプレート(ひな形)は、以下からダウンロードできます。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で議事録の作成を検討している方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。.png?w=479&h=676)
※状況により内容を変更してご利用ください
代表取締役を複数置くことはメリットもデメリットもあり、その会社の経営方針に合わせた選択をする必要があります。また、選定した際には登記を行う必要があるのも押さえておきましょう。
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
役員選任や役員変更、役員報酬の決定など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
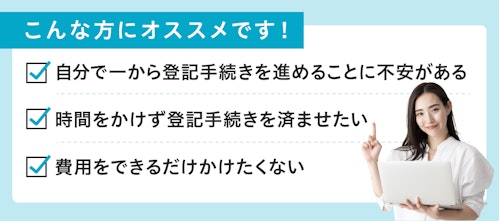
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\役員変更登記するなら/

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。