会社法は、その名の通り会社の規律について定める法律です。
株主総会や取締役会といった会社の意思決定を行う機関のルールについては、会社法に定めがありますが、具体的にどういったルールがあるのかについてご存じない方は多いのではないでしょうか。
また、例えば本店移転などの変更登記は、変更が生じた日(本店移転の場合は移転した日)から2週間以内に変更登記申請をしなければならないと、会社法により定められています。この期限を守らなかった場合、会社の代表者個人に100万円以下の過料が課せられる可能性がありますので注意が必要です。
本記事では経営者であれば押さえておきたい会社法のポイントについて解説します。なお、本記事内では特に断りが無い限り、最も一般的な株式会社を念頭においた解説をします。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
会社法の概要と制定の経緯
会社法の概要
会社法は、会社という形態(法人)をとる場合にその組織や運営方法について定める法律です。
もう少し簡単にいうと、会社の種類や、意思決定の権限や方法、経営者等の責任等といった点について定めている法律と言えます。
そのため、経営者としては会社法にどのようなルールが定められているのか、経営判断を行うにあたってどのような責任を誰に対して負っているのかという点を把握しておくという意味で会社法の理解が必要であるといえます。
会社法について詳しくはこちら
会社法制定の経緯
会社法は2006年に施行された比較的新しい法律です。それまでは、商法の中に会社に関する規定が定められているほか、有限会社法などで会社に関する定めがありましたが、会社に関する法制度の現代化や中小会社法制の見直しから、会社法が制定されるに至りました。
会社法が定める内容
会社法の定めるものの一例としては以下のようなものがあります。
定款
会社の基本的なルールであり、設立時に作成されるもので、目的や商号、本店所在地などを必ず記載しなければなりません。
また、各会社のそれぞれのルールを決めることができます。機関設計や役員任期、事業年度の他、株主総会の決議要件の軽減・加重や意思決定権限の委譲なども記載される場合がありますが、どの範囲まで定款で自由に定められるかが会社法に定められています。
株式
株式とは、株式会社の構成員である株主の地位・権利のことを指します。株式には剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利などが認められています。
また、株主総会の議決権や議案を提案する権利、各種書類の閲覧請求権や役員の責任追及などの経営に参加する権限も認められており、こういった、株式や株主について会社法に定められています。
意思決定機関
会社法では、会社の意思をどの機関がどのように決定するかという点も定められています。主に、株主総会、取締役会、取締役の過半数の決定、代表取締役の決定などで意思決定が行われます。
特に株主総会や取締役会の会議体では、開催する方法や決議要件、議事録の残し方など、多岐にわたり規定されています。
経営の場面で直面しやすい3つの場面と会社法
次に会社の経営にあたって直面しやすい場面と会社法のルールについて解説します。
株主総会や取締役会の開催
株主総会や取締役会は、必要がある場合に開催するものですが、事業年度の終了後一定期間には、必ず決算を承認する株主総会を開催する必要があります。いわゆる定時株主総会と言われるものです。定時株主総会では、前事業年度の事業報告や決算の承認などが行われます。また、決算承認後は、遅滞なく、決算公告をすることも義務付けられています。
さらに、取締役会を設置している会社の場合、代表取締役や業務執行取締役は、3か月に1回以上、自身の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。
役員の任期と改選手続き
役員にはそれぞれ任期が定められており、取締役は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査役は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされており、非公開会社の場合はそれぞれ10年まで伸長することが可能です。
中長期的な視点で経営方針を策定している会社などでは任期を10年としている会社も多いですが、任期が到来しているにもかかわらず、改選手続きを失念してしまうというケースも少なくありません。
また、12年以上必要な登記がなされていないと、事業を廃止している休眠会社としてみなし解散となってしまいます。
取締役の報酬決定と必要な手続き
取締役の報酬は株主総会で決定されることが一般的です。ここで決定するのはあくまでも取締役全体の報酬の総額を決定すれば足り、個別の具体的な金額については取締役会に委任することができます。
なお、役員報酬を損金として算入するためには、事業年度終了後の一定期間内に決定・変更する必要があるため、通常は定時株主総会で決議されます。
定時株主総会を準備する際に、議案に漏れが生じないように注意しましょう。
利益相反取引と必要な手続き
取締役が会社の事業と同じような事業を他社で取締役として行う場合や、会社と取引を行うようなケースでは、取締役がその地位を濫用して会社にとって不利となる行為をする可能性があります。
会社法ではこうした類型に該当する行為を利益相反取引として、事前に株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)で承認を得る必要があります。これらの義務違反の結果、会社に損害が生じた場合には任務懈怠責任が追及されることになります。
利益相反取引の取締役会議事録・株主総会議事録のテンプレートを無料でダウンロードできます
今すぐ使える利益相反取引承認の取締役会議事録・株主総会議事録のテンプレートを用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で議事録を作成したい方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
.png?w=1200&h=774)
※状況により内容を変更してご利用ください
利益相反取引承認の株主総会議事録のテンプレートはこちら
⇒株主総会議事録(利益相反取引議事録)
利益相反取引承認の取締役会議事録のテンプレートも以下にご用意しています。
⇒取締役会議事録(利益相反取引)
まとめ
会社法には本記事であげた他にも様々な定めがあり、こうしたルールを守らなかった場合にはその効力が否定されるなど様々な法的リスクが生まれます。会社法のルールを押え、適切な経営を行っていただく助けに本記事がなれば幸いです。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
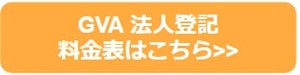
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
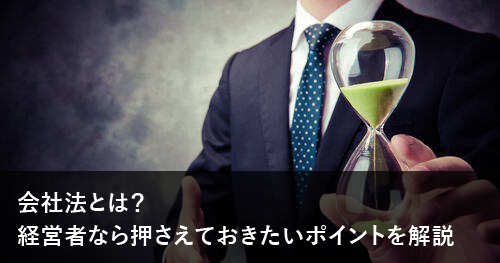
.png?w=1200&h=774)

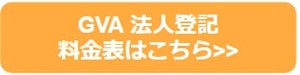
.jpg)



