多くの方が一度は耳にしたことがある「印鑑証明書」。何に使うもので、どうやって手に入れるのか疑問に感じている方も少なくありません。
印鑑証明書は市区町村に登録している実印(じついん)が本物であることを公的に証明する重要な書類です。個人の場合はマイホームの購入や車の売買、法人の場合は会社の設立や役員の変更など、人生の大きな節目やビジネスシーンで必要となる場面が多くあります。
この記事では印鑑証明書の基本的な概要から取得方法、必要なケースまでわかりやすく解説します。印鑑証明書に関する疑問が解消され、スムーズに手続きを進められるようになるのでぜひ最後までご覧ください。
印鑑証明書とは?有効期限や取得に必要な書類を解説
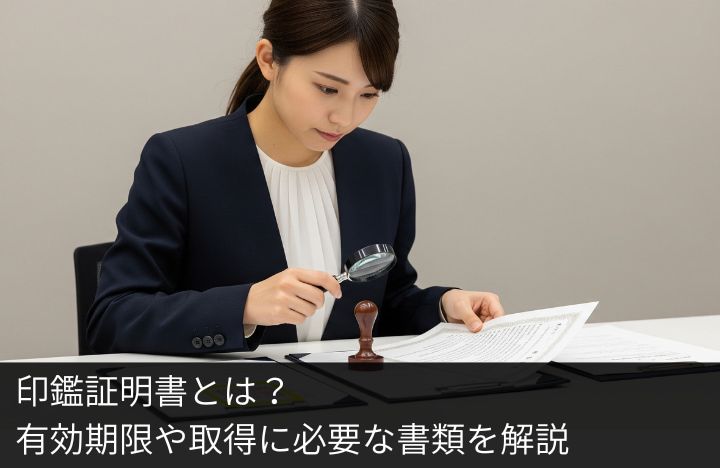
- 印鑑証明書とは実印を証明する公的書類
- 印鑑証明書が必要な理由
- 印鑑証明書と印鑑登録・登録証(カード)の違い
- 印鑑証明書の有効期限
- 印鑑証明書の4つの取得方法
- 市役所などの窓口で印鑑証明書を取得する方法
- コンビニでマイナンバーカードを使って取得する方法
- 代理人が印鑑証明書を取得する方法
- 法人が法務局で印鑑証明書を取得する方法
- 印鑑証明書の取得に必要な書類一覧
- 印鑑証明書が必要になる主なケース
- 不動産売買や住宅ローンの契約時
- 自動車の名義変更やローン契約時
- 法人設立・役員変更などの登記手続き
- その他:公正証書の作成や保証人になるときなど
- 法人の登記書類作成に不安がある方はGVA 法人登記がおすすめ
- 印鑑証明書は信頼性を担保する重要書類
- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- 【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
印鑑証明書とは実印を証明する公的書類
印鑑証明書は市区町村に登録された実印が、本物であることを公的に証明するための大切な書類です。印鑑証明書があることで重要な契約や手続きにおいて、契約者が本人であること、そして書面の意思に基づいていることが証明されます。
印鑑証明書が必要な理由
印鑑証明書が求められる主な理由は、契約や取引の安全性を確保し、詐欺やなりすましを防ぐためです。私たちが日常生活で使う認印やシヤチハタとは異なり、実印は法的な効力を持つ重要な印鑑です。
実印が本当に登録者本人のものであることを第三者が確認するために印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書を発行することで、不動産の売買や高額な金銭の貸し借り、会社の設立など重要な場面でのトラブルを未然に防げます。
印鑑証明書と印鑑登録・登録証(カード)の違い
印鑑証明書と関連して「印鑑登録」や「印鑑登録証(カード)」もよく耳にしますが、それぞれ異なるものです。
項目 | 説明 |
印鑑証明書 | 印鑑登録された実印が登録者本人のものであることを公的に証明する書類です。不動産売買や法人登記など、重要な契約や手続きにおいて、実印の正当性や本人の意思を確認するために使用されます。 |
印鑑登録 | 所有する印鑑を「実印」として公的に登録する手続きです。印鑑登録を市区町村役場で行うことで、その印鑑は法的な効力を持つ「実印」として認められるようになります。 |
印鑑登録証(カード) | 印鑑登録が完了した際に交付されるカードです。印鑑証明書を市区町村の窓口で取得する際に提示したり、マイナンバーカードがない方がコンビニ交付サービスを利用したりする際に必要となります。 |
印鑑登録の手続きを経て印鑑登録証(カード)が発行され、印鑑登録証を使って取得できるのが印鑑証明書です。
印鑑証明書の有効期限
印鑑証明書には原則として法律で定められた有効期限はありません。しかし、提出先によっては「発行から3ヶ月以内」「発行から6ヶ月以内」といったように、独自の有効期限を設定しているケースがほとんどです。
印鑑登録の情報(氏名、住所など)が変更される可能性があるため、常に最新の情報を反映した印鑑証明書を求めるためです。特に、不動産登記や商業登記、自動車の登録など重要な手続きで印鑑証明書を提出する際は、事前に提出先の窓口や担当者に有効期限を確認しましょう。もし有効期限を過ぎてしまった場合は、再度印鑑証明書を取得し直す必要があります。
印鑑証明書の4つの取得方法
印鑑証明書は個人の場合と法人の場合で取得方法が異なります。個人の場合は主に市区町村の窓口やコンビニエンスストアで印鑑証明書を取得します。法人の場合は管轄の法務局で印鑑証明書を取得するのが一般的です。それぞれの具体的な取得方法を解説します。
市役所などの窓口で印鑑証明書を取得する方法
最も一般的な印鑑証明書の取得方法が市区町村役場の窓口で申請する方法です。市役所などの窓口で印鑑証明書を取得する際は以下のものが必要になります。
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
- 手数料(1通200円〜300円程度)
【印鑑証明書を取得する流れ】
1. お住まいの市区町村役場の窓口(市民課、戸籍住民課など)に行きます。
2. 備え付けの「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項(住所、氏名、生年月日など)を記入しま
す。
3. 申請書と印鑑登録証(カード)、本人確認書類を窓口に提出します。
4. 手数料を支払い印鑑証明書を受け取ります。
多くの役所では平日の午前中から夕方まで窓口が開いています。自治体によっては、延長窓口や土日開庁を行っている場合もあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
コンビニでマイナンバーカードを使って取得する方法
マイナンバーカードと署名用電子証明書をお持ちであれば、コンビニエンスストアのマルチコピー機を利用して印鑑証明書を取得できます。市役所の窓口が閉まっている時間帯や、土日祝日でも取得できるため非常に便利です。
コンビニで印鑑証明書を取得する際はマイナンバーカードと、手数料(200~300円程度)が必要です。
【印鑑証明書を取得する流れ】
1. コンビニに設置されているマルチコピー機に向かいます。
2. マルチコピー機の画面で「行政サービス」または「証明書交付サービス」を選択します。
3. 「印鑑登録証明書」を選択し、マイナンバーカードを所定の場所にセットします。
4. 画面の指示に従って、マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書のパスワード(4桁の数字)
を入力します。
5. 必要な証明書の枚数などを選択し手数料を投入します。
6. 印鑑証明書が印刷されたら受け取ります。
コンビニ交付サービスを利用する際は、事前に市区町村役場で印鑑登録が完了し、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されていることが必須となります。また、コンビニでの印鑑証明書交付は24時間利用できるわけではなく、利用できる時間帯や曜日が限定されている場合があります(多くの場合は6:30〜23:00)。
本籍地と住民票の関係や住民基本台帳の登録状況によっては、交付対象外になる場合があるので、ご自身の状況に合わせて利用可能かどうかをご確認ください。
代理人が印鑑証明書を取得する方法
本人が忙しいなどの理由で、代理人に印鑑証明書の取得を依頼することも可能です。代理人が印鑑証明書を取得する際は以下のものが必要になります。
- 本人の印鑑登録証(カード)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(1通200円〜300円程度)
【印鑑証明書を取得する流れ】
1. 代理人が本人の印鑑登録証(カード)を持って、市区町村役場の窓口に行きます。
2. 備え付けの「印鑑登録証明書交付申請書」に本人の情報と代理人の情報を記入します。
3. 申請書と本人の印鑑登録証(カード)、代理人の本人確認書類を窓口に提出します。
4. 手数料を支払い印鑑証明書を受け取ります。
代理人が印鑑証明書を取得する際は、本人の印鑑登録証(カード)があれば、多くの自治体では原則として委任状は不要です。しかし、自治体によっては委任状の提出を求められたり、窓口で口頭による確認が行われたりするケースもあるので、事前に該当の市区町村に確認しておくと確実です。
コンビニ交付サービスは、マイナンバーカードの所有者である本人のみが利用可能です。そのため、代理人がコンビニで印鑑証明書の取得はできないので注意が必要です。
法人が法務局で印鑑証明書を取得する方法
会社などの法人で印鑑証明書が必要な場合は法務局で取得します。法人が法務局で印鑑証明書を取得する際に必要なものは以下の通りです。
- 印鑑カード
- 印鑑証明書交付申請書
- 手数料(1通450円)
- 窓口に行く人の身分証明書(代理人の場合も含む)
【印鑑証明書を取得する流れ】
1. 管轄の法務局に行きます。
2. 窓口で「印鑑証明書交付申請書」を入手し、必要事項(会社法人等番号、商号、本店所在地など)
を記入します。
3. 申請書に収入印紙(手数料分)を貼付します。
4. 印鑑カードとともに窓口に提出します。
5. 印鑑証明書を受け取ります。
法人の印鑑証明書は「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで請求し、郵送で受け取ることも可能です。登記・供託オンライン申請システムを利用するには、事前に利用者登録や電子証明書の取得が必要になりますが、法務局に直接出向く手間を省けるため、頻繁に取得する法人にとっては便利な方法です。
オンラインで申請し郵送で印鑑証明書を受け取る場合は、手数料が1通410円と窓口よりも安くなりますが、別途郵送料がかかります。急ぎの場合は窓口で印鑑証明書を取得する方が確実です。
印鑑証明書の取得に必要な書類一覧
印鑑証明書を取得する際の必要な書類は、取得方法や状況によって細かな違いがあります。以下の表で、取得方法ごとの必要なものと補足事項をまとめました。
取得方法 | 必要なもの | 補足説明 |
市役所などの窓口 | ・印鑑登録証(カード) ・本人確認書類(運転免許証、保険証など) | 本人が直接申請する必要あり |
コンビニ | ・マイナンバーカード ・利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字) | 対応自治体が限られる。発行可能時間が決まっていることが多い(概ね6:30〜23:00) |
代理人が窓口で取得 | ・印鑑登録証(カード) ・代理人の本人確認書類 ・委任状(必要な場合) | 自治体によって委任状の要・不要が異なるので事前確認が必要 |
法人の印鑑証明書を法務局で取得 | ・法人印鑑カード ・印鑑証明書交付申請書 | 窓口で即日発行可能。代表者個人の印鑑証明書ではなく、法人としての証明書 |
法人の印鑑証明書を郵送で取得 | ・交付請求書 ・収入印紙(手数料) ・返信用封筒(切手貼付) ・法人印鑑カードの写しなど | 管轄法務局によって異なるため、公式サイトで詳細確認を推奨 |
法人の印鑑証明書をオンラインで取得 | ・登記・供託オンライン申請システムのアカウント ・電子証明書(ICカード+カードリーダーなど) | 導入には事前準備が必要だが、非対面で発行可能 |
印鑑証明書の取得に必要な書類や手続きは、自治体や法務局によって一部異なる場合があります。事前に各公式サイトや窓口で確認することをおすすめします。
印鑑証明書が必要になる主なケース
印鑑証明書は印鑑が市区町村に正式に登録されたものであることを公的に証明する書類です。重要な取引や登記手続きにおいて、本人確認や意思確認の厳格性を高めるために印鑑証明書の提出が求められます。ここでは、印鑑証明書が必要となる主なケースを見ていきましょう。
不動産売買や住宅ローンの契約時
不動産の購入や売却、住宅ローンの契約時には多額のお金が動くため、契約の信頼性を担保することが極めて重要です。不動産取引をする際、契約者が間違いなく本人であることと、契約内容に同意していることを証明するために、実印の押印と合わせて印鑑証明書の提出が義務付けられています。
不動産取引の印鑑証明書はなりすましによる被害を防ぎ、取引の安全を確保するための重要な役割を果たします。
自動車の名義変更やローン契約時
自動車の購入や売却に伴う名義変更、オートローンを組む際にも印鑑証明書が必要です。特に、所有者の変更を伴う手続きや高額なローンの契約では、不動産取引と同様に本人の意思確認と契約の確実性が求められるため、印鑑証明書の提出が必須となります。
法人設立・役員変更などの登記手続き
会社を設立する際や役員の変更、増資といった重要な登記手続きを行う場合、法務局への申請に印鑑証明書が添付書類として必要になります。法人の代表者や役員が確かにその人物であること、その決定が正当な手続きを経て行われたことを証明するためです。
個人の実印だけでなく、法人の代表者印(会社実印)についても印鑑証明書が求められます。
その他:公正証書の作成や保証人になるときなど
上記以外にも印鑑証明書が必要となるケースは多岐にわたります。
・公正証書の作成時
遺言書の作成や金銭消費貸借契約など、法的効力の強い書類を公証役場で作成する際に必要です。
・保証人になるとき
他人の債務の保証人となる場合、その責任の重さから本人の意思確認を厳格に行うため、印鑑証明
書の提出が求められることがほとんどです。
・遺産分割協議を行う際
遺産分割協議書に署名捺印した者が本人であることを証明するために必要となります。
印鑑証明書が必要な場面は「本人の重要な意思表示を公的に証明する必要がある時」と考えると分かりやすいです。手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類を確認し、準備しておくことが大切です。
法人の登記書類作成に不安がある方はGVA 法人登記がおすすめ
法人の登記手続きは専門的な知識が必要で、書類作成には手間がかかるものです。特に、役員変更や本店移転など頻繁に行わない手続きの場合、何から手をつければよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな方には「GVA 法人登記」がおすすめです。GVA 法人登記はオンラインで簡単に法人の登記書類が作成できるサービスです。
- 登記に関する専門知識がない、または自信がない
- 司法書士に依頼する費用を抑えたい
- 忙しくて登記手続きに時間をかけたくない
- 書類作成のミスを避け、正確に手続きを完了させたい
上記のような悩みや願望がある方はGVA 法人登記の利用がぴったりです。GVA 法人登記を利用すれば複雑な法人の登記手続きも、画面の指示に従って必要情報を入力するだけで簡単に進められます。専門的な知識はないけれど、自分で手続きを進めたいと考えている方にとって、非常に心強いサービスなのでぜひご利用ください。
GVA 法人登記の詳細はこちら
https://corporate.ai-con.lawyer/
印鑑証明書は信頼性を担保する重要書類
印鑑証明書は市区町村に登録された、実印の正当性を公的に証明する非常に重要な書類です。個人の重要な取引や法人の登記手続きにおいて、その信頼性を担保する役割を担っています。印鑑証明書は主に以下の方法で取得できます。
- 市区町村の窓口で取得
- コンビニでマイナンバーカードを使って取得
- 代理人が申請して取得
- 法務局で法人の印鑑証明書を取得
印鑑証明書が必要な場面は、「本人の重要な意思表示を公的に証明する必要がある時」であり、不動産売買、自動車の名義変更、法人登記、公正証書の作成、保証人となる場合などが挙げられます。
法人の登記書類作成に不安がある場合はGVA 法人登記のようなオンラインサービスを活用すると、専門知識がなくても簡単に書類を作成でき、費用や時間の節約にもつながります。手続きをスムーズに進めるためにも、ご自身の状況に合った取得方法と必要な書類を事前に確認し、準備しておくことが大切です。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】GVA 法人登記なら法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力
\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。


