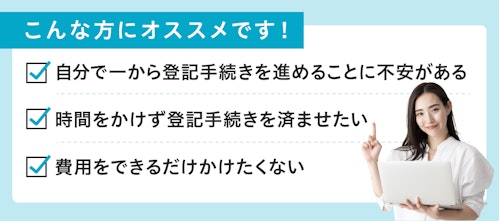初めて会社を設立する方にとって、「株式会社と合同会社のどちらを選ぶべきか」「手続きは自分ですべきか、専門家に依頼すべきか」といった疑問は尽きないでしょう。
本記事では、会社設立を検討されている方向けに、以下のポイントについて理解できるよう解説します。本記事を読めば、会社設立に関するこれらの疑問を解消し、スムーズなスタートを切るための道筋が見えてくるでしょう。
- 会社形態(株式会社・合同会社)の選択肢と比較
- 会社設立の手続きの流れ
- 設立方法(自力・専門家・クラウド)の比較
- 司法書士に依頼するメリット・デメリットと費用相場
費用を抑えて自分での法人変更登記必要書類を作成するなら「GVA 法人登記」が便利です
法人変更登記の必要書類は、株主総会議事録、株主リスト、登記申請書など必要となる書類が多く、登記申請の経験がない方にとっては少々ハードルが高いかもしれません。
自分で書類を作成して申請することも可能ですが、不備があると受理されず、作り直している間に期限の2週間が増えてしまうこともありますので注意が必要です。そんな方におススメなのが、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」です。
GVA 法人登記は、案内に従い必要情報をフォームに入力するだけで、登記申請に必要な書類がすべて自動作成できるオンラインサービスです。
【GVA 法人登記の特徴】
- 法人変更登記に必要な書類が24時間いつでも作成できます。
- 固定費・月額費なし、スポットで購入できるので、無料登録しておけばいつでもご利用可能です。
- 登記知識のない方でも、簡単にご利用できる仕様になっています。
- 法務局に行かずに申請できる郵送申請もサポート。ポストに投函するだけで申請が完了します。
GVA 法人登記はこちら
【GVA 法人登記で代表取締役の住所変更登記の変更登記書類を自分で作成された事例】
実際にGVA 法人登記で役員変更登記の書類を作成された、H&innovation株式会社様の事例です。専門家に依頼した場合の提示額に比べ安価だったとのことから「GVA 法人登記」をご利用いただきました。
詳しい内容は、こちらをご確認ください
UIがわかりやすく使いやすかったので2回目の利用も即決でした
.png?w=200&h=113)
会社形態の基本:株式会社と合同会社
現在、新たに会社を設立する場合、そのほとんどが「株式会社」または「合同会社」のいずれかを選択することになります。かつては有限会社という形態もありましたが、2006年の会社法施行により新たに設立することはできなくなりました。株式会社と合同会社にはそれぞれ特徴があり、事業の規模や将来の想定によってどちらが適しているかが異なります。
株式会社と合同会社の比較
項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|
社会的信用度 | 高い | 株式会社に比べると低い傾向 |
|---|
設立費用(実費) | 約20.2万円~24万円程度 | 約6万円~10万円程度 |
|---|
意思決定機関 | 株主総会、取締役会 | 社員の同意(原則として総社員の同意) |
|---|
役員の任期 | 原則2年(非公開会社は最長10年まで伸長可) | なし(定款で定めることは可能) |
|---|
利益の配分 | 原則として出資比率(持株比率)に応じて配当 | 定款で自由に定めることが可能 |
|---|
資金調達方法 | 金融機関からの融資はもちろん、株式の発行による増資など多様 | 社員からの追加出資や金融機関からの借入が主 |
|---|
定款認証 | 必要(公証役場で行う) | 不要 |
|---|
株式会社と合同会社の設立費用の比較
以下は、司法書士報酬などを除いた、会社設立において必ずかかる費用の比較です。
費用項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|
定款用収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | ※電子定款の場合は不要 |
|---|
定款認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 不要 | 資本金の額によって変動 |
|---|
定款謄本手数料 | 約2,000円 | 不要 | |
|---|
登録免許税 | 150,000円(または資本金額×0.7%の高い方) | 60,000円(または資本金額×0.7%の高い方) | 国に納める税金 |
|---|
両法人とも電子定款を利用することで収入印紙代の4万円が不要になります。また、合同会社は定款認証が不要なためその分の費用がかからないのと、設立登記の登録免許税が低額になります。これらの費用差が、「合同会社が安く設立できる」と言われる大きな理由です。
会社設立に必要な手続き
次に、会社設立の具体的な手続きの流れを見ていきましょう。株式会社と合同会社では、手続きに若干の違いがあります。
株式会社の設立手続きの流れ
- 基本事項の決定 商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額、発起人(出資者)、役員構成などを決定します。特に事業目的は、将来行う可能性のある事業も視野に入れて検討する必要があります。
- 定款の作成 会社の基本的なルールを定めた「定款」を作成します。
- 定款の認証 作成した定款が法的に有効であることを証明してもらうため、公証役場で認証を受けます。これは株式会社のみ必要になります。
- 資本金の払込み 発起人個人の銀行口座に、定められた資本金を振り込みます。この時点ではまだ会社名義の口座は作れないため、発起人代表の口座を使用します。
- 設立登記申請書類の作成 法務局に提出するための登記申請書や、就任承諾書、払込証明書などの添付書類一式を作成します。
- 法務局へ設立登記申請 本店所在地を管轄する法務局に、作成した書類一式を提出します。この申請日が、会社の設立日(創立記念日)となります。
合同会社の設立手続きの流れ
- 基本事項の決定 株式会社と同様に、商号、本店所在地、事業目的、資本金、社員構成などを決定します。
- 定款の作成 株式会社と同様に定款を作成します。
- 資本金の払込み 出資者(社員)が、定められた資本金を払い込みます。
- 設立登記申請書類の作成 登記申請書、添付書類を作成します。
- 法務局へ設立登記申請 本店所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。
合同会社の手続きは、株式会社のステップから「3. 定款の認証」が省略されています。また、定款の内容や資本金の払込方法など若干異なります。
会社設立を行う3つの方法
会社設立の手続きは、大きく分けて以下の3つの方法で行うことができます。それぞれのメリット・デメリット、そして費用感を比較してみましょう。
- 自分で書類を作成して設立登記する
- 司法書士などの専門家に依頼する
- クラウドの会社設立サービス(freee 会社設立など)を利用して設立登記する
3つの設立方法の比較
株式会社の設立を例に3つの方法を比較してみましょう。
項目 | ①自分で設立 | ②司法書士に依頼 | ③クラウドサービス |
|---|
総費用 | 約24.2万円~(紙定款の場合) | 約20.2万円~(司法書士報酬は除く) | 約20.2万円~(電子定款を利用) |
|---|
手間・時間 | 非常にかかる(調査、書類作成、法務局等への訪問) | ほぼ発生しない(専門家との打合せのみ) | 比較的かからない(フォーム入力中心) |
|---|
専門性・正確性 | 低い(全て自己責任) | 非常に高い(専門家による法的チェック) | 中程度(定型的な内容に限られる) |
|---|
サポート | なし | 手厚い専門的アドバイス、設立後のフォロー | 限定的(システムの操作方法など) |
|---|
会社設立を司法書士に依頼するメリット・デメリット
設立方法の選択肢の中でも、特に専門家である司法書士への依頼について、そのメリットとデメリットを解説します。
司法書士に依頼するメリット
- 本業の準備に専念できる(時間的なメリット): 起業前は、事業計画の策定、資金調達、オフィスや店舗の準備、Webサイトの構築など、やるべきことがたくさんあります。司法書士に任せることで、最も重要な「事業の準備」に集中できます。
- 電子定款の利用で印紙代4万円が不要に 司法書士は電子定款作成の設備を用意していることが多いため、ご自身で紙の定款を作成する場合にかかる印紙代4万円を節約できます。
- 将来を見据えた最適な定款を作成できる:定款は一度作ると、変更するには株主総会の決議と登記申請が必要になり、費用と手間がかかります。司法書士は、単に会社を設立するだけでなく、機関設計や資本政策、許認可を想定した事業目的など、将来の事業展開を見据えたアドバイスを提供できます。
- 手続きの確実性とスピード:登記の専門家である司法書士が手続きを行うため、書類の不備で法務局から補正(修正)を求められるリスクを低くできます。設立までのスケジュールに合わせてスムーズで確実に会社を設立できます。
司法書士に依頼するデメリット
- 専門家報酬(コスト)が発生する 当然ながら、専門家への依頼には報酬が発生します。とにかく1円でも安く設立したいという方にとっては、この費用が最大のデメリットとなります。
- 司法書士とのコミュニケーションの手間 依頼する以上、司法書士と打ち合わせを行う時間、依頼先を比較検討する時間が必要になります。
会社設立を司法書士に依頼する場合の費用相場
では、実際に司法書士に会社設立を依頼した場合、どのくらいの報酬がかかるのでしょうか。これは事務所の方針やサービス内容によって異なりますが、多くの場合、以下の価格に収まっているようです。
- 株式会社設立の司法書士報酬: 5万円 ~ 15万円 程度
- 合同会社設立の司法書士報酬: 4万円 ~ 10万円 程度
※なお、司法書士会のアンケートによると、発起人2名、資本金の額500万円の株式会社の発起設立による設立登記の平均報酬額として107,887円と紹介されています。
この報酬には、通常、以下の業務が含まれています。
- 設立に関する相談
- 定款の作成・認証手続きのサポート
- 設立登記申請書の作成
- 法務局への登記申請代理
総費用のシミュレーション(株式会社の場合)
- 法定実費(電子定款利用):約20.2万円
- 司法書士報酬:10.7万円(上記の司法書士会アンケートから抜粋)
- 合計:約30.9万円
メリット・デメリットを見極めて会社設立方法を選択しましょう
会社設立の選択肢と、司法書士に依頼するメリット・デメリットを解説しました。どの方法が一番良い、という絶対的な正解はなく、ご自身の状況や価値観に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。以下が依頼方法を決めるポイントになりますので、十分な比較検討をおすすめします。
- 費用を最優先し、時間と手間をかけられる場合 「自分で設立」または「クラウドサービス」が選択肢になります。特にクラウドサービスは、電子定款のメリットを享受できるため、有力な候補となります。
- 本業に集中し、確実かつスムーズに会社を立ち上げたい場合 「司法書士への依頼」が最適です。初期投資はかかりますが、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、将来の事業展開まで見据えた検討ができます。
GVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
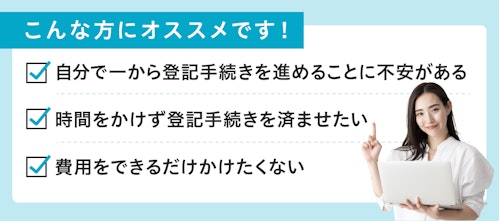
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\役員変更登記するなら/


.png?w=200&h=113)