雇い入れを行った場合には、労働者の管理のために、氏名住所や労働時間、出勤欠勤などを記録する必要があります。
雇い入れや賃金支払いをはじめとした労働関係に関する重要な書類は、労使間のトラブルを未然に防ぐためにもしっかりと作成し、適切に保管することが重要です。
本記事では、労働者の雇い入れを行った場合に、作成が義務付けられている法定三帳簿の種類と内容、保存期間などについて解説しています。労働者の雇い入れを行おうと考えている方は、ぜひご参考ください。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
役員変更や本堤店などの会社の変更登記は自分で申請できます
この記事をお読みの方の中には、会社の変更登記を控えている方もいらっしゃるかもしれません。会社の登記簿謄本に記載される事項の変更手続きには本店移転や役員変更など様々な種類がありますが、社内での決議に加えて、登記申請の手続きが必要という特徴があります。GVA 法人登記などのサービスを利用すれば、Webサイトから必要な情報を入力することで変更登記の申請に必要な書類を自動作成し、自分で申請できます。
法定三帳簿とは
労働基準法では、労働者の雇い入れを行った場合に、後述の事項を記載した書類を作成し、定められた期間保存することが義務付けられています。
労働基準法で作成が義務付けられている「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を併せて、法定三帳簿と呼び、記載すべき事項や保存期間がそれぞれ法令で定められています。
法定三帳簿は、労働保険や社会保険の手続きを行う際に添付を求められることがあるだけでなく、労働基準監督署の調査で提出を求められることもあるため、しっかりと不備がないように作成しなければなりません。
労働者名簿
労働者名簿は、労働基準法107条により、作成が義務付けられている書類です。労働者ごとに店舗や営業所、工場などの事業場単位で作成し、記入すべき事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければなりません。
労働者名簿の記載事項は次のとおりです。
- 氏名
- 生年月日
- 履歴
- 性別
- 住所
- 従事する業務の種類
- 雇い入れの年月日
- 退職の年月日及びその事由(解雇の場合にあってはその理由含む)
- 死亡の年月日及びその原因
上記の法で定められた記載事項の他に、会社が労働者を管理する上で必要となる事項を任意で設けることも可能です。任意記載事項には、電話番号などの連絡先や社会保険に関する事項を設けることが多くなっています。
また常時30人未満の労働者を雇用する会社であれば、労働者名簿に従事する業務の種類を記載する必要はありません。
賃金台帳
賃金台帳は、労働基準法108条により、作成が義務付けられている書類です。
労働者名簿と同様に事業場単位で作成し、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額、その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払いの都度記入する必要があります。
賃金台帳の記載事項は、次のとおりです。
- 氏名
- 性別
- 賃金計算期間
- 労働日数
- 労働時間数
- 時間外労働時間数
- 休日労働時間数
- 深夜労働時間数
- 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
- 賃金控除した場合にはその項目と控除額
労働時間数や時間外、休日、深夜労働時間数の記載が求められますが、始終業の時刻や休憩時間数まで記載する必要はありません。
賃金台帳の作成対象は、正社員やアルバイト、パートなど雇用形態を問わず、雇用している労働者全員ですが、日雇い労働者に関しては、賃金計算期間を記載することは不要となっています。
また一般的な給与明細では、法で定められた記載事項を網羅していないことが多く、賃金台帳に代えることは、原則としてできません。
出勤簿
出勤簿は、労働者名簿や賃金台帳と異なり、労働基準法上明文の規定はありません。しかし適切な労務管理を行うために必要な労働関係に関する重要な書類として、作成が義務付けられています。
労働者名簿や賃金台帳と同様に事業場単位で作成する必要があり、記載事項は次のとおりです。
- 出勤日及び労働日数
- 始終業の時刻及び休憩時間
- 日別の労働時間数
- 時間外労働を行った日付、時刻、時間数
- 休日労働を行った日付、時刻、時間数
- 深夜労働を行った日付、時刻、時間数
単純に出勤日や労働時間数を記載するだけでは、通常の労働時間か時間外、休日、深夜労働時間のいずれに該当するのか判断できないため、上記のように記載し、正確に労働時間を把握します。
また出勤簿の様式に定めはないため、ExcelやWordでの作成はもちろんこと、労働者の自己申告による手書きでの作成も可能です。
ただし、自己申告による労働時間の把握は、タイムカードやパソコンの使用時間など客観的な方法によることが困難な場合に限られます。
また自己申告による労働時間と客観的な方法により、把握した在社時間に著しい乖離がないか調査することや、自己申告制度について十分な説明を行うことなどが必要となります。
自己申告による労働時間の把握は、あくまでも客観的な方法による労働時間の把握が困難な場合の例外的な方法であり、労働時間の改ざんなどを防ぎ、正確な労働時間を把握するためにも、客観的な方法による労働時間の把握に努めることが必要です。
法定三帳簿の保存期間
法定三帳簿の保存期間は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のいずれも5年間(当分の間は3年間)とされていますが、保存期間の起算日はそれぞれ異なっており、次のとおりとなります。
労働者の死亡、退職又は解雇の日
最後の記入をした日(労働者の最後の賃金について記入した日)
その処理が完結した日(労働者が最後に出勤をした日)
法定三帳簿それぞれで保存期間の起算日が異なっているため、管理する上で各々の起算日をしっかりと把握し、誤って廃棄することがないようにしなければなりません。
また保存する形式に定めはないため、電子データでの保存も可能ですが、労働基準監督署の調査などに対して、直ちに必要事項を明らかにして、提出できるシステムであることなどが必要です。
源泉徴収簿は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。そのため、賃金台帳と源泉徴収簿を兼ねている場合には、保存期間が7年間となることに注意してください。
義務違反に対する罰則
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のいずれも、義務違反に対する罰則が設けられており、違反した場合には、労働基準法120条により30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
そのため帳簿に記載すべき事項をしっかりと守り、適切な管理を行って、定められた期間保存することが必要です。
まとめ
雇い入れた労働者を適切に管理するためには、しっかりと労働時間や賃金支払いに関する記録を付けることが必要です。
法定三帳簿は、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿のいずれも労働者の管理を行う上で必要となる重要な事項を記載する書類であるため、作成に当たって間違いがあってはなりません。
本記事では、法定三帳簿それぞれについて、必要となる記載事項や注意すべき点、保存期間などについて解説をしてきました。
法定三帳簿に関しては、義務違反の罰則も予定されているため、本記事で解説した知識を参考にしっかりと作成し、管理保存を行いましょう。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
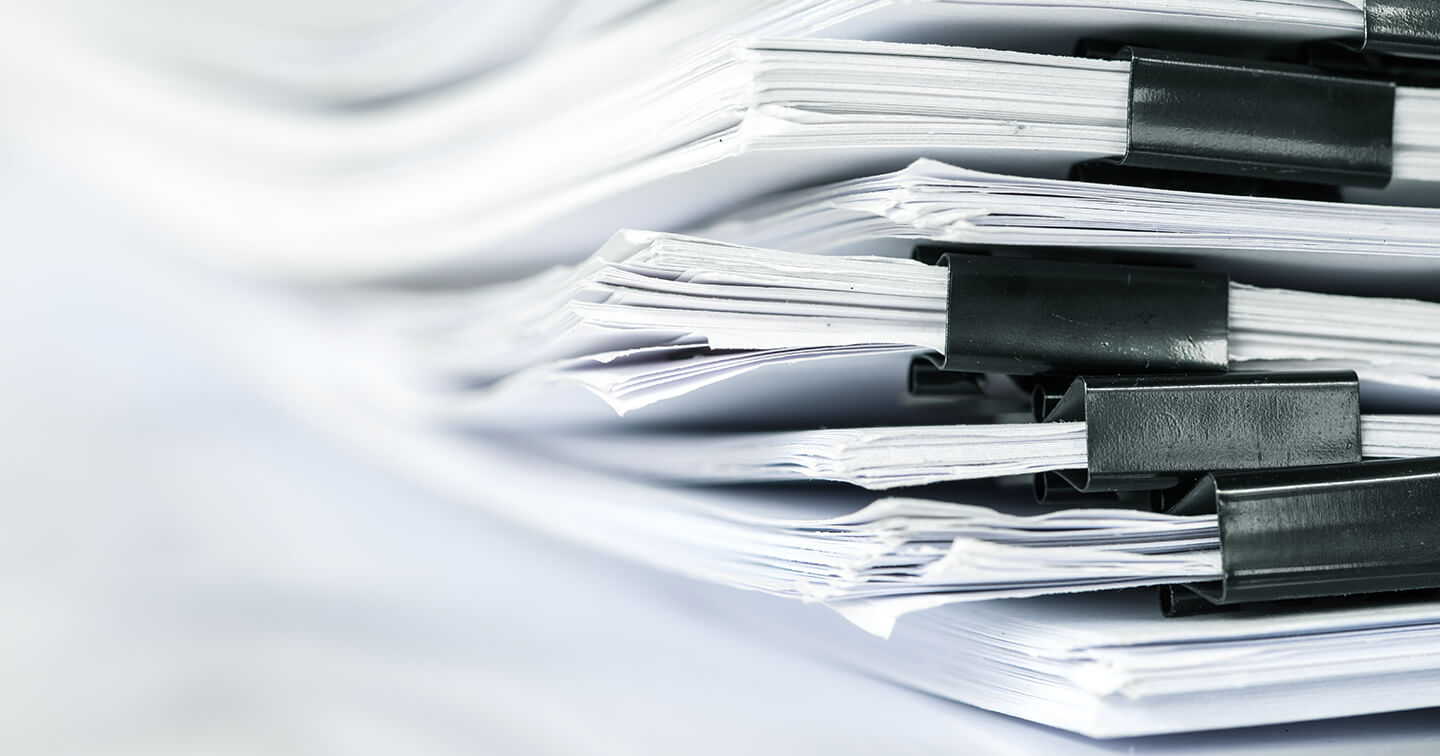


.jpg)



