会社には代表取締役や取締役をはじめとして様々な役職の人が存在します。その中でも相談役や顧問という役職を耳にされたことのある方は多いと思いますが、他方でこうした相談役や顧問ではどういった役割を果たしているのかといった点や、取締役などの役員とどのように違うのかといった点が分らない方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では相談役について顧問や取締役とどのように違うのかといった点などについて解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
相談役とは
相談役とは、一般的には取締役や代表取締役を兼任してはいないものの、取締役が行う会社の経営判断についてアドバイスや助言を行うために置かれる役割となっています。しかし、相談役について特に一義的な定めは無く、それぞれの会社において様々な役割を果たしています。
会社法における相談役
会社法では相談役について特段の定めはありません。そのため、会社法上定められた権限は相談役には特になく、設置も義務ではありません。
したがって、相談役を設置するか、そのような権限を持たせるかという点については会社の判断に委ねられることになります。
相談役の役割
前述の通り相談役の役割は会社法などで一義的に定められているものではありません。そのため、決まった相談役の役割はありません。一般的に相談役は取締役や代表取締役を退任した後になるケースが多いため、こうした経営者としての経験やコネクションを活かして、現在の代表取締役をはじめとした経営者へのアドバイスや相談に乗る役割を果たしているケースが多く見られます。
また、代表取締役が交代し、引き継ぎを行っている場合に引き継ぎが完了するまでの間相談役として会社に在任するというケースも少なくありません。
このように相談役が果たす役割はその会社が置かれた状況毎に異なるため、それぞれの会社の実態や経営体制などに応じて様々な役割を果たしています。
相談役は会社の組織図でどこになる?
結論、組織図の位置は企業の規模や構造によって異なりますので、これといった明確な答えはまちまちとなります。
一般的に大木のは以下です。
取締役の下
相談役は、取締役会や経営陣から直接アドバイスを受ける立場にありますが、実際は業務執行には関与しないため、取締役の下に配置されることが多いです。
顧問として配置
組織図として、「顧問」や「アドバイザー」のような立ち位置で表示されることもあります。
社外の立場として表記
相談役が外部から招聘されるとき、組織図には表示されないこともあります。
相談役と各役職の違いはどこにある?
代表取締役、監査役、取締役など様々な会社の役職を耳にしますが、相談役という役職と何が違うか答えられますか?
以下に疑問に感じやすい役職との違いを解説します。
顧問と相談役の違い
相談役と似た役職として顧問があります。顧問も相談役と同様に会社法に定めはありません。そのため、顧問にどういった権限や役割を持たせるのかは会社によって異なります。一般的には顧問も相談役と同様に会社の経営事項についてアドバイスを行う役割を果たすケースが多く見られますが、顧問の場合には相談役よりもより専門的な立場からアドバイスを行う役割を果たすのが一般的です。
そのため、相談役は主に社長などの代表取締役であった人がなるケースが多いのに対し、顧問には弁護士や税理士などの専門家がなることが多いようです。また、技術部門や開発部門などの専門的な知見を有している社内の人間が顧問として就任するケースも少なくありません。
このように顧問と相談役の違いは主にどういった人間が就任するかという点が異なるといえるでしょう。
取締役と相談役の違い
取締役は会社法上会社の業務執行機関として経営に関する事項の決定権限や執行権限を有しています(法第348条第1項)。
これに対して相談役は、取締役ではないため会社の経営事項について決定権限を有していません。
そのため、会社の経営事項についての決定権限の有無について大きな違いがあります。
相談役が設置されるケースや背景
相談役が実務上置かれるケースとしては、以下の様なケースが多く見られます。
- 会社の代表取締役に引き継ぎなどを行うために社内にとどまってもらうために設置されるケース
- 代表取締役の経営判断などについて相談やアドバイスを行うために設置するケース
- 経済界などと強力なコネクションを有する人間と会社の顔つなぎをしてもらうために設置するケース
- 突発的に生じた経営上の問題について助言をしてもらうために設置されるケース
主に以上のようなケースで相談役が設置されるケースが多いようです。特に3つめのケースは、大企業において複数の相談役を置いているケースでよく見られる相談役の活用方法です。
しかし、昨今では後述するように相談役というあいまいな役職を設けることについて投資家から批判を受けるケースも増えてきており、設置する企業は減少傾向にあります。
相談役を設置するのに必要な手続き
相談役は会社法上の役員では無いため、株主総会決議による選任は不要です。しかし、上場企業の場合には、東証が上場企業に対して要求するコーポレート・ガバナンスコードへの対応として、外部へ開示を行うコーポレート・ガバナンスに関する報告書(通称、CG報告書)にて退任した社長・CEOが就任する相談役、顧問等について、氏名、役職・地位、業務内容等について開示することが求められています。
コーポレート・ガバナンスコードとは、上場企業が行うべき企業統治についてガイドラインとして参照すべき原則や指針を示したものです。上場企業はこれら全てに従う必要はありませんが、同原則に従わない又は実施しない場合には、なぜ実施しないのかという点について説明(エクスプレインと呼ばれています。)する事が求められます。
CG報告書は、こうしたコーポレート・ガバナンスコードの実施状況について各会社から報告を求める文書です。
したがって、相談役を置いた場合には、上場会社ではCG報告書にて相談役の氏名や役職等について開示する必要がある点に注意が必要です。
相談役を設置する場合の実務上の留意点
相談役を設置する際に留意しておきたいのが、議決権行使助言機関の存在です。議決権行使助言機関とは、ISSやグラスルイスなど機関投資家に向けて議決権の賛否について助言・提言を行う機関で、海外の投資家に強い影響力を有しています。
これらの機関はいずれも相談役を新たに設置する議案を株主総会に諮る場合には原則として反対推奨を行う旨を明らかにしています。
前述の通り相談役の設置には株主総会決議は不要ですが、もし株主の理解を得て設置したいという思いから、株主総会決議を経て行おうとした場合には、相応に賛成率が低くなる可能性がある点には十分注意が必要です。
まとめ
実務上は経営者へのアドバイスや経済界との顔つなぎなど重要な役割を果たすこともある相談役ですが、様々な批判から昨今では設置する企業が減少傾向にあります。設置する際には、外部に向けてなぜ相談役が必要なのか、説明が可能な状態にしておくことが重要といえるでしょう。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /
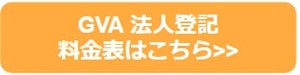
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
.jpg)

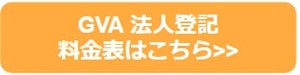
.jpg)



