当記事では、会社内部から社員が役員に昇進した場合の「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」などの社会保険手続きや兼務役員、役員と執行役員の違い等について解説してます。役員が失業保険のを受けれるのかなども解説します。
役員(取締役)就任による雇用保険の喪失などの手続き
.jpg)
- 必要書類が多い役員就任の登記はGVA 法人登記が早くて便利です
- 社会保険とは
- 新たな役員が就任したら、役員変更登記が必要です
- 社員と役員の社会保険・雇用保険適用における違い
- 社員からの役員就任に伴う社会保険手続き
- 役員就任による雇用保険の資格喪失手続き
- 雇用保険被保険者資格喪失届を提出
- 標準報酬月額の随時改定
- 兼務役員における雇用保険の例外
- 業務執行権や代表権を持たない役員であること
- 役員報酬より労働者としての給与の方が高いこと
- 業務遂行の拘束性が認められること
- 他の労働者と同様に就業規則の適用を受けること
- 役員と執行役員の社会保険適用における違い
- 執行役員就任に伴う社会保険手続き
- 会社が倒産したら失業保険はもらえる?
- まとめ
- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
- GVA 法人登記が対応している登記種類
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)
- GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
必要書類が多い役員就任の登記はGVA 法人登記が早くて便利です
役員就任時にはさまざま手続きが発生しますが、役員変更登記も忘れずに申請する必要があります。
GVA 法人登記なら、必要書類を把握していなくても書類の作成ができますのでぜひご利用ください。
役員変更登記に必要な書類の作成方法を見に行く
社会保険とは
社会保険とは、疾病や負傷、老齢、障害、死亡、失業等に対して、必要な保険給付を行う公的な保険制度です。社会保険には、広義と狭義の社会保険があり、狭義の社会保険は健康保険と厚生年金保険、介護保険の3つを指します。
一方で、広義の社会保険は、狭義の社会保険に加えて、労働保険である労災保険と雇用保険を含むことになります。以下、当記事では、社会保険を広義の社会保険の意味で使用します
新たな役員が就任したら、役員変更登記が必要です
社員・従業員から役員になるケースでは、雇用や保険関連など意外に手続きが多いものですが、役員変更の登記も忘れずに申請しましょう。
GVA 法人登記などのサービスを使えば、必要情報をフォームに入力するだけで簡単に書類が作成できます。
社員と役員の社会保険・雇用保険適用における違い
原則として、社員も役員も健康保険と厚生年金保険の適用を受けることに違いはありません。しかし労働者を対象としている労災保険と雇用保険では、取扱いが異なっています。
会社と委任の関係に立つ取締役等の役員は、雇用契約を締結した労働者ではないため、後に解説する兼務役員である場合を除いて、雇用保険の適用を受けません。また労災保険についても特別加入をするのでなければ、適用を受けることはありません。
社員からの役員就任に伴う社会保険手続き
既に解説したとおり、社員も役員も健康保険と厚生年金保険の適用を受けるため、昇進して役員に就任した場合であっても、後述する随時改定に該当するのでなければ、健康保険と厚生年金保険における手続きは不要です。
役員就任による雇用保険の資格喪失手続き
昇進などにより社員から役員に就任すると、労働者でなくなるため、雇用保険における資格喪失手続きが必要となります。
また社会保険に加入すべき役員が、新たに外部から就任した場合には、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等を管轄年金事務所に提出することが必要になります。
雇用保険被保険者資格喪失届を提出
昇進して役員に就任した場合には、原則として雇用保険の被保険者でなくなるため、雇用保険被保険者資格喪失届を管轄のハローワークに提出する必要があります。
この場合に資格喪失日として記載するのは、役員就任日や翌日ではなく、役員就任の前日であることに注意が必要です。
また雇用保険の資格喪失手続きを行うことで、労災保険も同時に手続きが行われるため、労災保険については、特別の手続きは不要です。
標準報酬月額の随時改定
継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、2等級以上の差を生じた場合には、標準報酬月額の随時改定手続きの対象となります。
役員就任に伴い報酬の額が大きく上がり、2等級以上の差が生じた場合には、随時改定の対象となるため、管轄年金事務所に月額変更届を提出することが必要です。
兼務役員における雇用保険の例外
原則として役員は、雇用保険の適用を受けず、被保険者とはなりません。
しかし取締役工場長や取締役総務部長等の労働者としての身分を併せ持つ役員の場合には、役員と労働者を兼ねる兼務役員として、雇用保険の被保険者となり、兼務役員雇用実態証明書を管轄のハローワークに提出する必要があります。
兼務役員となるか否かは、工場長や部長等の肩書ではなく、労働者性を持った実態があるかどうかで判断されます。労働者性があると判断され、兼務役員となるには、次の条件を満たす必要があります。
業務執行権や代表権を持たない役員であること
業務執行権や代表権を持った役員は、会社と指揮命令の関係に立たないことから、肩書がどのようなものであれ、労働者としては扱われません。また業務執行権や代表権は、肩書ではなく、実態で判断されることに注意してください。
役員報酬より労働者としての給与の方が高いこと
収入の主たる部分が役員報酬によるもので、労働者としての給与より高い場合には、労働者性が弱いと判断されます。一方で労働時間に応じて、給与が支払われている場合や、欠勤控除の対象となっているのであれば、労働者性が高いと判断を受けます。
業務遂行の拘束性が認められること
会社と委任の関係に立ち、自由な裁量権を持っている役員に対して、労働者は会社からの指揮命令を受けて労働を提供します。そのため、労働者性が認められるためには、仕事の進め方や出退勤の時間等を会社に管理され、労働者として拘束されていることが必要となります。
他の労働者と同様に就業規則の適用を受けること
役員は労働者と異なり、就業規則の適用がありません。そのため、他の労働者と同様に就業規則の適用を受け、労務を提供しているのであれば、労働者性が高いと判断されます。
役員と執行役員の社会保険適用における違い
会社における役員に類似した役職として、執行役員があります。
役員が会社法で、取締役、会計参与、監査役と定められているのに対して、執行役員は会社法上の定義が存在せず、設置も義務付けられてはいないため、会社は自由に執行役員を設置できます。
そのため、執行役員の地位や職責、待遇等は会社によってさまざまであり、委任契約であるか、雇用契約であるかによって社会保険の取り扱いが異なっています。
執行役員就任に伴う社会保険手続き
既に解説した通り、執行役員に関する会社法上の定めはなく、会社が取り扱いを自由に決定することが可能で、契約形態も自由です。一般的には雇用形態は正社員のまま役職して「執行役員」を名乗るケースが多いですが、なかには「取締役執行役員」というような場合もあります。
そのため、社員が昇進して、執行役員に就任した場合に必要となる社会保険の手続きは、執行役員が会社と委任契約を結んでいるか、雇用契約を結んでいるかで異なります。社員が委任契約によって執行役員に就任する場合には、一度会社を退職する形になるため、社会保険の資格喪失手続きが必要となります。
ただし取締役等の会社法上の役員を兼ねているような場合であれば、健康保険と厚生年金保険の適用を受けることになります。
また社員としての雇用契約を会社と結んだまま、執行役員に就任するのであれば、随時改定に該当するような場合を除いて特別な手続きは不要です。
会社が倒産したら失業保険はもらえる?
雇用保険に加入している社員は失業したら失業保険がもらえますが、役員の場合は雇用保険の対象ではないため、失業保険をもらうことはできません。
特例として受けられるケースもあるそうですが、基本的には
まとめ
社員が昇進し、内部から役員に就任する際には、雇用保険被保険者資格喪失届の提出等、外部から新たに役員が就任する場合とは、異なった手続きが必要です。
また兼務役員に該当するか否かも労働者性等の実態を見て判断する必要があり、慎重に検討を行う必要があります。
執行役員に関しては、会社法上の定めもなく、待遇等も自由に決定できることから、会社が執行役員をどのような位置づけにしたいのか明確にすることが必要です。
当記事では、役員就任に際して必要な社会保険手続きや兼務役員、執行役員について解説をしてきました。役員就任に関しての手続きに疑問がある場合には、当記事を参考にして正しい手続きを行ってください。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
GVA 法人登記なら、役員辞任登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員辞任の効力は、該当する役員の辞任の意思表示が会社に到達した時点で発生します。その為、急いで役員辞任登記手続きをしなければならない場合も多く、いざとなってバタバタしてしまうこともあります。そのようなときの備えとして、事前に役員変更手続きの方法は認識しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
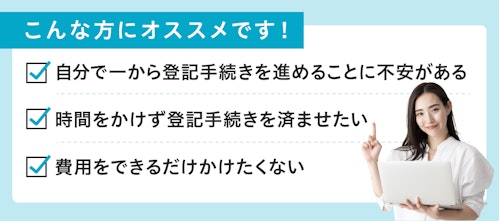
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員辞任の場合)
- 辞任届
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員辞任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\役員変更登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

