資本金は会社設立や増資に際して会社へ出資した金額を示すもので、事業を行う上での元手となります。
会社設立時の資本金に下限はありませんが、安定的な会社運営のためにはある程度の資本金が必要です。ただし、多ければ多いほど良いというわけでもありません。そのため「資本金はどれぐらい用意するべき?」とお悩みの人も多いでしょう。
今回は中小企業の設立時に必要な資本金の目安や平均額、資本金の決め方について詳しく解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
資本金とは?
はじめに資本金の基本情報として、資本金の概要や中小企業における資本金の平均額、資本金の役割を紹介します。
資本金とは?
資本金とは株主や投資家、経営者などの出資者によって払い込まれるお金です。出資者が会社に対して出資した額(払い込んだ額)が、原則、資本金として財務諸表や登記簿謄本に記載されます。
資本金は事業の元手となるお金です。特に会社設立時に払い込まれる資本金は、事業活動の初期費用や、事業が軌道に乗るまでの資金源として重要な役割を果たします。
現行の会社法に会社設立時の資本金に関する決まりはありません。そのため理論上は1円の資本金でも会社設立が可能です。ただし安定的な会社運営のためには、ある程度の資本金は必要になるでしょう。資本金の大きさは会社の体力を示す基準となり、安定して事業活動ができることの証明にもなります。
とはいえ、資本金が多ければ多いほど良いわけではありません。会社設立時の資本金額は慎重に決める必要があります。
なお、株主から払い込まれた出資金のうち、資本金の2分の1を超えない金額までは資本準備金として計上もできます。資本準備金は赤字の補填や資本金額の調整等に用いられるケースが多いです。資本準備金は資本金と同じく純資産として扱われますが、資本金と違い、登記簿謄本には記載されません。
中小企業における資本金の平均額
中小企業における資本金の平均額を推測する上での参考材料として、総務省・経済産業省による経済センサス活動調査の結果を紹介します。
令和3年経済センサス‐活動調査によると、資本金階級別に企業を区分した時に、最も企業数が多いのは「300万円~500万円」です。企業数の多い資本金階級を上から5つ紹介します。
1.資本金300万円~500万円未満:578,882社
2.資本金1,000万円~3,000万円未満:555,646社
3.資本金500万円~1,000万円未満:253,148社
4.資本金300万円未満:200,501社
5.資本金3,000万円~5,000万円未満:72,933社
上記のデータには増資による払込も含まれるため、必ずしも会社設立時の資本金を表しているわけではありません。そのため会社設立時に絞った資本金の平均を出すことはできませんが、ボリュームゾーンである300万円~500万円をひとつの指標と考えて良いでしょう。
ただし、資本金の額は業種や会社規模によって大きく異なります。資本金の平均額に合わせるのではなく、平均額はあくまで参考材料の1つとし、自社にとっての必要額を設定することが大切です。
資本金の役割
資本金の役割は大きく2つに分けられます。
1つ目は会社運営や事業活動の元手としての役割です。特に開業準備の期間や会社設立直後で売上収入が入らないうちは、資本金が直接的な活動資金のひとつとなります。
2つ目は会社の安定性や信用度の指標としての役割です。資本金の大きさは資金力や各種リスクへの備え等、会社の体力の証明につながります。そのため資本金が大きいと、取引先や顧客からの信用を得やすくなる可能性が高いです。与信調査や融資審査など、資本金が判断材料の1つとなる場面も存在します。
なお、許認可を受けるために一定の資本金額が必要なケースもあります。許認可が必要な業種で会社設立をする場合、許認可を受けるための資本金要件を満たすことを最優先に考えましょう。
資本金要件が含まれる許認可の主な例を紹介します。
- 有料職業紹介:500万円以上(事業所が複数の場合は500万円×事業所数)
- 人材派遣業:2,000万円以上(事業所が複数の場合は200万円×事業所数)
会社設立時に資本金を決める際の考え方
資本金には活動資金や会社の安定性・信用度の指標としての役割があります。会社設立時の資本金に下限がないとはいえ、ある程度の額が必要なのは事実です。
一方、資本金が一定よりも大きいと支払う税金が高くなってしまいます。節税面を考慮し、大きくなりすぎないよう調整するのも考え方の1つです。
この章では会社設立時に資本金を決める際の考え方を3つ紹介します。
初期費用と運転資金を計算する
まず、初期費用と運転資金を計算しましょう。
会社設立にかかる初期費用や売上収入・利益を得られるまでの運転資金は、基本的に自身で用意する必要があります。設立時に払い込んだ資本金だけでは足りない場合、役員から会社に貸し付けるお金(役員借入金)を利用することも可能です。
ただし役員借入金は貸借対照表の負債の部に計上されるお金であり、役員借入金が計上されれば自己資本比率が下がってしまいます。自己資本比率が低いと財政面のバランスが悪く経営の安定性が低いとみなされ、第三者からの信用度が下がる恐れがあります。
会社設立直後から自己資本比率が低い状態というのは避けるべきでしょう。初期費用や当面の運転資金は資本金でまかなうのが理想です。
初期費用や運転資金を計算する上で考えるべき要素の例を紹介します。
- 設備資金:オフィスや店舗の初期費用、内装工事費、器具備品代、事務用品費等が挙げられます
- 運転資金:運転資金とは事業を行う上で継続的に必要となるお金です。仕入、人件費、通信費、地代家賃等、事業活動のために毎月発生するお金はすべて運転資金となります
- 会社の成長計画:売り上げ予算や将来の事業拡大、新規事業の立ち上げ等の成長計画も考慮できるのが理想です。ただし、設備資金・運転資金に比べると優先度が下がります
融資の要件を満たす基準をクリアする
創業融資の利用を検討している場合、融資の要件を満たせるような資本金を設定しましょう。
創業融資の審査で重視される要素の1つに自己資金があります。自己資金が少ない場合、返済能力に懸念がある・創業に向けた準備が不十分等、審査でマイナス評価になってしまう恐れが大きいです。金融機関からの信用を得られず融資審査に通過できない可能性があるため、なるべく多くの資本金を用意しましょう。
日本政策金融公庫の「2023年度新規開業実態調査」によると、2023調査年度における開業時の資金調達額の平均は以下の通りです。
自己資金は金融機関等からの借入の約36%となっています。したがって、あくまで目安ですが、希望する融資額の3~4割程度の自己資金は用意するべきと考えられます。
なお、融資審査における資本金と自己資金は正確にはイコールではありません。自己資金とみなさされるのは、お金の出所が明確であり、返済義務がないと認められたお金のみです。資本金として計上したお金の全額が自己資金であると証明できるよう、お金の出所を示す資料をしっかり用意する必要があります。
また、会社設立時に見せ金を計上するのは厳禁です。
見せ金とは会社設立時の資本金や自己資金を実際よりも多く見せかけるために、一時的に借りてきたお金です。親戚や友人知人、金融機関等、借入先は問いません。資本金や自己資本の額を偽る目的で計上する一時的な借入金は、すべて見せ金とみなされます。
刑法157条1項「公正証書原本不実記載罪」において、登記簿・謄本簿等の公文書に虚偽の記載をすることは違法と定められています。見せ金を使った会社設立は資本金額を偽って登記を行ったことになるため、同罪にあたる恐れが大きいです。5年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される恐れがあるため、見せ金は絶対にやめましょう。
税金を考慮して資本金額を考える
税金を考慮して資本金額を決めるのも考え方の1つです。
会社に課される税金の中には、資本金の大きさによって税額が変わるものもあります。そして資本金額を1,000万円未満に設定しておくと、節税につながる可能性があります。
たとえば法人住民税の均等割は、資本金等の額や従業員数等、会社の規模が大きくなるほど金額も高くなる仕組みです。資本金等の額では全部で5つの区分があり、資本金等1,000万円以下の時に最も税額が低くなります。
資本金額が1,000万円未満であれば、消費税の節税も可能です。設立時の資本金額が1,000万円未満の場合、設立から2年間は消費税の納付が免除されます。一方、設立時の資本金額が1,000万円以上の場合、設立1期目から消費税の納付義務が生じます。
節税という観点で考えると、資本金は1,000万円未満に抑えるのが最適です。
資本金の種類について紹介
資本金は現金で払い込まれるのが一般的ですが、現金以外で用意する方法も存在します。この章では資本金の種類について解説します。
資本金の種類は大きく分けて2つ
資本金の種類は大きく2つに分けられます。
1つ目は現金です。最も一般的な資本金の形態であり、払い込んだ額面金額がそのまま資本金として計上されます。会社設立前は法人口座がないため、発起人の個人口座に払い込みます。
2つ目は金銭に代わりモノで出資する現物出資です。現物出資に使える資産は原則として現金化できるものに限られます。主な例として、有価証券、不動産、車両などが挙げられます。
現物出資のメリットは、現金がなくても資本金を用意できる点です。また、1単位あたり10万円を超える資産は減価償却資産として扱われ、減価償却による節税対策も実施できます。
現物出資の大きなデメリットは、現金による出資と比べて手間が大きい点です。現物出資に用いる資産の価値算定が必要なだけでなく、定款への記載項目が増え、資産によっては登記も必要となります。また、資本金として計上する額に比べて現金の割合が少なくなってしまう点にもご注意ください。
資本金の考え方を押さえて自社に適した額を決めよう
中小企業の資本金は、300万円~500万円が1つの目安といえます。ただし、資本金の適切な額は会社の規模や業種によって大きく異なるため、平均額に合わせれば良いとは限りません。初期費用や運転資金、許認可等を考慮した上で、自社に適した金額にする必要があります。
今回紹介した内容を押さえ、適切な資本金額を決めた上で会社設立を進めましょう。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。
書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。
募集株式の発行についての詳細はこちら
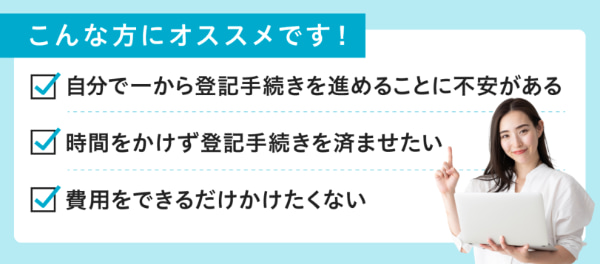
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 払込証明書
- 取締役会議事録
- 総数引受契約書
- 資本金の額の計上を証する書面
- 会計帳簿(DESの場合)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\増資の登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
%20(2).jpg)
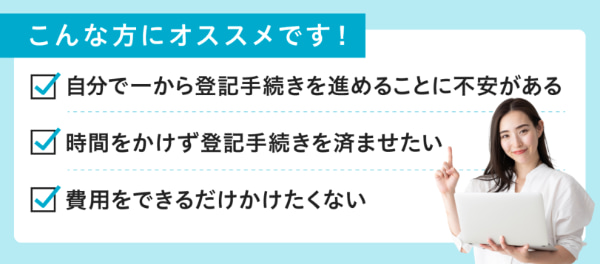
.jpg)



