会社の資金調達方法には借入など様々な方法が考えられますが、会社法においては株式会社の資金調達は新株発行による増資引受が主な方法として想定されています。
新株発行は多額の金銭を調達できる可能性があり、負債を負わないという点でメリットはあるものの、様々な手続きがあり、時間がかかるため資金調達方法として用いにくいと感じられている経営者の方は多いかもしれません。
そこで、今回は新株発行のうち、特に総数引受契約によって行う方法について分かりやすく解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
増資(募集株式の発行)の登記を自分で申請するなら
募集株式を発行しての増資では、社内での決議に加えて登記申請が必要です。株価や発行する株式数の検討などもあるため、他の登記手続きに比べると複雑になりがちです。GVA 法人登記なら、増資に関する情報を入力することで登記書類を7分で作成し、自分で申請できます。
GVA 法人登記はこちら
総数引受契約とは
1.1総数引受契約の概要
会社法上の募集新株発行の方法には、第三者に対して株式を発行する第三者割当(会社法(以下省略)第199条)と既存の株主へ株式を付与する株主割当(第202条)があります。
いずれも非公開会社の場合には株主総会決議、公開会社の場合には取締役会決議により募集事項について定める必要が原則あります(第201条第1項、第199条第1項)。
総数引受契約を用いる場合はこのうちの第三者割当増資に当たります。通常の第三者割当は不特定多数に対して、募集に対して申し込みに応じた数の株式を付与することも想定されています。
しかしながら、実務では上場企業等の第三者割当増資を除き、全く無関係の第三者に株式を付与するというケースも考えにくく、関係者や取引先へ株式を付与するケースがほとんどです。そのような場合には、総数引受契約による方法で株式を発行する場合があります。総数引受契約は、発行した株式を1人または複数の人間に全て付与するという内容の契約で、株式を引き受ける者と締結するものになります。
1.2総数引受契約が用いられる場面
総数引受契約は、一般的な募集新株発行と異なり、最初から発行される新株を引き受ける者が定まっているため、募集新株発行の手続きを一部省略して行うことができ短期間で多額の資金調達が可能という特徴があります。
そのため、短期間で確実に資金調達を行いたいというケースで活用されています。
1.3第三者割当との違い
前述のとおり総数引受契約による方法は第三者割当の一類型です。ただし、通常の第三者割当は募集時には株主になろうとする者が定まっていない場合もあります。
これに対し、総数引受契約による場合は新株を引き受ける者が決まっており、発行される新株が全て引き受けられることが決まっている場合に用いられます。
そのため、募集株式における手続きの一部を省略することが可能です(第205条第1項)。詳細は後ほど解説しますが、こうした予め株式を引き受ける者が決まっている点と手続きの省略が可能という2点が一般的な第三者割当との違いになります。
第三者割当増資における総数引受契約書作成のポイント
では、総数引受契約を用いる場合に新株引き受けを行おうとする者と締結する総数引受契約書はどのような点に注意して契約書を作成すべきでしょうか。
総数引受契約書とは
「総数引受契約書」とは総数引受契約を締結するための契約書です。総数引受契約の流れの中でも最も重要なプロセスといえます。基本的には第三者割当増資を前提とした株式引受契約といった内容になります。
①募集株式の総数を引き受ける旨
文字どおり、募集株式のすべてを引き受けることを目的とした契約であるため、その旨が読み取れるような記載が必要になります。
例えば、「募集株式の総数を引き受ける。」、「募集株式の総数を他の引受人と共に引き受ける。」といった記載や、引受人及び割当株式数が一覧に記載しているなどによって、総数引受契約と評価することができます。
②募集株式の特定
作成する総数引受契約が、どの募集事項に基づくものかをしっかりと特定する必要があります。特定の方法としては、何日付けの株主総会や取締役会で決議された募集事項か、募集事項の内容として、以下の事項を記載する方法などが考えられます。
(1)募集株式の種類及び数
(2)払込金額
(3)増加する資本金・資本準備金に関する事項
(4)払込期日
③契約当事者
総数引受契約は、募集株式の総数を引き受ける1人または複数の個人または法人と締結します。必ずしも、1通の契約書で全員で締結しなければならないというものではないため、署名や押印のやり易い形で作成すると良いでしょう。
総数引受による新株発行の手続きとメリット
総数引受による新株発行の手続きは以下の流れで行われます。なお、ここでは一般的に多く見られる非公開会社かつ取締役会設置会社の場合を念頭に置いた手続きとします。
①株主総会における募集事項の決定(第199条第1項、同条第2項)
②総数引受契約の締結
③出資金の払込み
④登記手続き
以上のような流れで新株発行が行われます。
注意が必要なのは、非公開会社の場合には株式が譲渡制限株式になるため、①の決議は特別決議になるという点です(第309条第2項第5号)。公開会社の場合にはこうした手続きは取締役会でできる(第201条第1項)ためこの違いについては留意しましょう。
総数引受契約によらない第三者割当増資の手続きでは②に代わり、株主になろうとする者への募集事項等の通知に始まり、株主になろうとする者からの申し込み、会社がそれに対してどれだけの数の割り当てを行うか決定を行い、その割当について通知する、という手続きが発生します(第203条、第204条)。
ただし、総数引受契約の場合にはこうした手続きを省略することができ(第205条第1項)、手続きの簡略化が総数引受契約の最大のメリットといえます。
総数引受を行った後の手続き(登記手続き)
4.1登記手続き
総数引受契約を締結し、出資金の払込みを受けた後は発行済株式総数や資本金額に変動が生じるため登記手続きが必要です。
一般的な登記手続きと同様に2週間以内に行う必要(第915条第1項)があるため、添付書類などがスムーズに準備できるように以下を参考に必要な書類を予め確認しておきましょう。
4.2登記手続きに必要な添付書類
総数引受契約によって新株発行を行った場合には以下の添付書類が必要になります。なお、ここでも先ほどの手続きと同様に非公開会社かつ取締役会設置会社を念頭に置いたものとします。
・変更登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・取締役会議事録
・総数引受契約書
・払込証明書
・資本金計上証明書
以上が添付書類として必要となります。払込証明書は自社で作成が必要になるケースが多いため、あらかじめどういった書式を作成するのか確認しておくとよりスムーズに手続きが可能となるでしょう。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。
書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。
募集株式の発行についての詳細はこちら
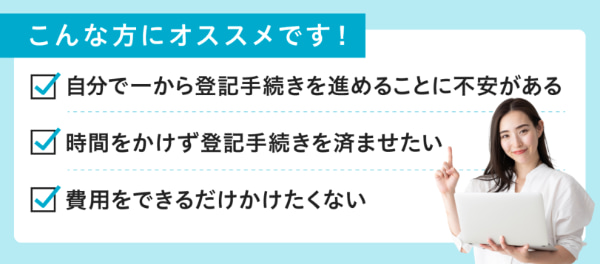
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 払込証明書
- 取締役会議事録
- 総数引受契約書
- 資本金の額の計上を証する書面
- 会計帳簿(DESの場合)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\増資の登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

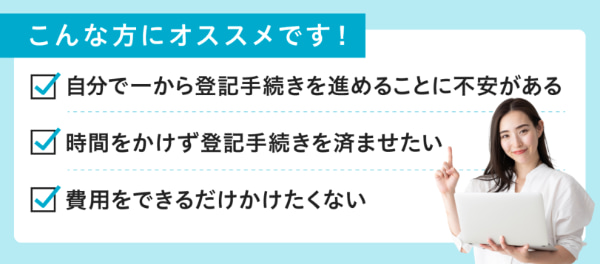
.jpg)



