剰余金の配当とは、一般に、決算によって確定した繰越利益剰余金等を分配することを指します。この剰余金の配当を行える限度額である分配可能額(配当可能な限度額)については、会社法等で計算方法が規定されています。また、剰余金の配当を行うには必要な手続きを経なければいけません。
そこでこの記事では剰余金の配当について詳しく解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
そもそも剰余金ってなに?
剰余金(じょうよきん)とは、企業が事業活動によって得た利益から、税金や事業活動に必要な資金を差し引いた残りの金額のことをいいます。
株主資本の一部であり、株主に配当されるほか、企業の事業拡大や設備投資などに充てることができます。
そのため、剰余金は企業の健全性を示す重要な指標の一つです。
剰余金が多い企業は利益を継続的に得ており、財務基盤が安定しているといえます。
剰余金等の資本組入れの登記ならGVA 法人登記が便利です
GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで剰余金等の資本組入れの登記申請書類を簡単に作成。作成後は法務局に行かずに郵送で申請できます。郵送申請サポート、収入印紙もセットで購入できるので、登記申請に伴う手間を大きく削減できます。
サービスサイトはこちら→GVA 法人登記
剰余金の分配可能額計算方法
剰余金の分配可能額とは、会社法にて、債権者を保護するため、企業が得た利益剰余金の中から、会社財産を株主に払い戻す金額の上限を定めたものです。
以下で計算方法を解説します。
分配可能額の計算
分配可能額の計算は以下のとおりです(会社法第461条第2項)。
1 (+)分配時点における剰余金の額
2 (+)臨時決算をした場合の利益
3 (+)臨時決算をした場合の自己株式の処分対価
4 (-)分配時点の自己株式の帳簿価額
5 (-)事業年度末日後に自己株式を処分した場合の処分対価
6 (-)臨時決算をした場合の損失
7 (-)その他法務省令で定める額
分配時点における剰余金の額
分配時点における剰余金の額の計算は以下のとおりです(会社法第446条)。
ア (+)資産の額
イ (+)自己株式の帳簿価額の合計額
ウ (-)負債の額
エ (-)資本金・準備金
オ (-)法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
なお、事業年度の末日時点の上記の額から、事業年度の末日後に自己株式の処分や資本金・準備金の減少、自己株式の消却や剰余金の配当を行った場合は、それぞれの加減が反映され、剰余金の額が算定されます。
その他法務省令で定める額
上記7の「その他法務省令で定める額」とは、具体的には以下のア〜ケの金額のことです。
ア 最終事業年度の末日におけるのれん等調整額(会社計算規則第158 条第1号)
イ 「最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差損」と「最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差損」(会社計算規則第158条第2号第3号)
ウ 株式会社が連結配当規制適用会社であるときの連結配当規制控除額(会社計算規則第158条第4号)
エ 2回以上臨時決算をした場合の最終の臨時計算書類の利益等(会社計算規則第158条第5号)
オ 資本金及び準備金等の額が300万円を下回る場合の不足額(会社計算規則第158条第6号)
剰余金の配当は純資産額が300万円未満であれば行えません(会社法第458条)。
そこで分配可能額の計算から以下の金額(0未満である場合にあっては0)を減額し、剰余金の配当後も純資産が300万円以上である状態を維持できるように対応がなされています。
分配可能額の計算から控除される金額(0未満である場合にあっては0)の計算
300 万円-(資本金の額+準備金の額+新株予約権の額+評価・換算差額等計上額 )
これにより、分配可能額の範囲内で配当がなされる限り、配当後も純資産が300万円を下回らないようになっています。
カ 臨時決算をした場合の吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式の対価(会社計算規則第158条第7号)
キ 最終事業年度の末日後に株式の不公正発行等に伴う引受人責任よるその他資本剰余金(会社計算規則第158条第8号)
ク 最終事業年度の末日後に自己株式の取得と引換えに当該株式の株主に対して自己株式を交付したときの当該取得した株式の帳簿価額(会社計算規則第158条第9号)
ケ 最終事業年度の末日後の吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式の対価(会社計算規則第158条第10号)
剰余金の配当可能額の計算方法
剰余金の配当可能額とは、実際に株主に配当として支払いことができる金額を指します。
一般的に配当可能の限度額は、剰余金の分配可能額から法定準備金を差し引いた金額を言います。
具体的な計算式に入る前に計算式となる要素のキーワードについて触れます。
- 純資産額: 企業の総資産から負債を差し引いた額のことを言います
- 資本金 :企業の資本金をいいます
- 資本準備金: 資本金の増加に伴って積み立てられる準備金をいいます
- 利益準備金: 法令や定款で定められた準備金で、当期利益から積み立てられる金額をいいます
この要素から指揮を組み立てるとこのようになります。
純資産額-資本金-資本準備金-利益準備金-対象となる決算期に積み立てる必要がある利益準備金
となります。
剰余金の配当に必要な手続き
株主総会による決議
剰余金の配当は、原則として、株主総会の普通決議によって決定します(会社法第454条)。この決議においては、以下の事項を定めます。
ア 配当財産の種類及び帳簿価額の総額
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
ウ 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
アの配当財産の種類は通常、金銭ですが、金銭以外の現物を配当することも可能です(会社法第454条第4項)。
イの割当てに関する事項としては、種類株式を発行している場合には株式の種類に応じて異なる取扱いとすることが可能です(会社法第454条第2項)。
なお、配当財産の割当ては株主の有する株式の数に応じることを内容としなければなりません(会社法454条第3項)。
中間配当に関する定款の定め
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって配当をすることができる旨を定款で定めることができます(会社法第454条第5項)。これにより中間配当について取締役会が決定することができます。
中間配当は3月決算の場合には9月末を基準日とすることが多いですが、会社法上は事業年度内であればいつでも行うことができます。
分配可能額を超えて配当した場合
分配可能額を超える剰余金の配当をした場合、当該剰余金の配当の議案を提案した取締役は、会社に対して、配当を受けた株主と連帯して、配当された金額を支払う義務を負います(会社法第462条)。
この責任の免除には総株主の同意が必要となります(会社法第462条第3項)。
配当後の積立
配当を行った場合、配当額の10分の1に相当する金額を資本準備金又は利益準備金として計上しなければなりません(会社法第445条第4項)。この積立計上は資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の額の4分の1に相当するまで行わなければなりません(会社計算規則第22条)。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
GVA 法人登記なら、剰余金等の資本組入れの登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
剰余金等の資本組入れの登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?通常の増資と比較したり、準備金や剰余金を区別したりと、専門知識が求められることもあります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしてもやりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が何とかするしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば剰余金の資本組入れの手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。
書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。
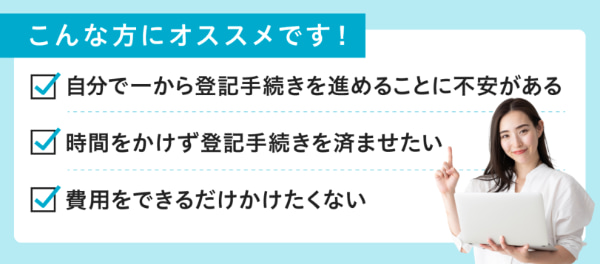
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(剰余金等の資本組入れの場合)
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 準備金・剰余金の額に関する証明書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\剰余金の資本組み入れの登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
.jpg)
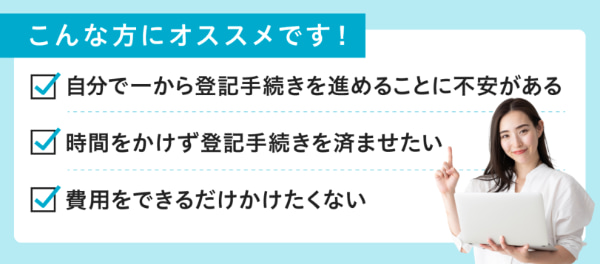
.jpg)



