資金調達の方法として増資がありますが、増資をするにはいくつかの方法があります。なかでも多いのが「募集株式の発行」による増資ですが、そのうち「株主割当増資」や「公募増資」といったものはご存知でしょうか?本記事ではこれら増資の方法のうち「株主割当増資」について基礎知識から手続きの流れまでを解説します。
株主割当増資とは?メリット・デメリットから手続きの流れを紹介

- 増資の際の変更登記ならGVA 法人登記が便利です
- 株主割当増資とは?
- 株主割当増資のメリット
- 増資後の株主構成比率(持株比率)が変わらない
- 株主割当増資のデメリット
- 大規模・戦略的な資金調達につながりにくい
- 既存株主が引き受けない
- 株主割当増資の手続きの流れ
- ①募集事項の決議
- ②募集株式の引受けの申込み
- ③出資の履行
- ④増資の登記申請
- 株主割当増資で増資したら登記申請が必要です
- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
- ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
- GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
増資の際の変更登記ならGVA 法人登記が便利です
増資をした場合は登記申請が必要です。申請に必要な書類作成はGVA 法人登記が便利ですので、ぜひお試しください。
GVA 法人登記の特徴
- 登記の知識がなくても案内に従い情報を入力するだけで書類が作成できる
- ネットで書類作成ができるので専門家とのやりとりなどが必要ない
- 書類作成後の郵送申請もサポート
GVA 法人登記はこちらです
株主割当増資とは?
株主割当増資は増資の方法の一つで、既存の株主に対して、持株比率に応じて新株を発行して引き受けてもらう(出資してもらう)ことで発行企業は資金調達を行います。
特徴としては、既存の株主に対してそれぞれの持分比率に応じて株式を新たに発行し出資してもらうという点があります。株主ごとの持株比率を変えないため、個別の調整が少なく済むといったメリットがあります。
たとえば、1000株を持つ株主Aと500株を持つ株主Bがいる場合、新たに発行される株式は持ち株数の比率である2:1という比率で割当てられます。株主Aに100株を割り当てるとすると、株主Bには50株が割当てられ、増資後の持ち株数は、株主A:1100株、株主B:550株となります。
「募集株式の発行」のうち、任意の既存株主もしくは新しい株主候補に新株を発行することは「第三者割当増資」と言われます。機動的に増資ができる反面、新たに割り当てる株価をどう算定するか?や新株発行後の株価(企業価値・ 時価総額)をどうするか、既存株主の持ち分の希釈化などさまざまな調整が発生します。
株主割当増資であれば、既存株主全員が同じ条件で新株を引き受けるため、これら調整の手間が減らせる可能性が高くなります。
株主割当増資のメリット
株主割当増資のメリットを整理すると以下があげられます。
増資後の株主構成比率(持株比率)が変わらない
新株を割り当てた既存株主が出資に応じれば株主構成は変わりません。企業価値全体に対する比率なども変わりませんので、事前の株主間での調整や、増資後の経営への関与に影響が出にくく、スムーズに資金調達を実施できる場合があります。
株主割当増資のデメリット
反面、デメリットとして以下が考えられます。
大規模・戦略的な資金調達につながりにくい
株主割当増資は、出資する株主側からみると持株比率は変わらず資金だけを供出するともいえます。つまり、外部から有力でパートナーシップが期待できる株主や、特定の株主から大きな資金調達をするといった戦略的な資金調達は難しくなります。
既存株主が引き受けない
株主割当増資は、ある意味では株主側の権利は変わらず出資だけを求められる手続きといえます。株主間の条件調整がない反面、そもそもの増資の理由やメリットを理解してもらう必要があります。
株主割当増資の手続きの流れ
非公開会社における株主割当増資の基本的な手順は以下のとおりです。
①募集事項の決議
「発行する株式の内容」を決定するための決議を行います。ここでは、
- 今回新たに発行する株式の数
- 1株当たりの払込金額
- 増加する資本金の額
- 払込期日
- 現物出資の場合は、その旨及び当該財産の内容、価額
- 株主割当である旨
- 株式引受の申込期日
が対象となり、原則として株主総会の決議によって決定されます。
※公開会社では取締役会の決議によって決定することが原則となります。
②募集株式の引受けの申込み
①で決定した内容をもとに、新株を引受ける既存株主が申し込みをします。
③出資の履行
申込後、新株を引受ける既存株主は払込期日に出資金の払込みを行います。
④増資の登記申請
増資が完了したら、会社の登記簿に株式数や資本金額の変更を反映するための登記申請を行います。完了後、2週間以内に登記する必要があるので速やかに申請しましょう。
なお、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合は定款の変更も必要です。
株主割当増資で増資したら登記申請が必要です
株主割当増資による増資が完了したら登記に反映するための登記申請を行います。
会社がいくつの株式を発行しており、資本金がいくらなのかは登記されます。会社の状態を公示することで安全で円滑な取引を実現するために法律で定められており、増資完了後2週間以内の申請が必要です。
(ちなみに融資による資金調達では登記の必要はありません)
登記申請書に、募集株式により増加した「資本金の額」及び「発行済株式の総数」の他、会社の基礎情報など必要事項を記載し、添付書類として「資本金の額」及び「発行済株式の総数」に変更があったことを証明できる書類を一緒に提出します。
法務局に提出した申請が受理され、登記に反映されることで、増資に関する手続きが完了となります。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。
書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。
※GVA 法人登記では株主割当増資の登記申請書類作成には対応していないのでご注意ください。
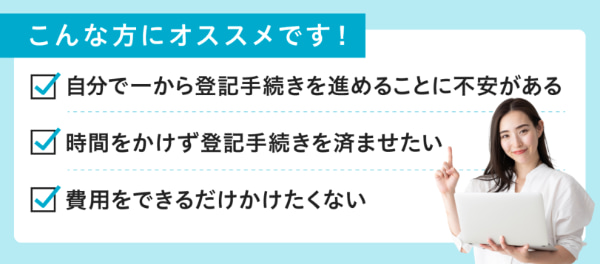
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 払込証明書
- 取締役会議事録
- 総数引受契約書
- 資本金の額の計上を証する書面
- 会計帳簿(DESの場合)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\増資の登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

