増資(募集株式の発行)とは、会社が新しく株式を発行し、投資家からお金を集めることです。増資による資金調達は株価に影響を与えます。そのため、不用意に行うと既存株主の信頼を失うことに繋がりかねず、計画的に行う必要があります。
この記事では増資の方法を3つ紹介し、増資が株価にどのような影響を及ぼすのかについて解説します。
増資(募集株式の発行)が株価に与える影響について解説
.jpg)
増資(募集株式の発行)の登記は自分で申請できます
増資の手続きには様々なプロセスがありますが、社内での決定や金銭の払込みの後に登記申請が必要という特徴があります。GVA 法人登記などのサービスを利用すれば、Webサイトから必要な情報を入力することで増資の登記申請に必要な書類を自動作成し、自分で申請できます。
増資の3つの方法
増資の方法は、株式引受の権利を与える相手の違いから、以下の3つに分類されます。
- 不特定多数に対して株式引受の権利を与える「公募増資」
- 既存の株主に対して株式引受の権利を与える「株主割当増資」
- 特定の第三者に対して株式引受の権利を与える「第三者割当増資」
公募増資
公募増資とは不特定かつ多数の投資家が株式を引き受ける増資のことです。公募増資の目的は経営に必要な設備投資などの資金を広く投資家から集めることです。それと同時に株主数を増やすことや株式の流通量を増加させることにも繋がります。
株主割当
株主割当とは新株の割り当てを受ける権利を既存株主に与える増資のことです。
株主割当では株主に持株数に応じて新株が割当てられます。しかし割当てを受けた株主は必ず新株を引き受けなければならないわけではなく、申込みをしなければ権利は失われます。
第三者割当増資
第三者割当は特定の第三者に対して新株を発行する増資のことです。割当てを受けなかった既存株主には、持株比率が低下するという不利益が生じます。
第三者割当は会社の資金調達方法の1つです。しかし、株式を引き受けると議決権比率が高まるのでM&Aにおいても活用されています。取引先等の縁故者に新株の割当てがなされることが多いので、縁故募集(えんこぼしゅう)と呼ばれることもあります。
また、敵対的買収の対象となった会社が買収会社の持株比率を低下させるために、買収防衛策の一環としてホワイト・ナイト(対象会社にとって友好的な事業戦略上のパートナー)に対して第三者割当を行うケースもあります。
第三者割当は割当てを受けなかった既存株主の持株比率が低下する上、不公正な価格で新株発行が実施された場合は経済的な不利益を被る恐れもあります。そのため、特に有利な金額で株式を発行する手続きについては会社法にて詳細に決められています。
増資が株価に与える影響
増資を行った場合、発行済株式の総数が増え、1株当たりの価値が低下することに繋がるケースがあります。
株価は、「株価収益率(PER)×1株あたりの利益(EPS)」で算定することが多く、1株あたりの利益(EPS)は、「当期純利益÷発行済株式数」で算出します。増資を行うと発行済株式の総数が増えますので、1株あたりの利益(EPS)は自然に低下することになります。
一方で、株価収益率(PER)は業界平均やマーケット平均と比較した水準を用いるため、特に変動しません。1株あたりの利益(EPS)が増資により低下し、株価収益率(PER)が変動しないと相対的に株価が下がることになり、これを「株式の希薄化」といいます。
もちろん、必ずしも株価が低下するわけではなく、成長などが見込めると期待された場合には株価が上がる可能性もあります。
増資の方法によっても株価への影響は若干異なることがあります。
第三者割当増資をすると株価は下がる?
上述の公募増資は比較的ポジティブでシンプルな資金需要の場合が多いですが、第三者割当増資は、資金需要はもちろん、M&Aや救済目的、戦略的な提携など背景が多様化する傾向があります。これら背景によっては株価が上がるケース/下がるケースが明確に分かれる可能性があります。
特に、第三者割当増資をすると株を追加発行するため、発行する株式の数を増やすため、1株あたりの価値を下げてしまいます。これは、ケーキを10人で分けるよりも20人で分ける方が一人当たりのケーキの量が減るようなものです。株式数が増えれば、1株当たりの利益が減少するため、株主は自分の持ち株の価値が低下したと感じ、株式を売却しようとする動きが強まる可能性があります。新規の投資家も将来の株価が下がる可能性を懸念し、投資を躊躇するかもしれません。そのため、多くの場合は、第三者割当増資は株価の下落要因となります。
募集事項の決定
募集株式の発行を行う場合には、「募集事項の決定」が必要です。「募集事項」は以下のとおりです。
① 募集株式の数
② 募集株式の払込金額又は算定方法
③ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨・その財産の内容・価額
④ 払込み等の期日又はその期間
⑤ 株式を発行するときは増加する資本金・資本準備金に関する事項
公募・第三者割当
公開会社の場合
公開会社とは、会社法の定義によると、譲渡制限されていない株式を発行している株式会社のことです。1株でも譲渡制限されていない株式があれば、残り全てに譲渡制限が付されていても公開会社に該当します。株式の譲渡制限とは譲渡による株式の取得について、株式会社の承認を必要とすることです。
注意していただきたいのは、会社法上の公開会社は証券取引所への上場会社(IPO)を意味しているわけではないことです。株式を上場してなくても、公開会社に該当するケースが存在します。
公開会社においては、募集事項の決定は取締役会決議で行います。ただし、募集株式の払込金額が特に有利なものである場合(有利発行)は、株主総会の特別決議が必要です。
取締役会の決議により募集事項を定めたときは、払込期日又は払込期間の初日の2週間前までに、株主に対し当該募集事項を通知・公告しなければなりません。ただし、金融商品取引法で規定された届出をしている場合等は、通知・公告は不要です。
非公開会社の場合
非公開会社とは公開会社でない会社、つまり、全ての株式に譲渡制限に関する規定がある株式会社のことです。
非公開会社の募集事項の決定は、原則として、株主総会の特別決議で行います。ただし、払込等の期日又は期間の末日が決議の日から1年以内の日である募集については取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に「委任」することができます。委任するためには株主総会の特別決議を取ります。そしてこの場合、株主総会の特別決議においてその委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければなりません。
株主割当
株主割当における募集事項等の決定は、公開会社においては取締役会の決議で行います。
一方、非公開会社においては、定款で別段の定めがなければ、株主総会の特別決議が必要です。定款で定めれば、取締役会非設置会社の場合は取締役、取締役会設置会社の場合は取締役会の決定事項とすることができます。
株主割当においては、募集事項以外に募集株式の引受けの申込期日等を定めなければなりません。そして株主に対し申込期日の2週間前までに、募集事項・当該株主が割当てを受ける株式の数・申込期日を通知しなければなりません。株主は持株数に応じて割当てを受ける権利を有しますが、1株に満たない端数については切り捨てられることになります。
募集株式の申込み・割当て・出資の履行
募集に応じて引受をしようとする者は、書面に一定事項を記載して申込みを行います。この申込みは会社が電磁的方法を認めている場合は、電磁的方法を用いることもできます。
公募・第三者割当の場合は、株式会社は申込者の中から割当てを受ける者とその者に割当てる募集株式の数を定めなければなりません。この際、申込者に割当てる募集株式の数を申込数よりも減少することができます。ただし、募集株式が譲渡制限株式の場合の割当てについての決定は、原則として、株主総会の特別決議(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によります。
株式会社は申込者に対し、払込期日又は払込期間の初日の前日までに、割り当てる募集株式の数を通知する必要があります。一方、募集株式の引受人は定められた払込期日又は払込期間に金銭の払込み等をしなければなりません。出資の履行をしないときは、募集株式の引受人は募集株式の株主となる権利を失います。
出資の履行をした者は払込期日が決められた場合は払込期日に、払込期間が決められた場合には出資の履行した日に、募集株式の株主となります。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。
とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。
書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。
募集株式の発行についての詳細はこちら
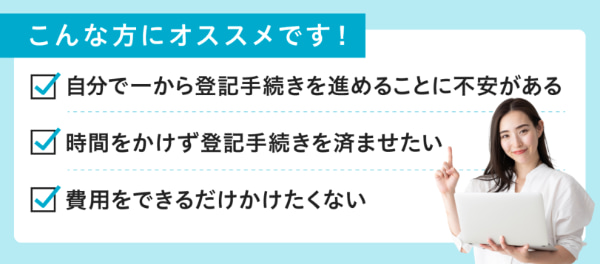
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)
- 登記申請書
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 払込証明書
- 取締役会議事録
- 総数引受契約書
- 資本金の額の計上を証する書面
- 会計帳簿(DESの場合)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\増資の登記するなら/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

