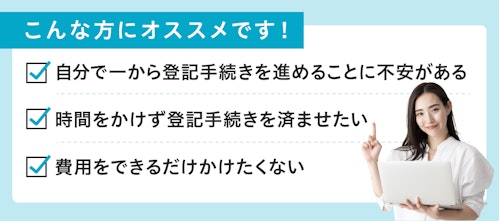取締役・監査役の役員任期とは?
株式会社の役員(取締役や監査役)には必ず任期があります。通常、取締役の任期は2年(監査役は4年)ですが、非公開会社の場合は、最長10年まで伸長することが可能です。
任期が到来した役員は原則として退任になりますが、満了後も継続して役員を務める場合は、一度退任した上で重任(再任)の手続きを経ることで継続できます。何も手続きをしなかった場合、自動で継続とはなりません。
つまり、一度役員を選任して、その後ずっと役員が変わらない場合であっても定期的に手続きが必要になります。そのため、定期的な手続きを漏れなく行うために、役員の任期を管理する必要があります。小さい企業であれば総務や代表者が、大きな企業では法務部門や総務部門が担当することが多いようです。
「任期管理といっても、全員同じ任期だから、切り替わるタイミングに一度にやればいいのでは?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、
- 任期途中で役員が辞任した
- 辞任した人の後任として交代で役員になった
- 経営体制強化のため、役員を増員、改選した
- あるタイミングで役員任期を変更した
こういったことが発生すると、徐々に任期管理が複雑になります。役員の任期は株主総会の開催が関係しますので、不備に気づいてもすぐ対応することが難しいという可能性もあります。
役員改選とは
役員任期に合わせて発生する任期満了での退任や重任、任期に限らず発生する就任や辞任など、複数の役員変更を背景に役員陣が入れ替わることを役員改選と呼ぶこともあります。背景としてはM&Aや業績の急な悪化による経営体制の刷新や、経営陣の世代交代など、会社としても大きな節目であることが多くなります。
取締役、監査役の役員任期の計算方法
役員の任期は、通常は2年(取締役)や4年(監査役)がありますが、場合によっては短縮したり最長10年まで伸長することができます。
自社の役員任期を規定後も、年数が経ったり役員の入れ替わりがあると、徐々に構成が複雑になってくることは避けられません。
今の役員の任期をどう把握すればいいのか?について以下の記事で解説していますのでご参考ください。
役員任期がジャスト2年にならないケースもある
役員(取締役)の任期は、特に定款で特別に規定していなければ2年になります。(監査役は4年)
「じゃあ役員になった日から2年後ですね」
と思いがちですが、そうではありません。
なぜかというと、取締役の任期は、会社法で「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められているため、丸2年間とならない場合も多く、また選任した日が数日違うだけで、任期が1年近く変わってしまうケース等もあります。
任期満了の度に手続きが必要なら、なるべく任期は長くしたいという考えの企業もあるかと思います。
以下の記事では、選任のタイミングで任期が変わるケースについて実例を挙げて解説しています。
選任懈怠と登記懈怠について
.jpg?w=500&h=262)
「任期満了を迎えたのに、何も手続きをしていなかった!」
この場合、厳密には以下どちらか2つのケースに該当します。
選任懈怠(せんにんけたい):株主総会など、社内での選任手続きをしていなかった
登記懈怠(とうきけたい) :任期満了後の役員状況について登記申請をしていなかった
懈怠は「サボっていた」みたいな意味です。
選任してから登記申請となるので、登記懈怠だけであればすぐ申請すれば問題ないかもしれませんが、選任懈怠の場合手続きが多くなります。
この2つの懈怠について、以下の記事で違いを詳しく解説しました。
役員任期の計算を間違えたことによるトラブル
「役員任期の計算を間違えてしまった」
まだ任期中であれば、問題ありませんが任期が切れてしまった場合、役員の定数を満たしていない状態になってしまう可能性があります。手続きの手間だけであればまだしも、もし会社に重大なトラブルや業績の大きな変化があれば責任問題にも発展しかねません。
以下の記事では役員任期を間違えるとどんな不都合があるのか?について実例をもとに紹介しています。
役員任期を伸長するメリット・デメリット
.jpg?w=500&h=262)
役員任期の管理はいろいろ手間がかかることを考えると、「役員任期はとりあえず長くしておこう」と考える方もいらっしゃると思います。
でも、ちょっと待ってください。
役員任期は長くすることによるデメリットもけっこうあるのです。
たとえば、役員のパフォーマンスに問題があったり、経営環境が変化したときに役員構成を一新する、といったことは難しくなります。任期半ばで解任するという方法もありますが、強行してしまえば損害賠償などのリスクも生じます。
以下の記事では役員任期を長く設定するメリットとデメリットをまとめました。任期を決める前に必ず一度読んでおいてください。
株式会社の取締役や監査役の役員任期を変更する方法
特に規定しなければ2年(監査役は4年)ですが、最長で10年まで任期を設定することも可能です。(非公開会社の場合)
「10年まで設定することも可能」ですが、実際にどうすれば良いのでしょうか?
まずは定款を確認してみましょう。今までに任期を変更したことがなければ、会社設立時の定款が現在の任期になります。任期が2年であれば、たいてい「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」という記載になっています。
新たに設定する任期が決まったら、株主総会で特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決議)を行い、決議したことを議事録で残せば任期変更は完了です。
【無料】役員任期変更の株主総会議事録のテンプレートを今すぐダウンロードできます
「今後、役員任期の変更を予定していて、株主総会議事録のテンプレートを探している」
「株主総会議事録を自分で作成しようと調べてみたけど、決まったフォーマットがなくてどのように書けばいいのかよくわからない」
「株主総会議事録の作成のためだけに司法書士などの専門家に相談したくない」
このような方のために、今すぐ使える役員任期変更の株主総会議事録のテンプレートを用意しました。
司法書士が監修しているテンプレートなので、安心してお使いいただけます。
.png)
役員任期変更の株主総会議事録のテンプレートはこちら
⇒役員任期変更の株主総会議事録のテンプレート
以下の記事でも役員任期の変更方法について詳しく紹介しています。
役員任期は何年にすべき?
.jpg?w=500&h=262)
役員任期は通常は2年ですが定款に記載することで「1〜10年の間で選べる」ということなります。
けっこう幅がありますが、果たして何年にするのがベストなのでしょうか?
結論としては、ケースバイケースで自社に合った年数を設定するべきです。ただ、特段の理由がなければ短くするほうがリスクは少なくなります。
任期が1年:改選や登記の手間が増える。役員本人からみても経営責任を1年で果たすとなると、できることが限られてしまうかもしれない。
任期が2〜5年:最もバランスが良い。2年以上であれば、当該役員の貢献も可視化しやすいし、数回重任(再任)するとしても手間は少ない
任期が6〜10年:自分一人や家族経営なら問題ないですが、一般的には長すぎる。10年後の経営状況や外部環境の予測が難しく、任期中の解任や辞任は手続きの手間がかかる上、最悪の場合、役員への違約金や損害賠償が発生する可能性もある。
以下の記事では任期を何年にすべきか、メリット・デメリットを合わせて詳しく紹介しています。
聞き慣れない「権利義務取締役」とは?
役員任期は満了したが、後任となる役員が選任されておらず、法令や定款に定められた員数を下回ってしまった場合、下回っている間、任期満了した役員が義務と権利を持ち続けることが法律で定められいます。これを「権利義務役員」、取締役の場合は「権利義務取締役」といいます。
この間に重大な経営責任を問われるようなことが発生した場合、取締役として解決にあたる義務や責任を追うことになります。
権利義務取締役になっていることを自覚していればまだしも、大半のケースでは後から気づくことも多いです。以下記事で詳しく解説していますので一度目を通しておきましょう。
登記懈怠の先に待っている「休眠会社のみなし解散」とは?
%20(1).jpg?w=500&h=262)
「登記懈怠といってもただの申請忘れでしょ?」
確かにそのとおりなのですが、「みなし解散」には十分注意しましょう。
みなし解散とは、12年間、登記簿に変更がないままになっている会社は経営実態がないとみなされ解散の登記がされてしまう手続きです。
登記上は存在しているけれど経営実体のない休眠会社。これはさまざまな理由で発生しますが、「解散の手続きが面倒」「とりあえず放置」といった理由で休眠会社が増えてしまえば、商業登記という制度自体が信頼されなくなってしまいます。
この問題を解決するために、平成26年度より毎年休眠会社の整理が行われるようになりました。
このみなし解散の現状とみなし解散に該当してしまった場合、どうすればいいかについて以下の記事で解説しています。
自社で役員任期管理から登記申請できる体制を作る方法

商業登記において役員に関する登記は最も頻度の高い登記です。なぜならば、意図して変更しなくても、数年の任期ごとに退任や重任(再任)などの登記が必ず発生するからです。
登記すべき事項が発生したにも関わらず申請しなければ登記懈怠(けたい)に該当してしまいますし、さらにその状態を長期間継続すると「みなし解散」という整理の対象になってしまう可能性もあります。
一定の頻度で発生する役員登記だからこそ、外部の専門家に都度依頼するのでなく自社の中で完結できるようにしたい、とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。確かに登記の申請方法は基本的に大きく変わらないルーチン的な業務なので可能ともいえます。
本記事では、自社の役員任期を管理し、任期満了のたびに発生する登記を自社で運用するために必要な作業をまとめました。
GVA 法人登記では無料で役員任期の管理ができます
GVA 法人登記では、役員任期管理サービスを無料で提供しております。会員登録後に必要情報を入力すうることですぐに利用可能ですので、役員の任期管理についてのサービスを探している方はぜひご確認ください。
役員任期管理はこちら→GVA 法人登記
さらにGVA 法人登記なら、役員変更登記に必要な書類を12,000円で作成、法務局に行かずに申請できます
役員の就任・重任・退任・辞任が発生した場合は、役員変更登記の申請が必要です。決議後(辞任の場合は辞任の意思が会社に到達した時点から)2週間以内に申請をしなければなりませので、予め役員変更登記の申請方法を準備しておくと良いでしょう。
役員変更登記は手続きに必要な書類が多く、準備しなければならない書類を確認するだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分12,000円で手続きに必要な書類をそろえることができます。また、事前に株主リストを手元に準備しておくことで、スムーズに書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。
※GVA 法人登記では役員退任のみの書類作成は行っていませんのでご了承ください。
役員変更登記についての詳細はこちら
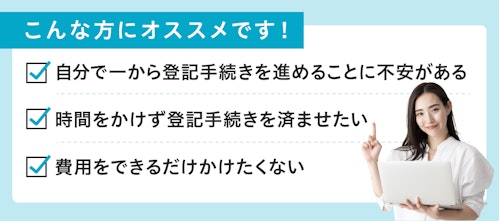
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。

GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(役員就任の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 就任承諾書
- 取締役会議事録
- 取締役決定書
- 登記申請書
- 定款
- 印鑑届書
※役員就任・重任・退任・辞任で作成される処理が異なります。上記は役員就任の場合です。
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\役員変更登記するなら/

本記事の内容は動画でも解説しています
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
.png)
.jpg?w=500&h=262)
.jpg?w=500&h=262)
.png)
.jpg?w=500&h=262)
%20(1).jpg?w=500&h=262)