そもそも定款とは?
定款(ていかん)とは、会社の基本的なルールや設計などの規則を定めた書類です。その会社の商号(社名)にはじまり、本店住所や事業目的、株式や役員に関する事項など、会社が成立するために必要な要件が網羅的に記載されています。
会社設立の際にはこの定款を作成し、内容に不備や問題ないことを確認、公証人に認証してもらった上で設立の登記をします。そのため定款に含むべき項目や内容については法律で定められており、後でちょっと変更したくなったからと勝手に変更はできない書類なのです。
法務局のWebサイトでは定款のサンプルがPDF形式で配布されていますので、イメージを掴む上でご参考ください。
参考URL:定款の例(法務局Webサイト)
株式会社の定款に記載される内容の種類
上述のとおり、定款に記載される項目は社名などの基礎的なものから株式や組織形態などまで、多岐に渡ります。必ず記載が必要なものもあれば、記載が任意のもの、記載すれば有効なものなどさまざまです。
定款に記載される項目の種類は大きく分けて以下の3種類があります
①絶対的記載事項
会社法で定められた必ず記載が必要な事項です。言い換えれば、これらが不足していたら会社が成立しない、ともいえる項目です。一番わかりやすいところでは「社名(商号)」があげられます。
②相対的記載事項
必ず記載しなければならないわけではないが、ある事項の効力を生じさせるためには定款に記載しなければならない、という事項です。対象となる事項がいくつかありますが、よく知られているのは単元株式数や、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人や委員会の設置に関するものがあります。
③任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款内に記載せずとも他で規定できる事項です。定款を作成する時点で決まってなくてもよい事項ともいえます。事業年度や役員の員数などが該当します。
絶対的記載事項とは
絶対的事項に該当する項目は以下の5種類です。会社が成立するために最低限必要な項目ともいえるでしょう。
- 商号(社名)
- 目的(会社の事業目的)
- 本店所在地(会社の住所のうち、最小行政区画まで)
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名及び住所
もしこれら事項が一つでも欠けていれば、公証人による定款認証が受けられず会社を設立できません。
また、絶対的記載事項といえども、この事項だけを決めて会社設立するのは現実的ではありませんので、相対的記載事項や任意的記載事項の中からも必要な事項を取り入れて定款を作成する必要があるので注意しましょう。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:会社の定款の絶対的記載事項について解説します
相対的記載事項とは
必ず記載しなければならないわけではないが、ある事項の効力を生じさせるためには定款に記載しなければならない、という事項です。対象となる事項がいくつかあり、主に以下のような事項等が該当します。
- 株式の譲渡制限に関する定め
- 株券発行の定め
- 取締役会の設置
- 監査役の設置
- 公告方法
- 設立時における現物出資や財産引渡
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:会社の定款の相対的記載事項について解説します
任意的記載事項とは
任意的記載事項として記載されているものの一例としては以下の事項があります。定款にあらかじめて記載しておけば、後で慌てて決めたりする手間が省ける一方、変更が生じた場合は株主総会での定款変更が必要になります。後の変更の可能性なども考慮してどの事項を入れるか決めましょう。
事業年度
事業年度は会社の財務状況などを確認するために一定の範囲で区切る期間をいいます。事業年度が決まると決算月が決まりますので、事業のトレンドや決算、株主総会などの業務の手間を考えて、負担が少なく効果的な期間を設定しましょう。
役員(取締役や監査役など)の員数
法律で定められた範囲内で取締役などの員数を設定します。員数を設定しない場合は、会社法で定められた員数となります。員数を厳密に決める他に「当会社の取締役は、3名以上とする」と幅を持たせることも可能です。
役員報酬
役員報酬を定款で決めることもできます。ただし、変更の際には定款変更が必要になりますので、定款に直接金額を記載することはあまりありません。定款に定めがない場合は株主総会の決議で決めることになります。
株主総会に関する事項
株主総会の招集時期や、誰が招集するか、議長は誰か、についてあらかじめて決めておくことができます。
株式に関する事項
名義書換手続きや株式取扱事務について決めることができます。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:会社の定款の任意的記載事項について解説します
定款変更に必要な手続き
定款に記載されている内容を変更するには株主総会での決議が必要になります。
定款は会社の規則を定め、設立時に公証人からその内容について認証を受けたものなので、勝手に記載内容を変更することはできません。定款を変更するには、株式会社の最高意思決定機関である株主総会での特別決議が必要となり、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られれば可決します。
定款内容の変更はさまざまなタイミングで発生しますが、そのたびに株主総会での特別決議が必要になります。定款変更のたびに招集していたのでは大変ですので、可能である限り一度にまとめた方が効率的です。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:定款を変更する場合は株主総会での決議が必要です
定款変更の際に登記申請が必要な事項がある
定款の記載内容に変更が生じたらすべて登記申請が必要なのですか?と聞かれることがあります。
回答としては「すべての変更において必要ではないが、登記事項に変更が生じる場合は変更登記が必要となる」ということになります。
どの事項を変更するときに登記申請が必要かを正確に判断するのが難しい場合には、専門家に事前に確認するようにしましょう。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:定款の記載事項のうち、変更時に登記申請が必要な事項について解説します
.png?w=500&h=109)
オフィス移転(本店移転)時の定款変更
会社規模の拡大や縮小など、さまざまな要因により発生するオフィス移転ですが、オフィスを移転する際に定款内の本店所在地を変更する場合は株主総会の決議が必要となります。また、変更登記申請も必要です。
変更登記申請には期限が設けられていますので、期間内に手続きを済ませましょう。
本店移転後2週間以内に申請する必要があります。この期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が過料を受ける可能性がありますので、必ず期限内に申請するようにしましょう
ただし、定款内の住所の記載方式は、番地まで正確に記載する場合と、「東京都○○区」と番地まで記載しない方法があります。最小行政区画までを記載している場合には、移転先住所によっては定款の変更は不要になります。(同じ市区村町内で移転する場合)ただし、本店移転の登記申請は必要なので注意しましょう。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:オフィス移転時の定款変更と本店移転登記について解説します
社名変更の定款変更
もちろんですが、その会社の商号(社名)も定款に記載されることで効力が生じます。
以下は法務局のWebサイトで配布されている、株式会社の設立登記申請書内の定款部分のサンプルですが、ご覧のとおり定款の一番最初に社名が記載されることが多いです。当たり前過ぎて忘れてしまいそうですね。

もし、会社を設立して以降、社名(商号)を変更する場合、厳密には「株主総会で定款に記載されている商号の変更を決議」し、その変更を登記申請することで登記簿に反映されるというプロセスになるのです。
社名変更というと、印象としてはかなり珍しいことのように感じますが、1文字だけの変更でもこれら手続きは必要になりますので、いざ必要になったときにあわてないようにしておきましょう。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:社名変更時の定款変更と商号変更登記について解説します
会社の事業目的を変更するときの定款変更
定款内の「絶対的記載事項」という項目があり、会社の事業目的はその中に含まれます。定款内の目的を変更するには株主総会での決議および登記申請することで登記簿に反映されます。
※記載イメージとしては、上記の定款サンプル内、第2条をご参考ください。
事業目的の内容に着目するケースは多くはありませんが、融資や出資などの資金調達の際や、許認可や補助金、助成金の申請時に提出する登記簿謄本(履歴事項全部証明書)においてチェックされることがあります。
例えば資金調達しようとしている事業が目的には含まれていなかったり、ある領域の補助金を申請するにはそぐわない目的になっている、といったことがないようメンテナンスを意識しましょう。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:事業目的を変更する場合の定款変更と目的変更登記について解説します
.png?w=500&h=109)
資本金や株式に関する定款変更
株式会社が発行できる株式数は「発行可能株式総数」として、会社設立の際に作成する定款の中で定められています。
この発行可能株式総数は、絶対的な発行上限数が決まっているわけでなく、会社ごとに定められます。一度決めた上限を増やすことも可能ですが、原則、株主総会の決議が必要になります。
もし、発行可能株式総数を超えて発行が必要な場合は、定款を変更するための株主総会の決議と新しい発行可能株式総数を登記簿に反映する必要があります。ただし実際には、増資などで株式数を増やそうとするタイミングで発行可能株式総数が足りないことがわかるケースが多いでしょう。
登記の手続き上も募集株式発行と発行可能株式総数は同時に行うことができます。募集株式の発行により発行済株式の総数が発行可能株式総数を超えてしまう場合は、同時に発行可能株式総数の変更を行いましょう。
詳しくはこちらの記事もご参考ください。
関連記事:発行可能株式総数を変更する場合の定款変更と募集株式の発行登記について解説します
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
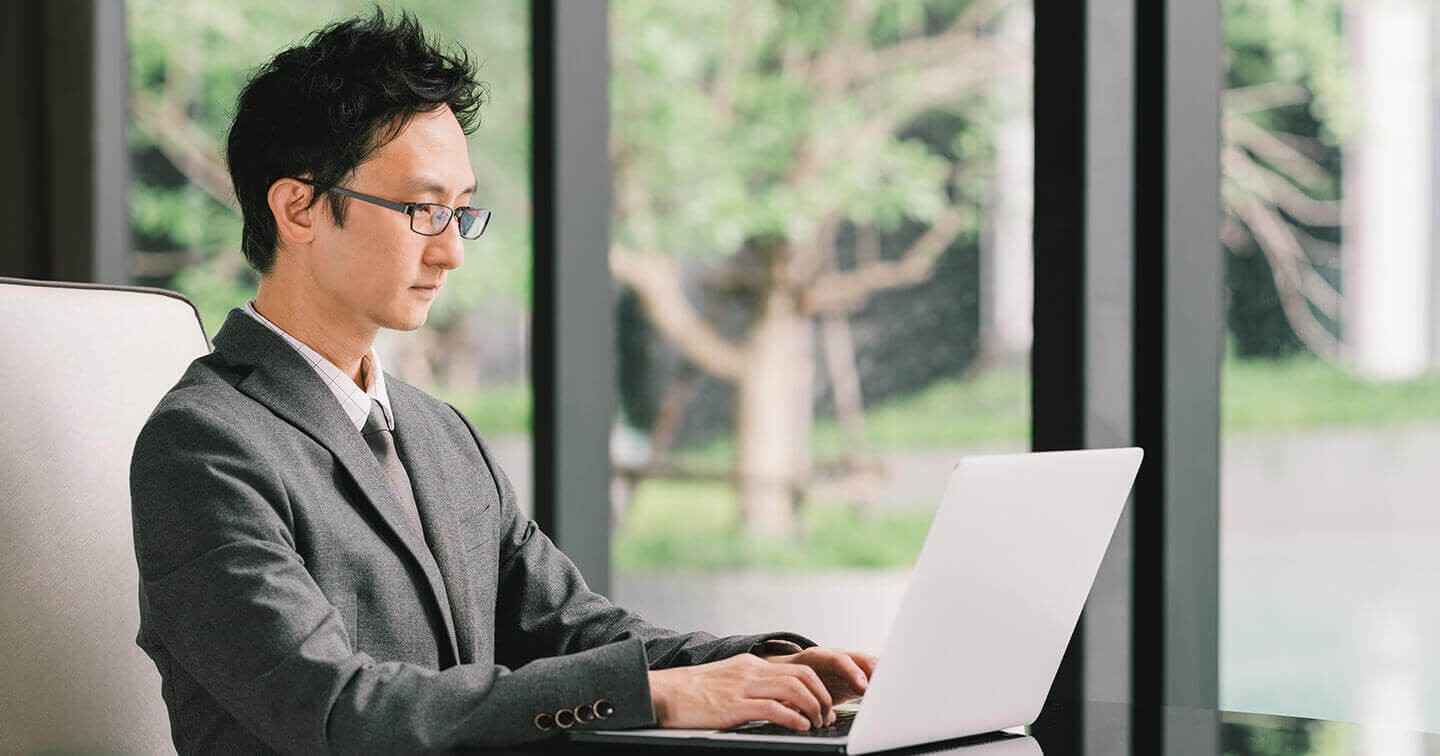
.png?w=500&h=109)



.jpg)



