商号(会社名)の変更登記申請は自分でカンタンにできます
この記事をお読みの方の中には、屋号を変更しようか、会社名を変更しようか検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら変更内容を入力するだけで商号変更登記に必要な登記申請書や株主総会議事録などの必要書類をWebでカンタンに作成できます。
⇒GVA 法人登記の詳細はこちら
商号変更登記についてはこちらの記事でも解説しています
関連記事:商号変更(社名変更)とは?登記申請の手続き方法を解説
関連記事:商号変更(社名変更)登記における登記すべき事項の書き方
屋号とは?
個人事業主が自分のお店や事業につける名前です。商業活動をする際に識別をしてもらうために、何らかの名称を使うことがあります。それが「屋号」です。
たとえば、塾であれば「●●塾」「●●アカデミー」などの名称を利用したりしますし、レストランであれば店に名前をつけることがほとんどです。個人名でやりとりするのに比べると取引先を識別しやすくなります。
商号とは?
法人の名前を示す用語として、法人名・会社名(企業名)・商号などがあります。
商号は、法人や会社が法律上登記する際に使う名前です。法人や会社は、社員やオーナーが変わっても継続して事業を行うことができるため、その団体の名前を法律的に登録します。たとえば、株式会社であれば、「株式会社○○」といった名前が商号になります。
この中で、会社法上の用語として正確に法人の名称を指すものは「商号」とされており、本稿では法人を指す名称については「商号」で統一します。(会社法第6条)
事業所名とは?
事業所名とは、企業や団体が複数の拠点を持っている場合、それぞれの拠点を区別するために使われる名称のことをいいます。
「○○事務所」「○○支店」など規模が大きい事業所によく使われます。
屋号と商号の違いは?
屋号は個人事業主が自分のお店につける名前であり、商号は法人や会社が法律的に登記する際の名前です。
会社名と店舗名って同じ?
一見同じように見える会社名と店舗名。店舗名は、会社が運営する店舗ごとに付けられる名称のことを言います。
会社名と店舗名が同じ例
会社名:ファミリーマート株式会社
店舗名:ファミリーマート
会社名:吉野家株式会社
店舗名:吉野家
会社名と店舗名が違う例
会社名:株式会社セブン&アイ・ホールディングス
店舗名:セブンイレブン、イトーヨーカドー
会社名:株式会社ファーストリテイリング
店舗名:ユニクロ、GU
事業所と商号の違いは?
「事業所」も「商号」もどちらも企業や事業団体の名称に関する言葉ですが、先ほどのように意味の違いがあります。
事業所名は、企業や団体が複数の拠点を持っている場合、それぞれ区別するために使用されてるものである一方、商号は法人が公式に登録している名称のことを言います。
会社名:ファミリーマート株式会社
事業所名:ファミリーマート 代々木〇〇店
会社名:吉野家株式会社
事業所名:吉野家新宿○○店
法人名と会社名の意味は何?
商号・屋号のほかにも会社名・法人名があります。
たくさんの名称があり、分からなくなってしまう方もいるかと思いますので、屋号についての説明に入る前に、法人名と会社名にも触れていきましょう。
「法人名」は、企業や団体が法律上で個別に登録する名前です。企業や学校、病院などが法人にあたります。
一方、「会社名」は、法人の中でも、特に「会社」として組織されたものの名前です。
例えば、「●●株式会社」や「●●合同会社」「●●有限会社」などが会社名の例です。
法人名と会社名の違いは?
法人名は企業や団体が法律上に登録する名前です。一方、会社名はその中でも「会社」として組織された企業の名前で、複数の人がお金を出し合って事業を行う組織を表します。両方とも法律的な意味がある名前であることは共通しています。
事業者名とは?
事業者名は事業を行う法人(企業)だけではなく個人事業を含めた名称全般のことを指します。
商号・屋号、個人の場合は屋号や屋号と氏名の組み合わせなど、事業を運営する際に使用される名前を含みます。
屋号と事業者名の違いは?
法人の場合は商号や屋号、個人事業主の場合は屋号や屋号と氏名の組合せなど、事業を運営する際に使用される名前を含みます。
法人企業の場合は会社名と事業者名は同じになりますが、
個人事業主の場合は事業者名として個人の名前を含むことがあり下記のような場合があります。
個人事業主の事業者名の例…GVA TECH GVA太郎(屋号+氏名の組合せ)
仮に一人社長だったとしても法人化されているのであれば、
『法人』になるため『法人名』が掲載されます。
屋号とは?個人事業主が商業主体として契約をする際の名称
では屋号と商号の端的な違いですが、屋号は個人事業主が商業主体として契約をする際の名称として利用するもので、商号は法人の名称です。
個人が個人事業主として商業活動をするにあたって、個人で契約をすることもできますが、商業活動をする際に識別をしてもらうために、何らかの名称を使うことがあります。それが「屋号」です。
一方で法人は、ここの自然人とは離れた法的主体として存在するので、その識別のために名称を付けなければなりません。その名称のことを商号と呼びます。
「屋号」の特徴
では屋号について詳しく見てみましょう
屋号とは個人事業主が名乗る事業の名称
上記でも触れていますが、屋号は個人事業主が商業主体として契約をする際に利用する名称です。
個人が個人事業主として活動する場合でも、契約をした場合の地位は、他の生活に必要な契約と異なることなく、契約をした本人に帰属します。
しかし、商業主体である以上、何らかの名称をつかって商売をします。
これは、商売上の契約であると相手にとっては、どのようなことをしているかわらかない人よりも、何をしているか・商売をしている人かどうか識別が可能な屋号の方が取引しやすいという機能があります。
個人事業主で屋号をつける場合には、預金名義人として本名のほかに屋号を付すことも可能になりますので、相手の信用を得られる可能性があります。
屋号は必ず利用しなければならないものではない
この屋号ですが、利用するかどうかは個人の自由です。
上述したように、店舗を構えるような業態である場合には、何等かの屋号を定めることが望ましいといえます。
しかし、個人の名前で仕事をする、作曲家・ライター・フリーランスのプログラマー・デザイナーといった職種の人であれば、屋号がなくても仕事をすることは可能です。
また、たとえばweb上では屋号をつけてインターネットで販売を行い、個人ではフリーランスのフォトグラファーとして活動するのであれば、前者で活動するときのみ屋号を利用してもかまいません。
屋号を使う場合のルール
屋号を使う場合のルールについて確認しましょう。
実は屋号には決まったルールはない
いきなり逆のことを言っていますが、実は屋号には特に決まったルールはありません。
そのため、ひらがな・カタカナ・英語でもかまいません。
極端な話、アラビア文字のような一般的に判読ができないものでも良いです。
ただ、屋号としてつける以上、適切な名称をつけないと、せっかく信頼を得るために行うのが台無しになってしまうことは言うまでもありません。
法律で名称をつけることが禁止されているものに注意
ただし、会社でもないのに、会社であると誤認をするような名称をつけることは、会社法第7条で禁止されています。
また銀行ではないのに銀行の名称を使用することは銀行法第6条で禁止されています。
これらの違反には刑事罰が付されていますので、絶対に違反をしないようにしましょう。
商号とは
会社のように、個人とは別人格の法人を作る際に、その法人を識別するためにつけるのが商号です。
法人を識別するために使うのが商号ですので、会社を設立する際に、必ず定めなければなりません。
会社の設立の際に作成する定款には商号が必ず記載されなければならず(会社法第27条3号)、会社設立の登記をする際には、商号も必ず登記されます(会社法第911条)。
商号を変更したら商号変更登記申請が必要です
商号変更は比較的簡単な変更登記申請ですが、GVA 法人登記なら最短7分で書類が自動作成、登録免許税額分の収入印紙も同時購入可能です。郵送申請もサポートしていますので、ぜひご利用ください。
GVA 法人登記サービスサイトはこちら
商号に関するルール
屋号と異なり、商号には法律で規定されたルールがいくつかあります。
設立する会社の種類が商号に含まれる
商号についての最初のルールは、設立する会社の種類が商号に含まれるということです。
例えば、株式会社を設立するのであれば商号の中に「株式会社」を、合同会社を設立するのであれば「合同会社」を使います(会社法第6条第2項)。
いわゆる「前株・後株」と言われるものでですが、会社種類は商号の前でも後でもどちらでもかまいません。
会社の種類によって、代表者の責任の範囲が異なったりしますので、これを混同させないためにも、他の種類の会社であるという誤認をさせる文字をつかってはならないとされています(会社法第6条第3項)。
不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある商号の利用禁止
会社を長年続けていると、その会社の名前がついていること自体に価値があることがあります。
他の会社が似たような名前を使って商売を始めることは、不公正ですし、その名前を使って粗悪品を売り出すようなことにもつながりかねません。
そのため会社法第8条で、不正の目的をもって他の会社であると誤認される恐れのある名称・商号を利用してはならないとしています。
同一の所在場所における同一商号の登記の禁止
ある商号が同一の所在場所においてすでに使われている場合には、その商号を利用することができません(商業登記法27条)。
上述したように、不正な目的で利用する場合もそうですが、同じような商号で違う業態の店舗を近くで営業する場合には、新しい業態に乗り出したという勘違いに繋がりかねません。
そのため、同一の所在場所における同一商号の登記は禁止されています(商業登記法第27条)。
このにおける同一の所在場所とは、番地まで一致するような所在場所を意味しています。
将来法人を作る場合には屋号にも注意しましょう
とりあえず個人事業主として開業を始めて、事業が大きくなったら会社を設立する、と考える方も多いでしょう。
この場合に、個人事業主として利用した屋号について、そのまま商号にしたいと考えます。
しかし、上述したように屋号は法的な権利・義務がないので気軽に選定しやすいのですが、商号についてはたくさんの制約があります。
そのため、いずれ法人化をすることを考えているのであれば、屋号の選定にあたっても慎重に行うようにしましょう。
【最短7分】株式・合同会社の商号(会社名)変更登記に必要な書類をカンタン作成できます
会社名を変更した際に必要になる商号変更登記では、自分で手続きするにも、
「どの書類を用意したらいいのかわからない」
「書類にどの印鑑を押印をしたら良いのかわからなかない」
など登記手続きに関する知識がないと調べるだけでも何時間もかかってしまうものです。
GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで株式・合同会社の商号(会社名)変更登記に必要な書類を最短7分、12,000円(税抜)で作成できます。
さらに、GVA 法人登記で登記手続きしていただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。登記申請するまでに必要な書類についてすべてまとめておりますので、流れの通りに押印して書類の製版をするだけで手続きを終えることができます。
株式、合同会社それぞれの商号変更に対応し、印刷や製本をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入いただけます。
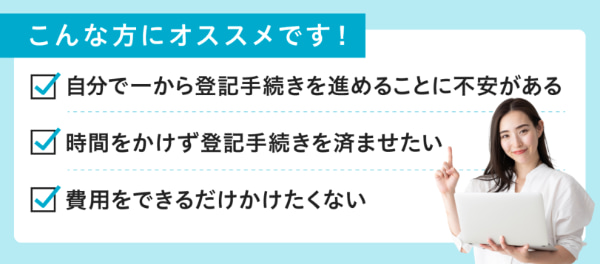
ステップに沿って入力するだけで株式・合同会社の商号変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
商号変更登記についての詳細はこちら
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる株式・合同会社の商号変更登記の書類
※申請状況により、一部作成されない書類がございます。
〈株式会社〉
〈合同会社〉
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\商号変更登記するなら/


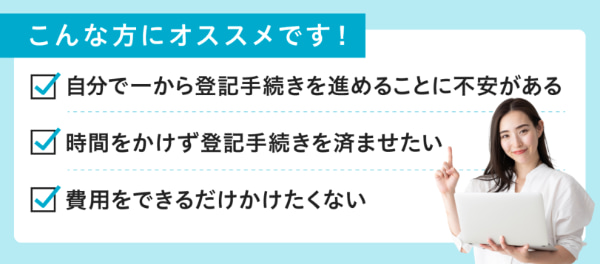
.jpg)



