「一人社長だから補助金は関係ない」「従業員がいないから申請できない」と思っていませんか?
個人事業主や従業員ゼロの法人(一人社長)こそ活用すべき、強力な国の支援策が豊富に存在します。
特に、IT導入や販路開拓、設備投資など、事業の成長に欠かせない取り組みにかかるコストに対して、国から最大で数分の2、数百万円〜数千万円もの補助を受けられる可能性があります。
本記事では、多忙な一人社長が手間をかけずに申請できる可能性が高く、事業規模拡大に直結する厳選した8つのおすすめ補助金・助成金を徹底解説します。
一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金10選

- 「GVA 補助金診断」で補助金・助成金を今すぐ無料診断
- 一人社長が補助金・助成金を申請する際に知っておきたいこと
- 従業員ゼロでも補助を受けられる
- 一人社長でも大丈夫!申請手続きの負担を軽減する方法
- 申請できる経費・できない経費の線引き
- 採用しない予定でも対象となる補助金は多数ある
- 一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金10選
- IT導入補助金
- 中小企業省力化投資補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- ものづくり補助金
- 新事業創出補助金(旧事業再構築補助金)
- 事業承継・M&A補助金
- 省エネ・非化石転換補助金
- 新事業進出補助金(旧:事業再構築補助金の代替)
- 省力化投資補助金(カタログ注文型)
- 地方自治体の独自補助金(横浜市・東京都・大阪市など全国)
- 一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金に関するよくある質問
- 一人社長でも持続化給付金はもらえる?
- 一人社長の給料は経費になる?
- 補助金・助成金の申請に必要な登記変更や登記簿謄本が必要になっても安心
- まとめ
「GVA 補助金診断」で補助金・助成金を今すぐ無料診断
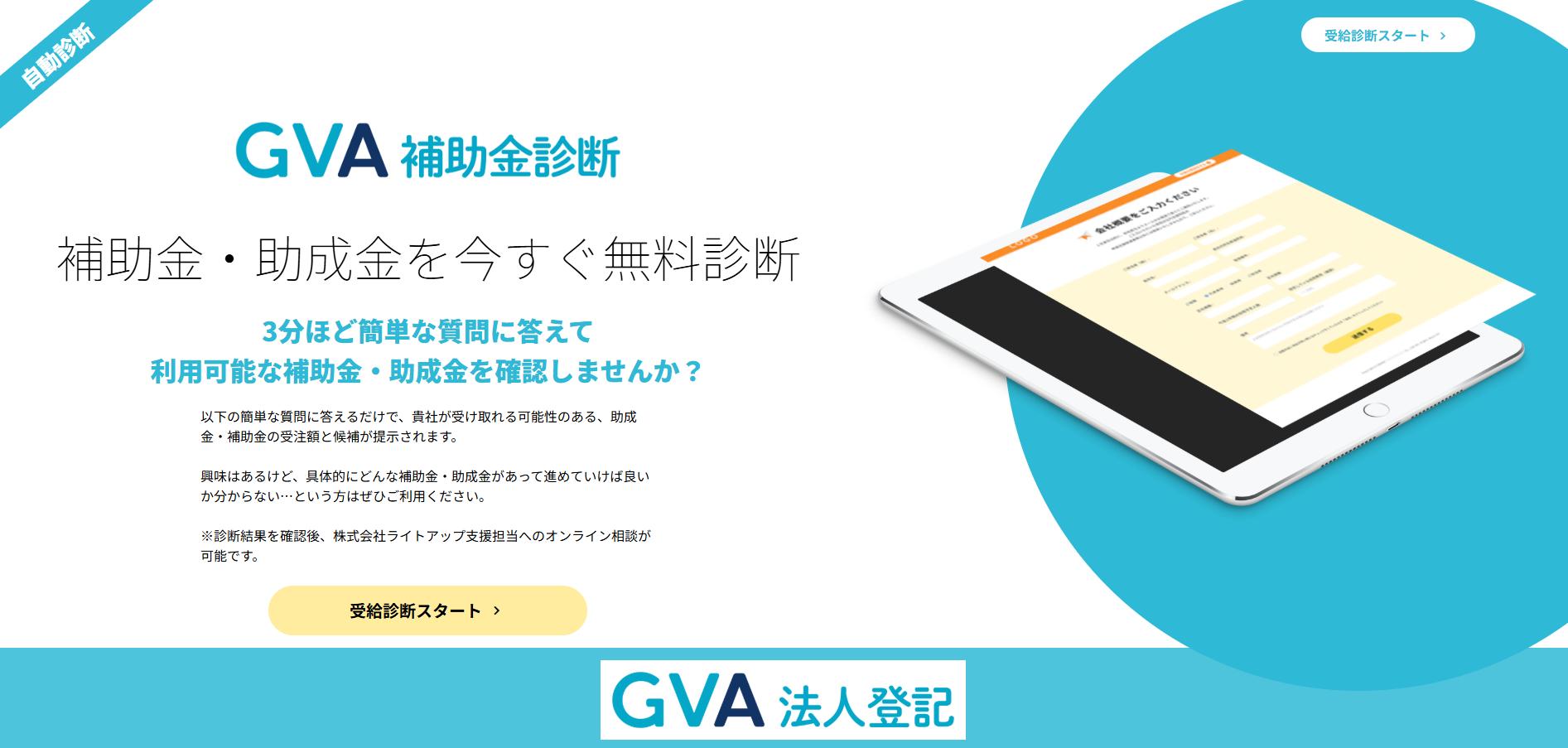
GVA 補助金診断なら3分ほど簡単な質問に答えて利用可能な補助金・助成金を確認できます。
簡単な質問に答えるだけで、貴社が受け取れる可能性のある、助成金・補助金の受注額と候補が提示されます。
興味はあるけど、具体的にどんな補助金・助成金があって進めていけば良いか分からない…という方はぜひご利用ください。
※診断結果を確認後、株式会社ライトアップ支援担当へのオンライン相談が可能です。
>>GVA 補助金診断はこちら
一人社長が補助金・助成金を申請する際に知っておきたいこと
一人社長が補助金・助成金を申請する際に知っておきたいことを基礎知識として解説します。
従業員ゼロでも補助を受けられる
「従業員がいないと補助金や助成金を申請できないのでは?」と考える方も多いでしょう。
結論から言うと、従業員ゼロでも補助を受けられます。
多くの補助金は「小規模事業者」を主な対象としており、特に小規模事業者持続化補助金は従業員がいない一人社長(個人事業主を含む)がメインの対象です。
助成金の多くは雇用保険に加入している従業員がいることが前提ですが、補助金は雇用関係を問いません。
一人社長が狙うべきは主に経済産業省系の「補助金」です。
一人社長でも大丈夫!申請手続きの負担を軽減する方法
補助金の申請手続きは、比較的難易度が高いといえます。
特に事業計画書の作成には時間がかかりますが、行政書士などの専門家に依頼するか、商工会・商工会議所の無料相談を活用することで、負担を軽減できます。
申請できる経費・できない経費の線引き
公募要領で定められた「対象経費」のみが認められます。
ウェブサイト制作費、広告費、機器購入費、専門家への謝金などが対象経費になる可能性があります。
汎用性の高いもの(パソコン、タブレット、スマートフォン、乗用車など)は、原則として対象外とされるケースが多いです。
補助金で購入する機器は、補助事業の遂行に「専ら使用されるもの」である必要があります。
採用しない予定でも対象となる補助金は多数ある
一人社長の方が補助金・助成金を検討する際に最も気になるのは、「従業員ゼロで申請できるか」という点です。
結論として、採用の予定がなくても、多くの「補助金」は対象となります。
特に小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金など、事業の成長や設備投資を支援する経済産業省系の補助金がおすすめです。
一方で、雇用関係を目的とする助成金は基本的に対象外です。
一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金10選
一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金10選をおすすめする理由を交えて解説します。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際、その経費の一部を国が補助する制度です。
目的は、企業の業務効率化・生産性向上、およびDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進を支援することにあります。
一人社長にIT導入補助金をおすすめする理由
一人社長の方にIT導入補助金をおすすめする最大の理由は、事業効率の劇的な向上とそれに伴う人件費の削減にあります。
ITツールを導入することで、これまで手作業で行っていた経理、顧客管理、受発注といったバックオフィス業務を自動化・効率化できます。
これにより、社長ご自身がコア業務や事業成長のための戦略策定により多くの時間を割けるようになり、生産性の向上に直結します。
また、補助金がITツールの導入費用の一部をカバーしてくれるため、初期投資の負担を大幅に軽減できる点も、資金力が限られがちな一人社長にとって大きなメリットとなります。
コストを抑えつつ、競争力を高めるための強力な手段となるでしょう。
制度の概要
- 対象者: 原則として、日本国内の中小企業および小規模事業者(個人事業主も含む)。業種や資本金、従業員数などの要件があります。
- 対象経費: ITツールの導入費用やサービス利用料(最大2年分)。具体的には、ソフトウェアの購入・利用料、クラウドサービスの利用料、場合によってはハードウェア(PC、タブレット、レジ・券売機など)も対象に含まれます(申請枠による)。
- 補助金額・補助率: 申請する枠や類型によって異なります。例えば、通常枠では最大450万円、補助率は1/2以内など、様々な要件が設定されています。
- 返済義務: 原則として返済義務はありませんが、導入後に策定した目標が未達成だった場合や報告を怠った場合などは、返還が必要になることがあります。
主な申請枠(2025年時点)
複数年度で実施されており、毎年内容が見直されますが、主な枠組みは以下の通りです。
- 通常枠: 幅広い業種の業務効率化や生産性向上を目的としたITツール導入を支援。
- インボイス枠: インボイス制度への対応を目的としたITツール導入を支援。
- セキュリティ対策推進枠: サイバーセキュリティ対策の強化を目的としたサービス導入を支援。
- 複数社連携IT導入枠: 複数の中小企業が連携してITツールを導入する地域DXの取り組みなどを支援。
この補助金を活用することで、IT導入にかかるコストを大幅に削減し、企業の競争力強化につなげることができます。
中小企業省力化投資補助金
「中小企業省力化投資補助金」は、中小企業の人手不足解消を目的として、IoT、ロボット等の省力化に効果がある汎用製品や設備・システムの導入費用の一部を国が補助する制度です。
生産性向上や売上拡大、賃上げにつなげることを目的としています。
一人社長に中小企業省力化投資補助金をおすすめする理由
一人で事業を営む社長にとって、最も切実な課題の一つが業務負荷の集中です。
この補助金は、ロボットやIoT、システムなどの省力化製品の導入費用を国が支援してくれるため、金銭的な負担を軽減しながら、業務の一部を自動化・効率化できます 。
これにより、社長はルーティンワークから解放され、コア業務や戦略的な活動に時間とエネルギーを集中できるようになります。
特に、小規模事業者は補助率が高く設定されるケースが多く、投資対効果を得やすい点も魅力です。
労働生産性の向上は、売上拡大や事業の持続可能性に直結し、将来的な事業拡大の土台を築くための大きな一歩となるでしょう。
煩雑な業務を機械に任せることで、ワークライフバランスの改善にもつながる、まさに一人社長の強い味方と言える補助金です。
制度の主な特徴
- 目的: 人手不足に悩む中小企業の省力化投資を促進する。
- 対象: 中小企業等。
- 補助対象: あらかじめ事務局が選定した「製品カタログ」に登録された汎用製品(IoT、ロボット等)の導入費用(機械装置費、導入経費等)。
- 申請方法: 省力化製品の「販売事業者」が、省力化製品の導入と補助金申請・手続きをサポートする(共同申請)。
- 手続き: 申請手続きが簡易で、随時公募受付が行われているため、比較的スピーディーに導入が可能。
- 補助率・補助上限: 従業員数や型(一般型、カタログ型)によって異なりますが、補助率は1/3〜2/3、補助上限額は最大1億円(一般型)とされています。
2つの類型
主に以下の2つの類型があります。
- カタログ注文型: 「製品カタログ」に登録された汎用製品から選択し、簡易な手続きで申請できる。
- 一般型: オーダーメイド設備や個別の現場に合わせて組み合わせた設備・システムの導入も対象となり、補助上限額も大きい。
この補助金は、人手不足の解消や業務効率化を目指す中小企業にとって、設備投資を後押しする重要な支援策です。最新の情報や詳細な公募要領は、中小企業庁の公式サイトで確認できます。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を自ら策定し、地域の商工会・商工会議所の支援を受けながら行う、販路開拓や生産性向上を目的とした取り組みを支援する国の補助金制度です。
一人社長に小規模事業者持続化補助金をおすすめする理由
一人社長に小規模事業者持続化補助金をおすすめする主な理由は、販路開拓や生産性向上のための経費を大幅に支援してもらえる点にあります。
この補助金は、ウェブサイト作成、チラシ制作、店舗改装といった集客力アップにつながる具体的な投資に利用できるため、リソースが限られる一人社長にとって、事業を次の段階へ進める大きな後押しとなります。
特に、最大50万円(補助率2/3)が支給される枠もあり、自己資金だけでは難しかった挑戦を可能にする強力なツールとなるからです。
制度の概要
- 目的: 地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図る。
- 対象者: 日本国内に所在する従業員が一定数以下の法人、個人事業主、特定非営利活動法人(NPO法人)など。具体的には、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は従業員5人以下、製造業その他は従業員20人以下などが要件となります。
- 支援内容: 経営計画に基づき実施する、新たな顧客獲得や売上向上につながる多様な経費(広告宣伝費、ECサイト構築費、店舗改装費、業務効率化のための設備導入費など)が対象となります。
- 補助上限額: 申請する枠(通常枠、創業型、共同・協業型など)や特例の有無によって異なり、例えば通常枠は50万円、創業型や災害支援枠は200万円が上限となる場合があります。
- 補助率: 原則として補助対象経費の2/3以内です。
特徴
- 計画策定支援: 申請にあたっては、商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成する必要があります。
- 採択審査: 要件を満たすすべての申請者が採択されるわけではなく、外部有識者等による審査を経て、評価の高い案件から順に採択されます。
詳細は、中小企業庁や全国商工会連合会、東京商工会議所などの公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。
ものづくり補助金
「ものづくり補助金」とは、中小企業・小規模事業者等が、生産性向上や持続的な賃上げを実現できるよう、革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する国の補助金制度です。
正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といいます。
一人社長にものづくり補助金をおすすめする理由
一人社長にものづくり補助金をおすすめする理由は、事業拡大の初期投資を大幅に軽減できるためです。
特に製造業を営む個人事業主にとって、新しい設備やシステムの導入は多額の費用がかかりますが、この補助金を利用することで、その費用の大半をカバーできます。
これにより、自己資金の負担を抑えつつ、生産性の向上や新分野への進出を早期に実現できるため、競争力を高め、将来的な収益の柱を確立するための大きな後押しとなります。
また、補助金獲得のプロセス自体が事業計画を見直す良い機会にもなります。
目的
働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入といった、今後複数年にわたり直面する制度変更等に対応するため、中小企業・小規模事業者の生産性向上を図ることを目的としています。
対象者
中小企業・小規模事業者等(個人事業主も含む)が対象です。
補助対象
新しい製品やサービスを開発する際などに必要となる設備投資(機械装置・システム構築費など)が主な対象です。単なる設備の入れ替えではなく、革新的な取り組みが求められます。
主なメリット
- 返還が不要な補助金であるため、新たな事業に挑戦する際のリスクを軽減できます。
- 自己資金や融資だけでは難しかった規模の大きい新規事業や設備投資が可能になります。
この補助金を活用するには、事業終了後3~5年で「付加価値額」や「給与支給総額」の一定以上の増加を目指す事業計画の策定・実行が要件となります。
新事業創出補助金(旧事業再構築補助金)
「新事業創出補助金」は、正式名称を「中小企業新事業進出促進事業補助金」といい、事業再構築補助金の後継として2025年度(令和7年度)に新設された国の補助金制度です。
この補助金は、中小企業が既存事業で培ったノウハウを活かしつつ、既存事業とは異なる新たな市場・高付加価値事業へ進出するために必要な設備投資費用などを支援することを目的としています。
一人社長に新事業創出補助金(旧事業再構築補助金)をおすすめする理由
一人社長に新事業創出補助金(旧事業再構築補助金)をおすすめするのは、新たな事業への転換や進出を検討する際に、高額な設備投資やシステム導入の費用を賄える点にあります。
この補助金は補助上限額が比較的高額に設定されており、小規模事業者でも補助率が優遇される枠があるため、自己資金だけでは困難な大胆な事業再構築へのチャレンジを可能にします。
これにより、一人社長であっても事業のスケールアップや多角化を効率的に進めるための大きな後押しとなるでしょう。
概要
- 目的: 中小企業の人手不足や賃上げといった経営課題を克服し、事業の成長を促進するため、既存事業の延長線上ではない全く新しい挑戦を支援する。
- 対象者: 国内に本社がある中小企業者等および中堅企業者等(個人事業主も含む)。
- 補助対象事業: 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画。
- 製品等の新規性: 中小企業にとって初めて製造・提供する製品やサービスであること。
- 市場の新規性: これまで取引のなかった新たな顧客層や業界を対象とすること。
- 新事業売上高要件: 新事業による売上が、申請時の売上高の10%以上になる見込みがあること。
- 補助対象経費: 建物費、構築物費、機械装置・システム構築費、外注費、広告宣伝費など幅広い費用が対象。
- 補助額・補助率: 従業員数に応じて異なり、最大で7,000万円(大幅な賃上げ要件を満たす場合は最大9,000万円)。
- 補助率は原則1/2(小規模事業者や賃上げ要件を満たす場合は2/3)。
- 主な要件: 事業計画期間終了後3~5年で、事業場内最低賃金が毎年地域別最低賃金より+30円以上となることなどが求められる。
「事業再構築補助金」との主な違い
「事業再構築補助金」がコロナ禍の影響を受けた事業者への支援に重点を置いていたのに対し、「新事業創出補助金」は、より積極的な新規性や市場性が高く評価される成長戦略に焦点を当てています。
また、「新事業に該当しない」例が明確化されるなど、要件がより具体的に定められています。
事業承継・M&A補助金
「事業承継・M&A補助金」は、中小企業の生産性向上や事業継続を目的として、事業承継やM&A(合併・買収)に伴う様々な経費を支援する国の補助金制度です。
正式名称は「事業承継・引継ぎ補助金」でしたが、2025年度からは「事業承継・M&A補助金」に名称変更されています。
一人社長に事業承継・M&A補助金をおすすめする理由
一人社長にとって、事業承継・M&A補助金の活用は、廃業の回避や事業の持続的な成長を実現する上で極めて有益です。
この補助金は、M&Aや事業承継にかかる専門家費用、システム導入費用などを支援することで、後継者不在という深刻な問題を持つ小規模事業者の円滑な引継ぎを力強く後押しします。
これにより、経営資源を次世代に繋ぎ、地域経済の活性化にも貢献できるのです。
制度の概要
この補助金は、主に以下のような取り組みを行う中小企業や個人事業主を対象としています。
- 事業承継をきっかけとした新しい取り組み: 後継者が事業を引き継いだ後、経営革新や新規事業展開のために行う設備投資や販路開拓など。
- M&Aの実施: 事業の譲渡(売り手)または譲り受け(買い手)に伴う専門家への費用支払いなど。
- M&A後の経営統合(PMI): M&A成立後の経営統合を円滑に進めるための設備投資やシステム導入など。
- 廃業・再チャレンジ: 事業承継やM&Aと併せて、既存事業の廃業や新たな挑戦を行う際の費用支援。
主な申請枠(2025年度 第13次公募時点)
公募時期によって枠組みは変動しますが、主な類型として以下の4つがあります。
- 事業承継促進枠: 後継者による事業の再構築や新規展開のための費用を支援。補助上限額は最大1,000万円(一定の賃上げ要件を満たした場合)。
- 専門家活用枠: M&A仲介業者や弁護士、公認会計士などの専門家に支払う費用を支援。
- PMI推進枠: M&A後の円滑な経営統合プロセス(Post-Merger Integration)に必要な費用を支援。
- 廃業・再チャレンジ枠: 廃業費用(在庫廃棄費、解体費など)を支援。
対象経費の例
申請枠によって異なりますが、一般的に以下のような費用が対象となります。
- 設備費
- 店舗・事務所の改築工事費
- 専門家への報酬・費用
- M&A関連のデュー・ディリジェンス(資産査定)費用
- 広告宣伝費、マーケティング調査費
- 廃業に係る費用(廃業・再チャレンジ枠)
詳細な要件や最新の公募情報は、事業承継・M&A補助金の公式サイトで確認できます。
省エネ・非化石転換補助金
「省エネ・非化石転換補助金」は、経済産業省が推進する「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」の通称です。
この補助金は、工場や事業場などにおける大幅な省エネルギー化や、非化石エネルギーへの転換(電化・脱炭素燃料への転換)を目的とした設備投資を支援するものです。
一人社長に省エネ・非化石転換補助金をおすすめする理由
一人社長に省エネ・非化石転換補助金をおすすめする理由は、返済不要の資金調達で、リスクを抑えつつ事業拡大に必要な設備投資ができる点にあります。
特に小規模事業者は補助率の優遇措置が適用されることが多く、例えば一般型では補助上限額が高額な上、補助率が優遇され自己資金の負担を大きく軽減できます。
これにより、限られたリソースで生産性向上や競争力強化につながる高効率な機械装置やシステムを導入しやすくなります。
ランニングコストの削減にも直結するため、一人社長の安定した経営基盤構築に大きく貢献します。
目的と概要
エネルギー効率の向上と持続可能な社会の実現を促進するため、事業者が行う以下の取り組み費用の一部を補助します。
- 省エネ設備の導入: エネルギー消費効率の高い最新設備への更新。
- 非化石転換: 化石燃料を使用する機器から、電気や水素などの低炭素な燃料を使用する機器への転換。
主な事業区分
この補助金は主に以下の4つの事業区分(I~IV型)で構成されています。
- (I)工場・事業場型: 工場や事業場全体で包括的な省エネ・非化石転換の取り組みを支援。
- (II)電化・脱炭素燃転型: 電化や、より低炭素な燃料への転換を伴う特定の機器への更新を支援。
- (III)設備単位型: SII(環境共創イニシアチブ)が定めた基準を満たす特定の高効率設備への更新を支援。
- (IV)エネルギーマネジメントシステム導入事業: エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入を支援。
補助対象者
原則として、国内で事業活動を行う法人や個人事業主などが対象となります。補助率や補助上限額は事業区分や企業の規模(中小企業、大企業)によって異なります(例:補助率1/2以内、補助上限3億円など)。
この補助金は公募期間が設定されており、予算額に達すると期間内でも受付を終了する場合があるため、申請には事前の準備と迅速な対応が重要です。
新事業進出補助金(旧:事業再構築補助金の代替)
「新事業進出補助金」は、2025年(令和7年度)から開始された、事業再構築補助金の後継となる中小企業向けの新たな補助金制度です。
中小企業が既存事業と異なる新市場・高付加価値事業へ進出する際にかかる設備投資費用などを支援することを目的としています。
一人社長に新事業進出補助金(旧:事業再構築補助金の代替)をおすすめする理由
新事業進出補助金は、一人社長や小規模事業者でも補助上限額2,500万円(特例適用で最大3,000万円)と高額な支援を受けられる点が最大の魅力です。
事業の多角化や新しい分野への進出といった大きなチャレンジに、返済不要の資金を活用することで、経営リスクを大幅に軽減しつつ、大胆な設備投資や販路開拓を可能にします。
この補助金は、小規模ながらも高い成長意欲を持つ一人社長の事業拡大を強力に後押しするために設計されています。
制度概要
- 目的: 中小企業が新規事業へ挑戦し、企業の成長・拡大、生産性向上、および賃上げを目指す取り組みを支援する。
- 対象: 既存事業とは異なる新たな製品・サービスを開発し、新たな顧客層・業界を対象とする「新事業進出」を行う中小企業。
- 補助対象経費: 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、広告宣伝費、販売促進費などが含まれます。
- 補助率: 原則1/2(一部、大幅賃上げを行う事業者への特例あり)。
- 補助上限額: 従業員数に応じて異なり、最大で9,000万円(特例適用後)の大型補助金です。
- 主な要件:
- 付加価値額の年平均成長率+4.0%以上の増加。
- 給与支給総額の年平均成長率+2.5%以上の引き上げ。
- 補助事業終了後3〜5年間、事業所の最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上高い水準となること(返還要件あり)。
事業再構築補助金との違い
事業再構築補助金と比較して、新事業進出補助金は以下の点で違いがあります。
- より明確に「新事業」への進出(製品や市場の新規性)が求められ、既存事業の延長線上の取り組みは対象外となるケースが明確化されています。
- 賃上げに関する要件がより具体的かつ厳格に設定されています。
- 目的や対象経費において明確な違いがあり、申請を検討する際には公募要領を確認することが重要です。
省力化投資補助金(カタログ注文型)
「省力化投資補助金(カタログ注文型)」は、人手不足に悩む中小企業・小規模事業者を対象に、業務効率化や生産性向上を目的とした省力化設備・システムの導入を支援する国の補助金制度です。
主な特徴は、国が事前に選定し「製品カタログ」に掲載された汎用的な製品から、事業者が自社の課題に合わせて選択・導入できる点にあります。
一人社長に省力化投資補助金(カタログ注文型)をおすすめする理由
一人社長に省力化投資補助金(カタログ注文型)をおすすめする理由は、手続きの簡便さと即効性の高い効果にあります。
この補助金は、あらかじめ登録された汎用性の高い省力化製品をカタログから選ぶだけで済むため、複雑な事業計画の策定が不要で、申請にかかる手間や時間が大幅に削減されます。
一人で全てをこなす社長にとって、この事務負担の軽減は大きなメリットです。
また、導入製品が人手不足解消に効果的なIoTやロボットなどに絞られているため、迅速な導入と生産性向上の実現が見込めます。
常勤従業員がいない事業者でも応募可能(規定の証憑提出が必要)となり、補助上限額も従業員5名以下で200万円(300万円)と設定されており、小規模事業者が取り組みやすい設計となっています。
制度の概要
- 目的: 中小企業の人手不足解消、生産性向上、および賃上げの促進。
- 対象者: 中小企業・小規模事業者等。
- 補助対象: 事前に登録された省力化製品(自動販売機、セルフレジ、清掃ロボット、特定のIoT機器など)の本体価格と、設置・導入設定費用の一部。
- 補助率: 原則として補助対象経費の1/2以内。
- 補助上限額: 従業員数に応じて異なり、200万円から1,500万円(賃上げ要件を満たすことで増額可能)。
主なメリット
- 手続きが簡易: 申請手続きが比較的簡素化されており、申請から交付決定まで最短1ヶ月程度と迅速です。
- 製品選定が容易: 国が性能等を審査済みの製品カタログから選ぶため、設備選びの負担が軽減されます。
- 販売事業者のサポート: 対象製品の販売事業者が、導入計画の策定や補助金の申請手続きをサポート(共同申請)するため、事業者の手間が省けます。
- 随時公募: 公募が随時行われているため、事業者のタイミングに合わせて申請が可能です。
「一般型」と比較して、カタログ注文型は汎用的な製品を迅速に導入したい場合に適しています。
地方自治体の独自補助金(横浜市・東京都・大阪市など全国)
一人社長でも申請できるおすすめの補助金・助成金を見つけるためには、まず国や地方自治体の公式ポータルサイトや相談窓口を活用することが重要です。
地方自治体独自の補助金・助成金は地域や時期によって内容が異なるため、以下の方法で効率的に情報を収集してください。
一人社長に地方自治体の独自補助金をおすすめする理由
一人社長に地方自治体の独自補助金をおすすめする理由は、その獲得のしやすさと事業へのインパクトの大きさにあります。
国や都道府県の補助金と比較して、独自の補助金は募集件数が少なく、地域経済の活性化や特定課題の解決を目的としているため、競合が少ない傾向があります。
一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金に関するよくある質問
一人社長でも申請できるおすすめ補助金・助成金に関するよくある質問に回答します。
一人社長でも持続化給付金はもらえる?
新型コロナウイルス対策として実施されていた本来の「持続化給付金」はすでに終了しているため、今から受け取ることはできません。
ただし、現在も実施されている「小規模事業者持続化補助金」であれば、一人社長(従業員ゼロの法人や個人事業主)でも要件を満たせば申請可能です。
一人社長の給料は経費になる?
一人社長の給料(役員報酬)は、原則として経費になりますが、定期同額給与などの税法上の要件を満たす必要があります。
不相当に高額な部分は経費として認められません。
また、補助金申請時には、役員報酬の額が審査対象となる場合があるため、申請する補助金の公募要領で人件費の扱いについて事前に確認することが重要です。
補助金・助成金の申請に必要な登記変更や登記簿謄本が必要になっても安心
補助金や助成金の申請における添付書類の代表格が法人の登記簿謄本(登記事項証明書)です。
書類の用意はもちろんですが、その内容にも注意が必要なことをご存知でしょうか?
- 補助金対象の自治体に本店や支店の登記が必要になる
- 補助金の対象となる事業目的が登記簿謄本内にも記載されていなかった
- 代表者や役員の住所変更時の登記を申請しておらず、古いままになっていた
このようなことがあれば、審査通過以前の問題ですし、慌てて登記申請したとしても補助金申請の締切に間に合わないという可能性があります。
今後補助金申請を検討している方は、現在の登記簿謄本の内容を確認して、必要なら時間に余裕をもって変更登記を申請しておきましょう。
GVA 法人登記なら、Web上から変更する情報を入力すれば書類を作成、法務局に行かずに自分で登記申請できます。
そして、登記簿謄本の取得ならGVA 登記簿取得がおすすめです。
メールアドレスだけで会員登録でき、使い慣れたクレジットカードで、数分の手続きで登記簿謄本の請求ができます。
まとめ
一人社長でも申請できるおすすめの補助金・助成金には、主に「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」などがあります。
これらの制度は、従業員がいない小規模事業者も対象としており、事業内容や目的に応じて活用できます。
まずは、ご自身の事業の目的(販路開拓か、IT導入か、設備投資か)に合わせて、補助金や助成金の活用を検討することをおすすめします。
最新の公募要領や締切は変更されることがあるため、常に公式ウェブサイトや専門家(商工会議所、税理士など)に確認することが重要です。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。