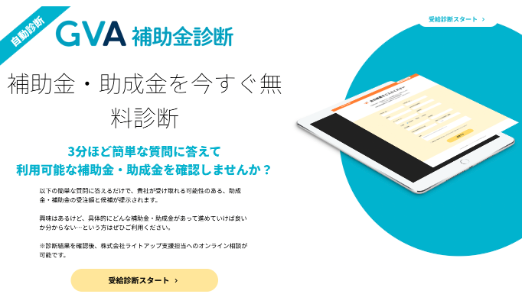設立間もない企業にとって、事業成長のための資金調達は避けて通れない課題です。金融機関からの融資や増資はもちろんですが「補助金」や「助成金」も活用できれば心強い武器になります。
ですが「補助金」という名称は知っていても「補助金や助成金の違いは?」「たくさんあってどれを選べばいいかわからない」「設立直後の会社でも使えるの?」などの疑問が解決できず活用できていないケースが意外と多いのです。
本記事では、法人の設立を検討・準備している、あるいは設立直後の中小企業向けに、補助金・助成金の基本から、会社設立・創業時に活用できる主な制度、申請にあたっての注意点まで解説します。
法人の設立時・創業時に申請できる補助金・助成金を解説

- 補助金・助成金の基礎知識
- 補助金とは?
- 助成金とは?
- 会社設立・創業時に利用できる補助金・助成金
- 小規模事業者持続化補助金
- IT導入補助金
- 創業助成金(東京都など地方自治体)
- キャリアアップ助成金(厚生労働省)
- 補助金・助成金の申請にあたっての注意点
- 1. 必ず受給できるわけではない(補助金の場合)
- 2. 申請条件が細かく設定されていること
- 3. 申請の提出書類準備、結果報告など手続きがあり申請が通らないと労力が無駄になる可能性
- 4. 先行して資金が必要になる可能性がある(支出してから補助金が支払われるケースなど)
- GVA 補助金診断なら自社にあった補助金・助成金を3分で検索
- 補助金・助成金の申請に必要な登記変更や登記簿謄本が必要になっても安心
- 補助金・助成金は準備が肝心
補助金・助成金の基礎知識
補助金と助成金は混同されがちですが明確に異なるものです。前提として共通しているのは、国や地方公共団体が政策目標を達成するために、条件を満たした企業や個人に「返済不要な資金」を提供する制度であるという点です。
補助金とは?
補助金は主に経済産業省(中小企業庁)が管轄しているものが多く、「特定の政策目標に合致する事業活動」を支援する目的で交付されます。例えば、「IT導入による生産性向上」「新たな事業分野への挑戦」「海外への販路開拓」などです。
補助金のおもな特徴は以下の通りです。
- 採択審査があるため交付は確実ではない
- 予算や件数に上限があり、申請された事業計画の優位性や妥当性が厳しく審査されるため不採択となる可能性もあります。
- 公募期間が短い
- 募集期間が限定されていることが多く、情報収集と申請準備を迅速に進める必要があります。
- 事後精算が原則
- 原則として、事業完了後に実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。つまり、先に自己資金で費用を支払い、後から補助金を受け取ります。
- 加点要素あり
- 創業間もない企業や、特定の地域での事業、デジタル化への取り組みなどが加点要素となることがあります。
士業に依頼するなら行政書士
補助金の申請書類作成や事業計画書の作成支援は、行政書士の独占業務の一つです。行政手続きの専門家として、申請者の事業内容や補助金の目的を理解した上で採択されやすい事業計画書の策定、必要な書類の収集・作成をサポートします。
助成金とは?
助成金は主に厚生労働省が管轄しているものが多く、「雇用維持や労働環境改善」に関する取り組みを支援する目的で交付されます。例えば、「従業員のスキルアップ研修」「働き方改革の推進」「特定の雇用(高齢者、障害者など)の促進」などです。
助成金のおもな特徴は以下の通りです。
- 条件に合致すれば確実に受給できる
- 補助金のような競争的な採択審査は少なく、制度が定める要件をきちんと満たし必要な手続きをすれば原則として受給できます。
- 通年で募集
- 補助金と比較して比較的長期間、または通年で募集している制度が多い傾向にあります。
- 事後申請・支給
- 補助金と同様に、取り組みの実施と費用支払い後に申請・支給されるものがほとんどです。
- 労働法規の遵守が前提
- 労働基準法を遵守していること、労働保険(雇用保険・労災保険)に加入していることなど、労働関連の法令順守が前提条件となります。
士業に依頼するなら社会保険労務士
助成金の申請手続きは、社会保険労務士(社労士)の独占業務の一つです。社労士は、労働・社会保険の専門家として、雇用関連の計画策定、労働条件の整備、必要書類の作成・提出をサポートします。
会社設立・創業時に利用できる補助金・助成金
法人の設立・創業というフェーズは、新規事業の機会創出のチャンスであると同時に資金面での課題も抱える時期です。そんな会社設立時に活用しやすい代表的な補助金・助成金をピックアップして紹介します。
※以下で紹介するものは2025年時点の内容になります。補助金によっては申請期間が終了している可能性もあるので各補助金のホームページもご確認ください。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、販路開拓や生産性向上を目的とした取り組み(例:Webサイト制作、チラシ作成、店舗改装、新たな設備の導入など)を行う際に、その経費の一部を補助する制度です。創業間もない企業や個人事業主にとって活用しやすい補助金として知られています。
設立時に使えるポイント: 創業型や通常枠では、設立間もない事業者も対象となるケースがあります。特に、Webサイトを活用した集客や、新しいサービス提供のための初期投資を考えている企業にとって使い勝手が良いでしょう。
活用例
- オンラインショップ開設のための費用
- 新規顧客獲得のための広告費(リスティング広告、SNS広告など)
- 新商品の試作開発費
- 業務効率化のためのソフトウェア導入費
備考・注意点:補助金額は比較的小規模(通常枠で50万円~200万円程度、補助率2/3)ですが、申請要件を満たせば採択される可能性があります。
IT導入補助金
概要:近年利用が増えている制度で、中小企業・小規模事業者が、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際の費用の一部を補助することで、業務効率化や売上向上を支援します。
設立時に使えるポイント:設立直後の企業でも、会計ソフト、顧客管理システム(CRM)、営業支援システム(SFA)、ECサイト構築ツールなどの導入費用を補助対象とすることができます。特にデジタル化を推進したい創業企業に有効です。
活用例
- クラウド会計ソフトの導入費用
- 予約システムや決済システムの導入費用
- テレワーク環境整備のためのITツール導入費用
- セキュリティ対策ソフトの導入費用
備考・注意点: 導入するITツールは、事務局に登録された「IT導入支援事業者」を通じて選定・導入する必要があります。計画書の策定や実績報告も、IT導入支援事業者と連携して行います。補助率や補助上限額は類型によって異なりますが、最大で450万円程度(通常枠)の補助が受けられるケースもあります。
創業助成金(東京都など地方自治体)
概要:国だけでなく、東京都や各地方自治体も、地域経済の活性化を目的として独自の創業支援助成金・補助金を提供しています。これらの制度は、地域に根ざした事業を支援する傾向が強いです。
設立時に使えるポイント:東京都の「創業助成事業」のように、特定の地域内で新たに事業を開始する法人や個人事業主に対して、初期費用の一部(賃料、人件費、広告宣伝費など)を補助する制度があります。金額も補助金の種類によってさまざまです。
活用例
- オフィスの賃借料や内装工事費
- 新たに採用した従業員の人件費
- 事業立ち上げに必要な広告宣伝費や専門家への依頼費用
備考・注意点:募集期間、要件、補助上限額、対象経費は自治体によって大きく異なります。必ず事業所を置く自治体の情報を確認しましょう。
キャリアアップ助成金(厚生労働省)
概要:有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。種類によっては受給できる金額が100万円を超えることもあります。
設立時に使えるポイント:設立直後であっても、非正規雇用の従業員を正規雇用に転換したり、賃金規定を改定して処遇改善を図る場合に活用できます。人材採用を対象にしているので、どんな会社でも利用するチャンスがあります。
活用例
- アルバイトとして採用した従業員を正社員に転換した場合
- 有期雇用労働者の賃金規定を改定し、一定額以上の賃上げを実施した場合
備考・注意点:雇用保険に加入していることや、労働基準法を遵守していることが前提となります。
補助金・助成金の申請にあたっての注意点
補助金や助成金は有効な制度ですが、申請にあたってはいくつかの重要な注意点があります。特に設立・創業直後の会社は人や資金面のリソースが潤沢ではないという点に注意して検討しましょう。
1. 必ず受給できるわけではない(補助金の場合)
助成金が要件を満たせば原則受給できるのに対し、補助金は厳しい審査があるため、申請したからといって必ずしも受給できるわけではありません。多くの事業者が申請し、その中から予算と政策目標に最も合致する事業が選ばれる「競争」の面もあります。
2. 申請条件が細かく設定されていること
ほとんどの補助金・助成金には、対象となる事業者(設立時期、資本金、従業員数、所在地など)や、対象となる事業内容、経費など、詳細な申請条件が設定されています。これらの条件を一つでも満たさない場合、申請自体が受理されないか、審査の対象外となってしまいます。
3. 申請の提出書類準備、結果報告など手続きがあり申請が通らないと労力が無駄になる可能性
補助金・助成金の申請には、事業計画書、見積書、決算書、定款など、膨大な量の書類準備が必要です。これらは正確かつ網羅的に作成・収集する必要があり、非常に時間と労力がかかります。また、採択された後も、中間報告や実績報告書、経費の証拠書類の提出など、煩雑な手続きが続きます。もし不採択となった場合、これらの準備にかかった時間や労力が「無駄」になってしまうリスクがあることを認識しておく必要があります。
4. 先行して資金が必要になる可能性がある(支出してから補助金が支払われるケースなど)
補助金・助成金は、原則として「事後精算」です。つまり、事業に必要な経費を自己資金で先に支払い、事業完了後に実績報告を行い、その審査が通って初めて補助金が支払われます。このため、一時的であっても自己資金で全額を賄えるだけの資金力が必要となります。
GVA 補助金診断なら自社にあった補助金・助成金を3分で検索
GVA 補助金診断なら会社の人数や、投資を検討している内容を選択するだけで3分で受給可能性のある補助金・助成金をで検索できます。利用したい補助金が見つかったら、申請にあたっての相談や、書類作成などのコンサルティングを受けることも可能です。
本記事で解説したとおり、補助金はその申請経験の有無が重要な手続きです。自分でやってみて、条件に合致しなかったり、リソースを確保できないといった問題を先回りしてチェックしたりアドバイスが得られるのは大きなメリットです。かけた時間や労力が無駄になってしまうリスクを減らせます。
また、もし補助金・助成金の活用に伴って法人の変更登記や商標登録などの手続きが発生する場合は「GVA 法人登記や」や「GVA 商標登録」など各サービスで支援も可能です。
→GVA 補助金診断はこちら
補助金・助成金の申請に必要な登記変更や登記簿謄本が必要になっても安心
補助金や助成金の申請における添付書類の代表格が法人の登記簿謄本(登記事項証明書)です。
書類の用意はもちろんですが、その内容にも注意が必要なことをご存知でしょうか?
- 補助金対象の自治体に本店や支店の登記が必要になる
- 補助金の対象となる事業目的が登記簿謄本内にも記載されていなかった
- 代表者や役員の住所変更時の登記を申請しておらず、古いままになっていた
このようなことがあれば、審査通過以前の問題ですし、慌てて登記申請したとしても補助金申請の締切に間に合わないという可能性があります。
今後補助金申請を検討している方は、現在の登記簿謄本の内容を確認して、必要なら時間に余裕をもって変更登記を申請しておきましょう。
GVA 法人登記なら、Web上から変更する情報を入力すれば書類を作成、法務局に行かずに自分で登記申請できます。
そして、登記簿謄本の取得ならGVA 登記簿取得がおすすめです。
メールアドレスだけで会員登録でき、使い慣れたクレジットカードで、数分の手続きで登記簿謄本の請求ができます。
補助金・助成金は準備が肝心
補助金・助成金の申請では申請内容の入力以外にもさまざまな手続きが必要です。時間をかけて申請対象を絞り込み、受給後の対応も含め念入りな準備が必要です。後から必要なものに気づいて慌てて対応することのないよう、準備は計画的に行いましょう。