取締役の競業避止義務とは、取締役が会社と競合する事業に従事することを制限する義務のことです。この義務は、会社の利益を守るために非常に重要です。しかし、「どこまでが競業にあたるのか」「退任後はどうなるのか」など、実務上の判断に迷うケースも少なくありません。本記事では、取締役の競業避止義務の基本的な考え方から、義務の定め方、契約の有効性を判断する重要なポイントを解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
競業避止義務の基礎知識:法律の背景と運用のポイント
競業避止義務とは、取締役本人が自社と競合する事業を行うことを禁止や制限する義務です。この義務は、企業の機密情報や競争力の保護において重要な役割を果たします。ここでは、その具体的な内容と範囲について解説します。
競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)の定義と法律上の位置付け
競業避止義務は、会社法第356条第1項第1号に基づき、取締役が自社と競合する事業に従事することを制限する義務です。会社法では、取締役が以下の行為を行う場合、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を得ることが求められます。
1. 取締役が自己または第三者のために、会社の事業に関する取引をしようとする場合
2. 取締役が自己または第三者のために株式会社と取引をしようとする場合
3. 株式会社が取締役の債務を保証することその他、取締役以外の者との間において株式会社と当該取
締役との利益が相反する取引をしようとする場合
これらの行為は、取締役による地位の濫用を防ぎ、会社の経営資源や競争優位性を守るために制限されています。
参考:「e-Gov 法令検索」会社法第356条第1項第1号
競業避止義務の適用範囲
競業避止義務の範囲は、取締役の在任中と退任後で異なります。
在任中の競業避止義務
取締役は在任中、取締役会の承認がない限り、自社の事業と類似した分野で他社の取締役や経営陣として従事すること、あるいは自社と競合する事業に直接関与することが禁止されています。
ただし、取締役会の承認を得れば、これらの行為が認められます。承認を得る際には、取引に関する重要な情報の開示と、当該取引が会社の利益に反しないことの説明が不可欠です。
退任後の競業避止義務
退任後の競業避止義務については、会社法に明確な規定はありません。しかし、実務的には多くの企業が契約や就業規則により、取締役の退任後一定期間について競業制限を定めています。これは企業の機密情報や競争力を守るための重要な措置であり、この制限を設けることで、退任後も企業の利益を保護することができます。
●競業避止義務違反で想定されるリスクと法的責任(267文字)
競業避止義務に違反した場合、取締役は以下の法的責任を負うことになります。
- 損害賠償責任:取締役が競業避止義務に違反し、会社に損害を与えた場合、取締役はその損害を賠償する責任を負います(会社法第423条第1項)。
- 利益返還義務:取締役が競業取引によって得た利益は、会社の損害と推定され、賠償する責任を負います(会社法第423条第2項)。
会社法は、このような責任規定を通じて、競業避止義務の実効性を確保しています。
競業避止義務のルール策定:誓約書と実務対応のポイント
競業避止義務を実効性のあるものにするためには、自社の事情に応じた適切な方法で明文化することが重要です。
競業避止義務の誓約書や規定作成の具体例
競業避止義務の定め方に関して、法律で明確な規定は設けられていません。そのため、企業は自社のリスクや運営方針に基づき、柔軟にルールを設定する必要があります。
実務では、以下の方法が一般的に用いられています。
1. 誓約書を利用する方法
競業避止義務を文書化し、対象者の同意を得ることで、義務の明確化と責任の所在を示します。委任契約書の中で規定する場合もあります。
2. 就業規則に記載する方法
取締役には通常適用されませんが、全従業員に統一的に適用可能で、会社全体の規範として有効です。
3. 誓約書と就業規則の併用
個別のケースに対応しつつ、全体として統一したルールを設定できる方法です。特に、退任後の競業制限を確実にする場合に適しています。
いずれの方法を選ぶ場合も、競業避止の範囲や期間を必要最小限に抑え、退職金の上乗せなどの金銭的な補償(代償措置)を設けるなど、取締役の権利を不当に制限しないよう配慮することが重要です。契約書や誓約書を作成する場合は、弁護士などの専門家のアドバイスを受け、内容を適切に調整することをお勧めします。
競業避止義務の誓約書を作成するパターン
競業避止義務を個別に設定する方法として、誓約書を作成し、取締役から同意を得る手法があります。
この方法は、以下のようなメリットがあります。
・義務の明確化
競業避止義務の具体的な範囲や期間を文書化することで、双方がルールを明確に理解できるため、
トラブルを防止できます。
・個別対応が可能
取締役の役割や状況に応じて、柔軟に義務の内容を調整できます。
・責任の所在を明確にできる
署名や同意を得ることで、取締役自身の責任が明確になります。
以下は、退職後の競業を禁止する条項を含む誓約書のテンプレート例です。
競業避止義務に関する誓約書(テンプレート例)
第1条(競業避止義務)
1. 在任中および退職後[X]年間、当社の事前の書面による承諾なく、以下の行為を行わないことを
誓約します。
(1) 当社と競合する[○○○○]事業を自ら行うこと
(2) 当社と競合する[○○○○]事業を行う他社の役員、従業員、または顧問となること
(3) 当社の顧客、取引先、または従業員を勧誘すること
(4) 当社の営業秘密やノウハウを使用または第三者に開示すること
2. 前項の競業避止義務の対象となる地理的範囲は、[具体的な地域]とします。
第2条(代償措置)
1. 当社は、本誓約に基づく競業避止義務の対価として、退職金とは別に金[○○]円を支払うものと
します。
第3条(損害賠償)
1. 本誓約に違反した場合、私は当社に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
第4条(合意管轄)
1. 本誓約に関する紛争については、[○○]地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに
同意します。
署名欄
年 月 日
氏名 印
注意点
この誓約書はテンプレートであり、運用時には以下の点を確認することが推奨されます。
1. 内容の合理性
競業避止義務の範囲や期間は、必要最小限に設定し、法的に合理的であることを確認してくださ
い。
2. 代償措置の適切性
競業避止義務の対価として十分な代償措置が設定されていることにより有効性が認められやすくな
る場合があります。例:退職金の上乗せ。
3. 地理的範囲と期間の具体化
競業避止義務の適用範囲(地理的範囲)や期間を明確に記載することで、法的リスクを軽減しま
す。
4. 専門家の助言
弁護士などの専門家に相談し、自社の状況に応じた適切な内容に調整することをお勧めします。
競業避止義務を就業規則に明記するパターン
就業規則に競業避止義務の規定を設ける方法は、全従業員に一律に適用できる効率的な手段です。ただし、取締役には適用されない場合もありますので注意ください。
この方法には以下の特徴とメリットがあります。
・全社的に適用可能
就業規則に競業避止義務を定めることで、すべての従業員に統一したルールを適用できます。これ
により、全社的なコンプライアンス体制が強化されます。
・管理が効率的
一度規定を整備すれば、個別の誓約書作成が不要となり、運用管理の手間を大幅に削減できます。
・ルールが透明
就業規則は全従業員に周知されるため、ルールが明確で、従業員間の公平性が保たれます。
以下は、就業規則に記載する競業避止義務条項のテンプレート例です。
必要に応じて、自社の就業規則の該当箇所に追加してください。
就業規則のテンプレート例
第X条(競業避止義務)
1. 従業員は、在職中及び退職後[X]年間、会社の事前の書面による承諾なく、以下の行為を行っては
ならない。
(1)会社と競合する[○○○○]事業を自ら行うこと
(2)会社と競合する[○○○○]事業を行う他社の役員、従業員、または顧問となること
(3)会社の顧客、取引先、または従業員を勧誘すること
(4)会社の営業秘密やノウハウを使用または第三者に開示すること
2. 前項の競業避止義務の対象地域及び期間は、合理的な範囲内で定め、[業種または役割]に応じて調
整するものとする。
3. 会社は、本条に基づく競業避止義務の対価として、別途定める基準に従い、退職金とは別に金銭
を支払うものとする。
4. 本条に違反した場合、会社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
注意点
この就業規則のテンプレートは参考例であり、実際の運用では以下の点を確認してください。
1. 内容の合理性
競業避止義務の範囲や期間は、必要最小限に抑えることが重要です。過度な制約は無効とされる可
能性があります。
2. 代償措置の明確化
競業避止義務を課す際には、適切な代償措置(例:退職金の上乗せや特別手当など)を設定し、従
業員との合意を明確にしておくことで有効性が認められやすくなる場合があります。
3. 法改正への対応
就業規則の内容が最新の法規制に適合していることを定期的に確認する必要があります。
4. 専門家の助言
就業規則の改定や新規導入にあたっては、弁護士などの専門家に相談し、自社の実情に合わせて調
整してください。
誓約書と就業規則を併用するパターン(1236文字)
誓約書と就業規則を併用することで、個別の事情に対応しつつ、全体に統一したルールを設定できるため、競業避止義務をより効果的に運用できます。この方法は、法的拘束力と実効性を高める強力なアプローチで、次のようなメリットがあります。
・包括的な規定
全体に適用するルールは就業規則で定め、個別の条件や詳細は誓約書で補足することで、柔軟性と
一貫性を両立できます。
・柔軟な対応が可能
取締役や重要な従業員に対して、より具体的で厳格な競業避止義務を課すことが可能です。
・法的拘束力の強化
就業規則が土台を提供し、誓約書が個別の拘束力を補完することで、義務の効果を最大限に高めま
す。
以下が、就業規則と誓約書のテンプレート例です。
就業規則の記載例
第X条(競業避止義務)
1. 取締役及び従業員は、在職中および退職後[X]年間、会社の利益を損なう以下の競業行為を行っては
ならない。
・会社と競合する[○○○○]事業を自ら行うこと
・会社と競合する[○○○○]事業を行う他社の役員、従業員、または顧問となること
・会社の顧客、取引先、または従業員を勧誘すること
・会社の営業秘密やノウハウを第三者に開示または使用すること
2. 前項の競業避止義務の具体的な条件および内容については、別途定める誓約書によるものとする。
3. 会社は、本条に基づく競業避止義務の対価として、別途定める基準に従い、適切な代償措置を講じ
るものとする。
4. 本条に違反した場合、会社に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
誓約書の記載例
第1条(競業避止義務)
1. 在職中および退職後[X]年間、当社の事前の書面による承諾なく、以下の行為を行わないことを誓
約します。
(1)当社と競合する[○○○○]事業を自ら行うこと
(2)当社と競合する[○○○○]事業を行う他社の役員、従業員、または顧問となること
(3)当社の顧客、取引先、または従業員を勧誘すること
(4)当社の営業秘密やノウハウを第三者に開示または使用すること
第2条(代償措置)
1. 当社は、本誓約に基づく競業避止義務の対価として、退職金とは別に金[○○]円を支払うものとし
ます。
第3条(損害賠償)
1. 本誓約に違反した場合、私は当社に生じた損害を賠償する責任を負うものとします。
第4条(合意管轄)
1. 本誓約に関する紛争については、[○○]地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに
同意します。
署名欄
年 月 日
氏名 印
注意点
1. 整合性の確保
誓約書の内容が就業規則の規定と矛盾しないように注意してください。矛盾があると、法的拘束力
が弱まる可能性があります。
2. 代償措置の明記
競業避止義務を課す際には、適切な代償措置(例:退職金の上乗せや特別手当)を明記すること
で、義務の合理性を確保します。
3. 合理性の確保
競業避止義務の範囲、期間、地理的条件が適切であることを確認してください。過剰な制約は無効
となる可能性があります。
4. 専門家の助言
就業規則や誓約書を新規導入・改定する際には、弁護士などの専門家に相談し、自社の実情や法的
リスクを考慮した調整を行うことが推奨されます。
競業避止義務契約を有効にするための6つの条件
競業避止義務契約が有効と認められるためには、企業の利益を保護しつつ、従業員の職業選択の自由を不当に制限しない合理的な契約内容である必要があります。ここでは、その判断基準となる6つのポイントを解説します。
企業利益を守る競業避止義務契約の判断基準
競業避止義務契約において、企業秘密やノウハウの保護は最も重要な判断基準です。これらは企業の競争力の源であり、適切な保護が必要不可欠です。どのような企業秘密やノウハウが法的保護の対象となり得るのか、具体的な判断基準と実務上の留意点について以下に解説していきます。
① 守るべき企業の利益があるか
競業避止義務契約の有効性を判断する際、着目すべき点は、企業に保護すべき正当な「利益」が存在するかどうかです。
不正競争防止法上の営業秘密だけでなく、営業方法、指導方法、顧客情報といった営業活動上の財産も「利益」です。また、顧客との人的関係など、企業活動を通じて得られた資産も「利益」に含まれます。中でも、長期間にわたって確立された独自性の高いノウハウや技術は、特に重要な保護対象として認められやすい傾向にあります。
② 従業員の地位
契約の対象となる従業員が、企業の機密情報やノウハウにアクセスしていたか、その役職が守るべき利益に直接関与していたかが重要です。形式的な職位ではなく、具体的な業務内容と役割が重視されます。一方で、重要な情報に関与しない従業員に広範な競業避止義務を課すことは、合理性を欠くと判断される場合があります。
③ 地域的な限定があるか
競業避止義務の地理的な範囲は、使用者の事業内容や展開地域に応じて合理的に設定される必要があります。たとえば、全国展開する企業では広範な制限が認められる場合もありますが、無制限の地域指定は無効とされる可能性があります。
ただし、地理的な制限が明確に定められていない場合でも、契約が全体として無効になるとは限りません。競業禁止の対象が「特定の業務内容」や「具体的な顧客接触」に限定されている場合や、存続期間が短期間であれば、合理性が認められるケースもあります。このように、地理的な制限は、契約の合理性を判断する要素の一つに過ぎないといえます。
④ 競業避止義務の存続期間
競業避止義務の期間は、一般的に1年以内が合理的とされており、判例でも1年以内の期間は肯定的に評価されることが多く、2年以上の期間については否定的な判断が増えています。
ただし、守るべき企業利益が明確で、業界や事業の特性から合理的な理由が認められる場合には、2年以上でも有効とされることがあります。
⑤ 禁止される競業行為の範囲について必要な制限があるか
禁止される行為の範囲は、具体的かつ限定的であることが重要です。業界事情や従業員の職務内容に応じて競業禁止の対象を合理的に絞ることで、契約の有効性が高まります。
競業企業への転職を「業界全般」や「全ての競合企業」といった広範な表現で一律に禁止する規定は、過剰な制約として無効とされる可能性が高くなります。
一方、「在職中に担当した顧客との取引を禁止する」や、「特定の業務・役職に基づく競業行為の制限」など、具体的な範囲を定めた規定であれば、合理性が認められやすい傾向にあります。
⑥ 代償措置が講じられているか
競業避止義務を課すためには、退職金の上乗せや特別手当など、義務を負う従業員への適切な補償(代償措置)が求められます。これは、義務の合理性を担保し、契約が無効とされるリスクを軽減するためです。
判例では、代償措置がない場合には、契約が無効とされることが多く、補償の設定は契約の実効性を確保する上で重要です。ただし、代償措置が明確でなくても、高額な報酬や特別待遇が「みなし代償措置」として認められたり、ほかの判断基準により総合的に合理性が判断されることがあります。
企業が競業避止義務を課す際には、退職金や特別手当といった明確な代償措置を設けることが望ましく、補償が十分でない場合でも、報酬体系やその他の待遇を総合的に検討することが必要です。
ここまで解説してきたように、競業避止義務契約の有効性を確保するためには、6つの要素を総合的に考慮し、契約内容を合理的かつ明確に設計することが重要です。
競業避止義務の実務運用で重要なチェックポイント
競業避止義務契約を効果的に運用するには、以下のポイントを十分に理解しておく必要があります。
1. 企業利益の保護
競業避止義務契約は、企業の秘密情報やノウハウを守るためのものです。契約内容の合理性を確保
し、保護すべき利益を具体的に明示します。
2. 従業員の地位と役割
競業避止義務の対象は、機密情報や重要な役割にアクセスする従業員に限定します。
3. 地理的範囲と存続期間
契約で定める地理的制限や存続期間は、1年以内の期間が一般的に認められやすく、事業地域や業務
内容に応じた合理的な制限を設けます。
4. 代償措置の設置
退職金の上乗せや特別手当など、競業避止義務に対する適切な補償を明確に設けることで、契約の
有効性を担保します。
実務においては、契約内容が従業員の職業選択の自由を不当に制約しないかを常に確認し、弁護士などの専門家の助言を得ることで、リスクを最小化することが重要です。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
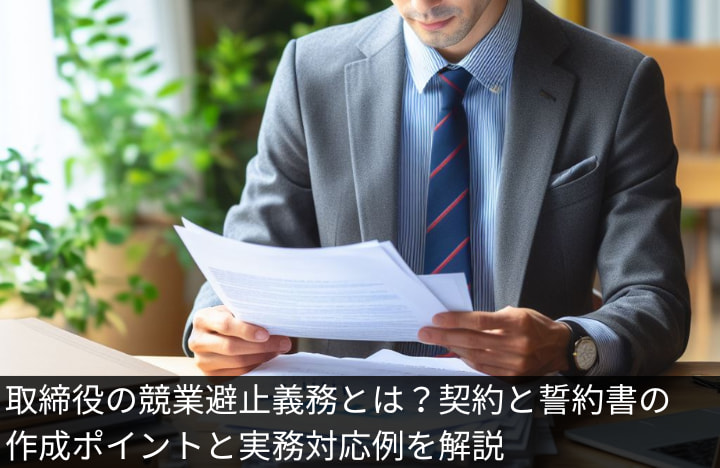


.jpg)



