「資本政策」は経営においてたまに耳にする言葉ですが、しっかりとしたイメージが沸かないという方も多いのではないでしょうか。実際、資本政策には多くの手法や注意点がありますので、資本政策を立案する際に考慮すべきポイントを総合的に把握しておくと良いでしょう。
そこでこの記事では、資本政策の総合的な理解に繋がるよう、資本政策の意味や概要・資本政策の方法・資本政策を実施する際のポイントなどについて詳しく解説します。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
資本政策とは?
まずは「資本政策」とはどういったものか、概要を説明します。「資金調達」との違いについても解説します。
資本政策とは?
資本政策とは、株式数や資本の増減により、資金調達・株主構成の最適化・利害関係者の利益調整の実現などの目的を達成するための手続きや活動全般のことです。資本政策には実施のメリットだけではなく議決権の希薄化など多くの問題もあり、それぞれの要素がトレードオフの関係にあります。
資本政策について考えられる手法や目的は多岐に渡り、その推進には様々な専門知識が必要です。
資金調達との違い
資本政策とよく似た概念として資金調達があります。資金調達は、資金借入れ以外には、第三者割当増資などの新株の発行又は自己株式の処分により行われるのが一般的です。第三者割当増資などについては株主の異動を伴うケースもあり、資金借入れ以外の資金調達は資本政策に含まれる概念であると考えられます。
ただし、資金借入れは通常、資本政策に含まれませんが、例えば財務戦略の一つである新株予約権付社債の発行は資金借入れであると同時に資本政策の一環でもあると考えられます。
資本政策の目的・背景
この章では資本政策の目的・背景、なぜ資本政策が必要なのか解説します。
資金の調達
増資には第三者割当増資・株主割当増資・公募増資があり、これらは主に資金調達を目的に行われますが、株主の変化を伴います。増資を行うにあたって資本政策の面から特に重要なポイントは、増資前と増資後の各株主の持ち株比率です。各株主の適切な持ち株比率を検討するためには、株主総会の普通決議と特別決議に必要な議決権比率を押さえておく必要があります。
- 普通決議:議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもってなされる。
- 特別決議:当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行われる。さらにこの決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることができる。
また種類株式を発行している場合は、株式の種類にも注目しておく必要があります。
新興企業などでは、起業直後に1回ではなく複数回増資を行う流れが多いので、各増資における増資額や株式発行数をしっかりと計画した上で、増資を実施することが重要です。
従業員のインセンティブ設計
ストックオプション制度とは、企業が役職員に対して、あらかじめ決められた価格(行使価格)で企業の株式を購入する権利を付与する仕組みのことです。このストックオプション制度は資本政策の一環として用いられ、主に役職員のインセンティブ設計の役割を担います。
株主構成の管理
資本政策を行う上で考慮すべき事項として株主構成の管理が挙げられます。特に長期的に株式を保有する株主の存在は大きなポイントです。
中小企業では将来の事業承継に備えた株主の集中化の観点からも長期的に株式を保有する株主の存在は重要です。一般的に株主が多い企業ほど、長期的な事業計画に基づいた経営が難しい可能性があります。その点からも意図しない株主の増加は防止するべきです。
その他中堅企業などでMBOを行うと、経営権が集中するため、長期的な経営戦略を立てることができ、企業の成長に繋がりえます。MBOとは、Management Buy-Outの略で、経営者が会社の株式を購入して独立することです。
さらに事業上、シナジーが発生するような株主による経営参画も企業の成長に繋がると考えられます。シナジーとは2つ以上の企業又は事業が統合することで、それぞれが単独で運営されるよりも、生み出される価値が大きくなる(「1+1」以上の価値が生じる)相乗効果のことです。
IPOやM&Aに備えた準備
IPOは、Initial Public Offeringの略で、直訳すると「(株式の)最初の社会的提供」となります。それまでは創業者自身とVCなどプロの投資家に閉じていた新株発行と資金調達の対象を、広く一般社会へと公開・拡大するものです。M&Aとは、「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略称です。
これらに備えた準備としての資本政策は主に上場前後の企業で検討されます。例えば従業員持株会などです。
またIPOを経ることで株式の一般投資家への提供がなされます。既存株主へのキャピタルゲインを提供するためにもEXITのデザインが緻密に行われる必要があります。
※キャピタルゲインとは株式など保有している資産を売却することによって得られる売買差益のことで、EXITとは、未上場企業などの創業者・出資者が株式を売却し投資資金の回収を行うことです。
資本政策において用いられる手法
資本政策において用いられる手法には様々な選択肢があります。この章で詳しく説明します。
会社設立時の持株比率の設計
会社設立時の創業者の持株比率や株主構成は後の資本政策に大きな影響を与えます。また創業直後の増資についてはシリーズごとにどの程度の増資をどのように行うのかしっかりと計画する必要があります。
新株の発行(増資)
資本政策として公募増資が行われるケースもありますが、多くの場合は株主割当増資や第三者割当増資が用いられます。種類株式や新株予約券付社債などを発行する場合もあります。
株式分割
資本政策として株式分割が実施されるケースもあります。株式分割が実施されると、一般的に株価の上昇がもたらされます。また株式分割は株主数の増加に備え、株式数を増加させておくためにも用いられます。
新株予約権の発行
先述したストックオプション制度も資本政策における手法の一つです。
その他
特に上場している場合は、自社株買いも資本政策の手法として活用されています。
資本政策の失敗事例と注意点
この章では資本政策の失敗事例と注意点を説明します。今後の資本政策に活かしてください。
創業時の株式数や持株比率のミス
一般的に資本政策の実施内容を後から修正するのは非常に難しいです。自分以外の創業者との共同設立であっても、役割と責任に応じて持株比率にはしっかりと差をつけた方が良いでしょう。株式割合が均一になり過ぎないように注意して下さい。
また、スタートアップにおけるエンジェル投資家など、直接経営に貢献しない人たちの持ち株比率を高くしすぎないことも重要です。創業メンバーが途中退社することもふまえて、退社時の株式の扱いを定めた創業者間契約の締結も有効な方法です。
強気・弱気なバリュエーションによる資金調達のハードル上昇
企業価値を高く見積もり過ぎると株式の発行価格が高価なものとなり、今後の増資が実施しにくくなります。これは株式上場・企業買収などのEXITの株価にも影響します。ただし、弱気になりすぎることで、発行できる株式数が確保できない可能性もあるため注意が必要です。
持株比率のバランス悪化による経営への悪影響
外部株主により多くの議決権が付与されると経営への悪影響も懸念されます。少なくとも、意思決定のスピードと自由度には大きく影響します。
ストックオプション行使による従業員への影響
ストックオプション制度のデメリットとして、IPOがなされた後に主戦力となっていた役員や従業員が大勢辞めてしまうといった事態が想定されます。行使条件や時期を定めることで行使タイミングを調整するなどの対策も必要でしょう。
意図しない株主が増えてしまう
相続のタイミング等には、株主が予想外に増加する可能性があります。非上場の場合は、株式の譲渡制限などの予防措置を事前に講じておく必要があります。場合によってはスクイーズアウトなどの手法が必要になる可能性があります。
資本政策は状況に合わせた適切な計画に基づき実施しましょう
資本政策には様々な方法があります。よく調べて、どの方法が自社に合っているかを見極め、資本政策を成功させてください。
銀行からの融資とは異なり、株式による資金調達は直接返済する義務はありません。ただし、安易に増資を実施すると、株主の利益を失い、事業を成長させる機会も失われる可能性がありますので、注意が必要です。
今回の記事が皆様の資本政策に関する理解を深めるきっかけとなれば幸いです。
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます
法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。
GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。

GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
.jpg)
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。
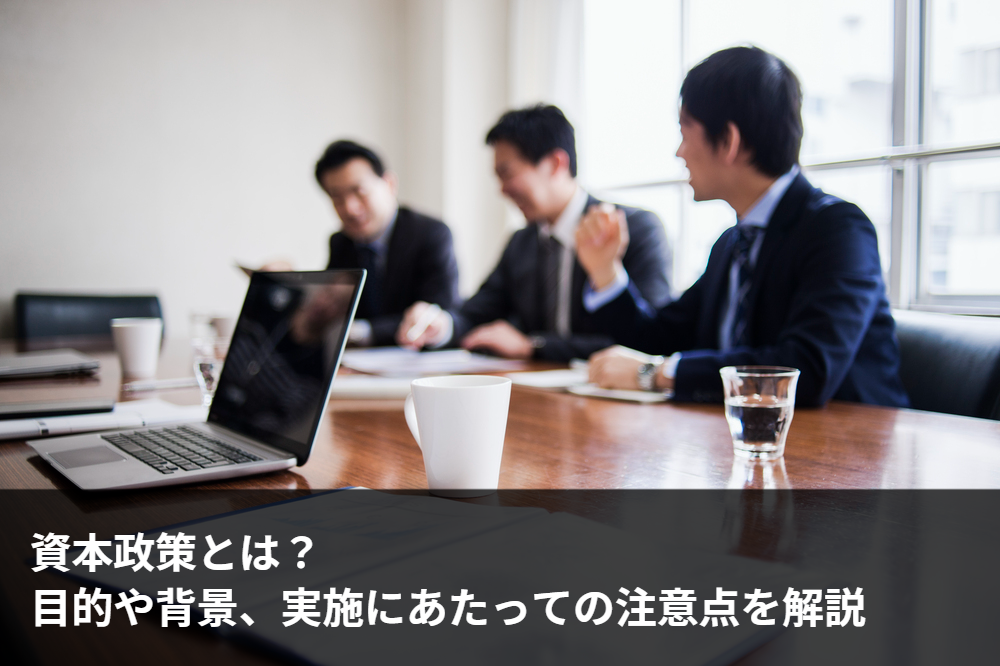


.jpg)



